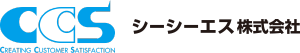光と色の話 第一部

第19回 虹の色
・・・・・ 光の屈折による発色現象 ・・・・・
自然界における発色原理には幾つかの種類があります。最も一般的な発色原理は照明光の波長毎の物体による選択的反射(透過)・吸収特性によるものです(本連載第 12 回、第 13 回参照)。今回から数回にわたって、それ以外の発色原理によるものを採り挙げてみましょう。
雨上がりの空にかかった半円形の美しい虹の架け橋に感動した記憶は誰しもが持っていることでしょう。虹は、大気中に浮かんだ無数の微小な水滴群によって太陽の光が屈折した結果として現れる、ということは子供の頃教わった記憶がありますね。しかし、具体的にどのような仕掛けであのように半円形の美しい縞模様が見えるのかまでは、具体的に教わる機会は意外に少ないようです。人知を超えた大自然の壮大な芸術の一端を覗いてみましょう。

光の屈折現象
器の中に棒を立てかけた場面を考えてみましょう。器の中が空の場合には当然棒はまっすぐな直線状に見えます。ところが、器の中に水を入れると、水面のところから棒が折れ曲がって浮き上がったように見えますね。これが光の屈折現象として観察される典型的な場面です。なぜこのように折れ曲がって見えるのでしょうか?

例えば水中の棒の先端部分から発した光は、水面に達して空気層へ抜け出すところで、進行方向が水面に近づく方向に折れ曲がり、その光が観察者の眼に入射してきます。観察者の方から見ると、その光は水面で折れ曲がって来ていることは分からず、あたかも眼に入射してくる方向の延長線上から一直線で来ているように見えます。その結果、棒は水面から下の部分が浮き上がったように屈曲した虚像として見えることになります。

このように、異なる二種の透明媒質の境界(界面と言います)では光が屈折するのですが、この屈折の度合いは両媒質の光学的特性(屈折率 n )の組み合わせ、および界面への入射角度 θi によって決まります。これを理論的に記述したものがスネルの法則( Snell’s law )です。
屈折率が小さい媒質(例えば空気:屈折率 n1 )から屈折率が大きい媒質(例えば水:屈折率 n2 > n1 )に光が進行する場合は、光は界面から遠ざかる方向に屈折します。光が水から空気へ進行する場合には、上記とは全く逆のコースを進行し界面に近づく方向に屈折します。
更にもう少し詳しく正確に言いますと、媒質の屈折率 n は、光の波長によって異なる値をとり、波長が短くなるほど屈折率 n は大きくなります。つまり、界面への入射光が様々な波長成分を持った白色光である場合、界面で屈折した光は波長成分毎に屈折方向が異なることになり、短波長成分ほど大きく屈折することになります。

空気中に浮遊する水滴による屈折と反射
雨上がりの空には無数の水滴が浮かんでいます。これらの水滴群に太陽の光(白色光)が入射すると、水滴の表面で屈折現象が起こります。屈折した光は波長によって異なる方向に進行し水滴の内面の別の場所で空気との界面に達し、そこで殆どの成分は鏡面反射されます。(一部は界面を通過して空気中へ抜けます。)界面で反射した光は進行方向を変えて再び空気との界面に達し、空気中へ屈折して抜け出して行きます。つまり、水滴へ入射した太陽光は屈折・反射・屈折という過程を経て空気中へ再放出される訳です。その結果、図のように、例えば可視域短波長成分(紫色に見える)は太陽からの入射光方向に対して約40°の角度で折り返すことになり、可視域長波長成分(赤く見える)は入射光方向に対して約42°の角度で折り返すことになります。このような現象が、空中に浮遊している水滴の全てで同時に生じている訳です。

虹が見える仕組み
上記の無数の屈折現象を、観察する側の眼から見るとどのように見えるでしょうか。下図の赤の直線上に存在する水滴群から眼の方向に向かって降り注いでくる光は、長波長光(赤)の光のみとなります。これらの水滴群からの赤より短い波長成分の光は観察者の眼には入らずに頭の上を通過してしまいます。また、下図の紫色の直線上に存在する水滴群から眼の方向に向かって降り注いでくる光は、短波長光(紫)の光のみとなります。これらの水滴群からの紫より長い波長成分の光は観察者の眼より下の足元の方に来ている訳です。
以上の現象が生じる条件は、光源(太陽)と水滴群と観察者の位置関係において、眼を円錐の頂点とする角度のみによって決まることが分かります。すなわち、光源(太陽)と観察者(眼)によって決まる方向を中心軸として、水滴群によって屈折・分光された光が円錐方向に 40° ~ 42° の範囲に波長の順番で並ぶことになります。その結果、同心円状の七色≪※1≫の虹が観察されるわけですね。

虹が観察される条件
虹の発生原理は上述のように太陽と観察者と水滴群の三者の位置関係が特定の条件になった場合に観察されます。太陽(光源)は必ず虹を見ている人(観察者)の背後から射しており、虹の円弧の中心は、太陽と観察者を結ぶ直線の延長線上にあります。つまり、空中の水滴群と観察者と太陽(光源)との位置関係は特定の条件で結び付けられており、この相対的位置関係が成り立てば、雨上がりの空以外でも虹は発生することになります。例えば、瀑布にかかった虹や、霧吹きで霧を作った場合などに見える虹なども例外ではありません。

円形の虹
一般に、虹が半円形の架け橋のように見えるのは、通常は円形の下半分は大地にかかりますので、屈折を起こす水滴が存在しないためです。従って、崖の上から瀑布を眺めたような時に見える虹は、足元より下方向にも水滴群が存在しますので、半円形よりももっと円に近い虹が見えます。更に、飛行機から見える虹は、視界全体に水滴群が広がっていますので「まん丸」の虹が見えます。

虹の架け橋は決してくぐることはできない
以上の説明からわかりますように、虹が見える条件は、光源と水滴群と観察者の位置関係が角度条件のみで決まる訳ですから、虹の架け橋の下をくぐることは不可能です。観察者が虹の下へ移動しようとすれば、それまで観察者の眼に入射していた虹の光は眼に入らず頭上を通過してしまい、観察者が移動した距離だけ離れた別の水滴群からの屈折光が眼に入ることになります。つまり(水滴群が存在する限り)いくら移動しても、常に同じ方向に虹が観察されることになるからです。
副虹
空にかかった虹を注意深く観察すると、目立つ虹の外側に同心円状にうっすらともう一つの虹が見えることがあります。目立つ方の虹は主虹、外側のうっすらと見える虹は副虹と呼ばれています。
そして、虹の色の順番が主虹と副虹は異なっていることが分かります。主虹は外側が赤、内側が紫になっているのに対して、副虹は外側が紫、内側が赤となっており、色の順序がちょうど逆になっています。また、主虹と副虹に挟まれた中間の空は主虹の下側、あるいは副虹の上側の空よりも幾分暗く見えます。この暗い領域は「アレキサンダーの暗帯」≪※2≫と呼ばれています。

水滴における屈折・反射のパターン
空中に浮遊する水滴で発生する光の屈折および反射の仕方には、実は二通りのパターンがあります。主虹の原因となる屈折・反射のパターンは上述のように、屈折→反射→屈折という順序で起こるものです。もう一つのパターンは、屈折→反射→反射→屈折という順序で起こるもので反射が1回多いものです。水滴によって分光されて観察者の方向に返される光は、2 回の反射の結果、長波長光(赤)は太陽光方向に対して約 51° の角度をなし、短波長光(紫)はそれ以上の角度をなすことになります。この後者のパターンが副虹の原因で、51° という角度が主虹の場合の 42° という角度よりも大きいため、副虹は主虹の外側に見えます。
反射が 1 回多いことによって、水滴から返される光の波長(色)毎の角度の順序が逆転し、観察者の眼から見ると、副虹は主虹の場合とは逆に、円弧の外側が紫、内側が赤に見えるという訳です。

水滴内の反射現象では、界面への入射角度が全反射の起こる角度よりも小さい(臨界角よりも小さい)ため、一部は空気中へ抜けてしまいます。従って、反射回数が1回多い副虹は、観察者方向へ返される光が主虹の場合よりも弱くなってしまうため、あまり鮮やかには見えないことになってしまいます。
また、主虹と副虹に挟まれた領域(アレキサンダーの暗帯)に浮遊する水滴群でも、全く同様な二通りのパターンの屈折・反射現象が発生しているのですが、反射 1 回パターンの光は全て観察者の頭上を通過し、反射 2 回パターンの光は観察者の足元の方を通過することになり、いずれも眼に直接入射することはありません。従って、「アレキサンダーの暗帯」 は周囲の空に比べて暗く見えてしまうことになります。

注釈
≪※1≫ 虹の色数
日本では虹の色は「七色」と表現されることが多いですね。しかし、虹の色数の表現はその民族やその国の歴史的文化的背景により様々で、五色とか三色とかで表現されるところもあります。虹の発生原理からわかりますように、虹の色は水滴群によって可視域の光が波長毎に分光され、多数の単色光が波長の順序に並んだ形で観察されるものですから、可視域をいくつに分割するかという問題になる訳で、七色に分割するのが正しいとか正しくないということではありません。
日本でも古代には虹を五色と表現していたということですが、明治以降、学校教育でニュートンの虹の研究をもとに七色と教えたことにより、今では殆どの日本人は七色と表現するようになったようです。ニュートンは当然ながら、虹は白色光が分光されて多数の単色光が配列された結果であることを知っていましたが、これを敢えて七つに分割して表現したのは、当時の英国での社会通念が関係していたようです。当時の英国では、“ 7 ” が聖なる数と考えられており、音楽でも 1 オクターブを 7 つの音階(ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ)に分割していたことに倣って、虹の色を七色と表現したということです。
≪※2≫ アレキサンダーの暗帯
「アレキサンダーの暗帯」は、古代ギリシャの哲学者のアレキサンダー( B.C.356 ~ 323 )によって初めて記述されたことから、このように呼ばれるようになったそうです。
光と色の話 第一部

第19回 虹の色
・・・・・ 光の屈折による発色現象 ・・・・・
自然界における発色原理には幾つかの種類があります。最も一般的な発色原理は照明光の波長毎の物体による選択的反射(透過)・吸収特性によるものです(本連載第 12 回、第 13 回参照)。今回から数回にわたって、それ以外の発色原理によるものを採り挙げてみましょう。
雨上がりの空にかかった半円形の美しい虹の架け橋に感動した記憶は誰しもが持っていることでしょう。虹は、大気中に浮かんだ無数の微小な水滴群によって太陽の光が屈折した結果として現れる、ということは子供の頃教わった記憶がありますね。しかし、具体的にどのような仕掛けであのように半円形の美しい縞模様が見えるのかまでは、具体的に教わる機会は意外に少ないようです。人知を超えた大自然の壮大な芸術の一端を覗いてみましょう。

光の屈折現象
器の中に棒を立てかけた場面を考えてみましょう。器の中が空の場合には当然棒はまっすぐな直線状に見えます。ところが、器の中に水を入れると、水面のところから棒が折れ曲がって浮き上がったように見えますね。これが光の屈折現象として観察される典型的な場面です。なぜこのように折れ曲がって見えるのでしょうか?

例えば水中の棒の先端部分から発した光は、水面に達して空気層へ抜け出すところで、進行方向が水面に近づく方向に折れ曲がり、その光が観察者の眼に入射してきます。観察者の方から見ると、その光は水面で折れ曲がって来ていることは分からず、あたかも眼に入射してくる方向の延長線上から一直線で来ているように見えます。その結果、棒は水面から下の部分が浮き上がったように屈曲した虚像として見えることになります。

このように、異なる二種の透明媒質の境界(界面と言います)では光が屈折するのですが、この屈折の度合いは両媒質の光学的特性(屈折率 n )の組み合わせ、および界面への入射角度 θi によって決まります。これを理論的に記述したものがスネルの法則( Snell’s law )です。
屈折率が小さい媒質(例えば空気:屈折率 n1 )から屈折率が大きい媒質(例えば水:屈折率 n2 > n1 )に光が進行する場合は、光は界面から遠ざかる方向に屈折します。光が水から空気へ進行する場合には、上記とは全く逆のコースを進行し界面に近づく方向に屈折します。
更にもう少し詳しく正確に言いますと、媒質の屈折率 n は、光の波長によって異なる値をとり、波長が短くなるほど屈折率 n は大きくなります。つまり、界面への入射光が様々な波長成分を持った白色光である場合、界面で屈折した光は波長成分毎に屈折方向が異なることになり、短波長成分ほど大きく屈折することになります。

空気中に浮遊する水滴による屈折と反射
雨上がりの空には無数の水滴が浮かんでいます。これらの水滴群に太陽の光(白色光)が入射すると、水滴の表面で屈折現象が起こります。屈折した光は波長によって異なる方向に進行し水滴の内面の別の場所で空気との界面に達し、そこで殆どの成分は鏡面反射されます。(一部は界面を通過して空気中へ抜けます。)界面で反射した光は進行方向を変えて再び空気との界面に達し、空気中へ屈折して抜け出して行きます。つまり、水滴へ入射した太陽光は屈折・反射・屈折という過程を経て空気中へ再放出される訳です。その結果、図のように、例えば可視域短波長成分(紫色に見える)は太陽からの入射光方向に対して約40°の角度で折り返すことになり、可視域長波長成分(赤く見える)は入射光方向に対して約42°の角度で折り返すことになります。このような現象が、空中に浮遊している水滴の全てで同時に生じている訳です。

虹が見える仕組み
上記の無数の屈折現象を、観察する側の眼から見るとどのように見えるでしょうか。下図の赤の直線上に存在する水滴群から眼の方向に向かって降り注いでくる光は、長波長光(赤)の光のみとなります。これらの水滴群からの赤より短い波長成分の光は観察者の眼には入らずに頭の上を通過してしまいます。また、下図の紫色の直線上に存在する水滴群から眼の方向に向かって降り注いでくる光は、短波長光(紫)の光のみとなります。これらの水滴群からの紫より長い波長成分の光は観察者の眼より下の足元の方に来ている訳です。
以上の現象が生じる条件は、光源(太陽)と水滴群と観察者の位置関係において、眼を円錐の頂点とする角度のみによって決まることが分かります。すなわち、光源(太陽)と観察者(眼)によって決まる方向を中心軸として、水滴群によって屈折・分光された光が円錐方向に 40° ~ 42° の範囲に波長の順番で並ぶことになります。その結果、同心円状の七色≪※1≫の虹が観察されるわけですね。

虹が観察される条件
虹の発生原理は上述のように太陽と観察者と水滴群の三者の位置関係が特定の条件になった場合に観察されます。太陽(光源)は必ず虹を見ている人(観察者)の背後から射しており、虹の円弧の中心は、太陽と観察者を結ぶ直線の延長線上にあります。つまり、空中の水滴群と観察者と太陽(光源)との位置関係は特定の条件で結び付けられており、この相対的位置関係が成り立てば、雨上がりの空以外でも虹は発生することになります。例えば、瀑布にかかった虹や、霧吹きで霧を作った場合などに見える虹なども例外ではありません。

円形の虹
一般に、虹が半円形の架け橋のように見えるのは、通常は円形の下半分は大地にかかりますので、屈折を起こす水滴が存在しないためです。従って、崖の上から瀑布を眺めたような時に見える虹は、足元より下方向にも水滴群が存在しますので、半円形よりももっと円に近い虹が見えます。更に、飛行機から見える虹は、視界全体に水滴群が広がっていますので「まん丸」の虹が見えます。

虹の架け橋は決してくぐることはできない
以上の説明からわかりますように、虹が見える条件は、光源と水滴群と観察者の位置関係が角度条件のみで決まる訳ですから、虹の架け橋の下をくぐることは不可能です。観察者が虹の下へ移動しようとすれば、それまで観察者の眼に入射していた虹の光は眼に入らず頭上を通過してしまい、観察者が移動した距離だけ離れた別の水滴群からの屈折光が眼に入ることになります。つまり(水滴群が存在する限り)いくら移動しても、常に同じ方向に虹が観察されることになるからです。
副虹
空にかかった虹を注意深く観察すると、目立つ虹の外側に同心円状にうっすらともう一つの虹が見えることがあります。目立つ方の虹は主虹、外側のうっすらと見える虹は副虹と呼ばれています。
そして、虹の色の順番が主虹と副虹は異なっていることが分かります。主虹は外側が赤、内側が紫になっているのに対して、副虹は外側が紫、内側が赤となっており、色の順序がちょうど逆になっています。また、主虹と副虹に挟まれた中間の空は主虹の下側、あるいは副虹の上側の空よりも幾分暗く見えます。この暗い領域は「アレキサンダーの暗帯」≪※2≫と呼ばれています。

水滴における屈折・反射のパターン
空中に浮遊する水滴で発生する光の屈折および反射の仕方には、実は二通りのパターンがあります。主虹の原因となる屈折・反射のパターンは上述のように、屈折→反射→屈折という順序で起こるものです。もう一つのパターンは、屈折→反射→反射→屈折という順序で起こるもので反射が1回多いものです。水滴によって分光されて観察者の方向に返される光は、2 回の反射の結果、長波長光(赤)は太陽光方向に対して約 51° の角度をなし、短波長光(紫)はそれ以上の角度をなすことになります。この後者のパターンが副虹の原因で、51° という角度が主虹の場合の 42° という角度よりも大きいため、副虹は主虹の外側に見えます。
反射が 1 回多いことによって、水滴から返される光の波長(色)毎の角度の順序が逆転し、観察者の眼から見ると、副虹は主虹の場合とは逆に、円弧の外側が紫、内側が赤に見えるという訳です。

水滴内の反射現象では、界面への入射角度が全反射の起こる角度よりも小さい(臨界角よりも小さい)ため、一部は空気中へ抜けてしまいます。従って、反射回数が1回多い副虹は、観察者方向へ返される光が主虹の場合よりも弱くなってしまうため、あまり鮮やかには見えないことになってしまいます。
また、主虹と副虹に挟まれた領域(アレキサンダーの暗帯)に浮遊する水滴群でも、全く同様な二通りのパターンの屈折・反射現象が発生しているのですが、反射 1 回パターンの光は全て観察者の頭上を通過し、反射 2 回パターンの光は観察者の足元の方を通過することになり、いずれも眼に直接入射することはありません。従って、「アレキサンダーの暗帯」 は周囲の空に比べて暗く見えてしまうことになります。

注釈
≪※1≫ 虹の色数
日本では虹の色は「七色」と表現されることが多いですね。しかし、虹の色数の表現はその民族やその国の歴史的文化的背景により様々で、五色とか三色とかで表現されるところもあります。虹の発生原理からわかりますように、虹の色は水滴群によって可視域の光が波長毎に分光され、多数の単色光が波長の順序に並んだ形で観察されるものですから、可視域をいくつに分割するかという問題になる訳で、七色に分割するのが正しいとか正しくないということではありません。
日本でも古代には虹を五色と表現していたということですが、明治以降、学校教育でニュートンの虹の研究をもとに七色と教えたことにより、今では殆どの日本人は七色と表現するようになったようです。ニュートンは当然ながら、虹は白色光が分光されて多数の単色光が配列された結果であることを知っていましたが、これを敢えて七つに分割して表現したのは、当時の英国での社会通念が関係していたようです。当時の英国では、“ 7 ” が聖なる数と考えられており、音楽でも 1 オクターブを 7 つの音階(ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ)に分割していたことに倣って、虹の色を七色と表現したということです。
≪※2≫ アレキサンダーの暗帯
「アレキサンダーの暗帯」は、古代ギリシャの哲学者のアレキサンダー( B.C.356 ~ 323 )によって初めて記述されたことから、このように呼ばれるようになったそうです。
光と色の話 第一部

第19回 虹の色
・・・・・ 光の屈折による発色現象 ・・・・・
自然界における発色原理には幾つかの種類があります。最も一般的な発色原理は照明光の波長毎の物体による選択的反射(透過)・吸収特性によるものです(本連載第 12 回、第 13 回参照)。今回から数回にわたって、それ以外の発色原理によるものを採り挙げてみましょう。
雨上がりの空にかかった半円形の美しい虹の架け橋に感動した記憶は誰しもが持っていることでしょう。虹は、大気中に浮かんだ無数の微小な水滴群によって太陽の光が屈折した結果として現れる、ということは子供の頃教わった記憶がありますね。しかし、具体的にどのような仕掛けであのように半円形の美しい縞模様が見えるのかまでは、具体的に教わる機会は意外に少ないようです。人知を超えた大自然の壮大な芸術の一端を覗いてみましょう。

光の屈折現象
器の中に棒を立てかけた場面を考えてみましょう。器の中が空の場合には当然棒はまっすぐな直線状に見えます。ところが、器の中に水を入れると、水面のところから棒が折れ曲がって浮き上がったように見えますね。これが光の屈折現象として観察される典型的な場面です。なぜこのように折れ曲がって見えるのでしょうか?

例えば水中の棒の先端部分から発した光は、水面に達して空気層へ抜け出すところで、進行方向が水面に近づく方向に折れ曲がり、その光が観察者の眼に入射してきます。観察者の方から見ると、その光は水面で折れ曲がって来ていることは分からず、あたかも眼に入射してくる方向の延長線上から一直線で来ているように見えます。その結果、棒は水面から下の部分が浮き上がったように屈曲した虚像として見えることになります。

このように、異なる二種の透明媒質の境界(界面と言います)では光が屈折するのですが、この屈折の度合いは両媒質の光学的特性(屈折率 n )の組み合わせ、および界面への入射角度 θi によって決まります。これを理論的に記述したものがスネルの法則( Snell’s law )です。
屈折率が小さい媒質(例えば空気:屈折率 n1 )から屈折率が大きい媒質(例えば水:屈折率 n2 > n1 )に光が進行する場合は、光は界面から遠ざかる方向に屈折します。光が水から空気へ進行する場合には、上記とは全く逆のコースを進行し界面に近づく方向に屈折します。
更にもう少し詳しく正確に言いますと、媒質の屈折率 n は、光の波長によって異なる値をとり、波長が短くなるほど屈折率 n は大きくなります。つまり、界面への入射光が様々な波長成分を持った白色光である場合、界面で屈折した光は波長成分毎に屈折方向が異なることになり、短波長成分ほど大きく屈折することになります。

空気中に浮遊する水滴による屈折と反射
雨上がりの空には無数の水滴が浮かんでいます。これらの水滴群に太陽の光(白色光)が入射すると、水滴の表面で屈折現象が起こります。屈折した光は波長によって異なる方向に進行し水滴の内面の別の場所で空気との界面に達し、そこで殆どの成分は鏡面反射されます。(一部は界面を通過して空気中へ抜けます。)界面で反射した光は進行方向を変えて再び空気との界面に達し、空気中へ屈折して抜け出して行きます。つまり、水滴へ入射した太陽光は屈折・反射・屈折という過程を経て空気中へ再放出される訳です。その結果、図のように、例えば可視域短波長成分(紫色に見える)は太陽からの入射光方向に対して約40°の角度で折り返すことになり、可視域長波長成分(赤く見える)は入射光方向に対して約42°の角度で折り返すことになります。このような現象が、空中に浮遊している水滴の全てで同時に生じている訳です。

虹が見える仕組み
上記の無数の屈折現象を、観察する側の眼から見るとどのように見えるでしょうか。下図の赤の直線上に存在する水滴群から眼の方向に向かって降り注いでくる光は、長波長光(赤)の光のみとなります。これらの水滴群からの赤より短い波長成分の光は観察者の眼には入らずに頭の上を通過してしまいます。また、下図の紫色の直線上に存在する水滴群から眼の方向に向かって降り注いでくる光は、短波長光(紫)の光のみとなります。これらの水滴群からの紫より長い波長成分の光は観察者の眼より下の足元の方に来ている訳です。
以上の現象が生じる条件は、光源(太陽)と水滴群と観察者の位置関係において、眼を円錐の頂点とする角度のみによって決まることが分かります。すなわち、光源(太陽)と観察者(眼)によって決まる方向を中心軸として、水滴群によって屈折・分光された光が円錐方向に 40° ~ 42° の範囲に波長の順番で並ぶことになります。その結果、同心円状の七色≪※1≫の虹が観察されるわけですね。

虹が観察される条件
虹の発生原理は上述のように太陽と観察者と水滴群の三者の位置関係が特定の条件になった場合に観察されます。太陽(光源)は必ず虹を見ている人(観察者)の背後から射しており、虹の円弧の中心は、太陽と観察者を結ぶ直線の延長線上にあります。つまり、空中の水滴群と観察者と太陽(光源)との位置関係は特定の条件で結び付けられており、この相対的位置関係が成り立てば、雨上がりの空以外でも虹は発生することになります。例えば、瀑布にかかった虹や、霧吹きで霧を作った場合などに見える虹なども例外ではありません。

円形の虹
一般に、虹が半円形の架け橋のように見えるのは、通常は円形の下半分は大地にかかりますので、屈折を起こす水滴が存在しないためです。従って、崖の上から瀑布を眺めたような時に見える虹は、足元より下方向にも水滴群が存在しますので、半円形よりももっと円に近い虹が見えます。更に、飛行機から見える虹は、視界全体に水滴群が広がっていますので「まん丸」の虹が見えます。

虹の架け橋は決してくぐることはできない
以上の説明からわかりますように、虹が見える条件は、光源と水滴群と観察者の位置関係が角度条件のみで決まる訳ですから、虹の架け橋の下をくぐることは不可能です。観察者が虹の下へ移動しようとすれば、それまで観察者の眼に入射していた虹の光は眼に入らず頭上を通過してしまい、観察者が移動した距離だけ離れた別の水滴群からの屈折光が眼に入ることになります。つまり(水滴群が存在する限り)いくら移動しても、常に同じ方向に虹が観察されることになるからです。
副虹
空にかかった虹を注意深く観察すると、目立つ虹の外側に同心円状にうっすらともう一つの虹が見えることがあります。目立つ方の虹は主虹、外側のうっすらと見える虹は副虹と呼ばれています。
そして、虹の色の順番が主虹と副虹は異なっていることが分かります。主虹は外側が赤、内側が紫になっているのに対して、副虹は外側が紫、内側が赤となっており、色の順序がちょうど逆になっています。また、主虹と副虹に挟まれた中間の空は主虹の下側、あるいは副虹の上側の空よりも幾分暗く見えます。この暗い領域は「アレキサンダーの暗帯」≪※2≫と呼ばれています。

水滴における屈折・反射のパターン
空中に浮遊する水滴で発生する光の屈折および反射の仕方には、実は二通りのパターンがあります。主虹の原因となる屈折・反射のパターンは上述のように、屈折→反射→屈折という順序で起こるものです。もう一つのパターンは、屈折→反射→反射→屈折という順序で起こるもので反射が1回多いものです。水滴によって分光されて観察者の方向に返される光は、2 回の反射の結果、長波長光(赤)は太陽光方向に対して約 51° の角度をなし、短波長光(紫)はそれ以上の角度をなすことになります。この後者のパターンが副虹の原因で、51° という角度が主虹の場合の 42° という角度よりも大きいため、副虹は主虹の外側に見えます。
反射が 1 回多いことによって、水滴から返される光の波長(色)毎の角度の順序が逆転し、観察者の眼から見ると、副虹は主虹の場合とは逆に、円弧の外側が紫、内側が赤に見えるという訳です。

水滴内の反射現象では、界面への入射角度が全反射の起こる角度よりも小さい(臨界角よりも小さい)ため、一部は空気中へ抜けてしまいます。従って、反射回数が1回多い副虹は、観察者方向へ返される光が主虹の場合よりも弱くなってしまうため、あまり鮮やかには見えないことになってしまいます。
また、主虹と副虹に挟まれた領域(アレキサンダーの暗帯)に浮遊する水滴群でも、全く同様な二通りのパターンの屈折・反射現象が発生しているのですが、反射 1 回パターンの光は全て観察者の頭上を通過し、反射 2 回パターンの光は観察者の足元の方を通過することになり、いずれも眼に直接入射することはありません。従って、「アレキサンダーの暗帯」 は周囲の空に比べて暗く見えてしまうことになります。

注釈
≪※1≫ 虹の色数
日本では虹の色は「七色」と表現されることが多いですね。しかし、虹の色数の表現はその民族やその国の歴史的文化的背景により様々で、五色とか三色とかで表現されるところもあります。虹の発生原理からわかりますように、虹の色は水滴群によって可視域の光が波長毎に分光され、多数の単色光が波長の順序に並んだ形で観察されるものですから、可視域をいくつに分割するかという問題になる訳で、七色に分割するのが正しいとか正しくないということではありません。
日本でも古代には虹を五色と表現していたということですが、明治以降、学校教育でニュートンの虹の研究をもとに七色と教えたことにより、今では殆どの日本人は七色と表現するようになったようです。ニュートンは当然ながら、虹は白色光が分光されて多数の単色光が配列された結果であることを知っていましたが、これを敢えて七つに分割して表現したのは、当時の英国での社会通念が関係していたようです。当時の英国では、“ 7 ” が聖なる数と考えられており、音楽でも 1 オクターブを 7 つの音階(ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ)に分割していたことに倣って、虹の色を七色と表現したということです。
≪※2≫ アレキサンダーの暗帯
「アレキサンダーの暗帯」は、古代ギリシャの哲学者のアレキサンダー( B.C.356 ~ 323 )によって初めて記述されたことから、このように呼ばれるようになったそうです。