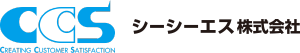光と色の話 第一部

第38回 色彩の心理 (その1)
・・・・・ 暗順応、明順応、色順応 ・・・・・
「光と色」は私たち人間の活動にとって極めて重要で、切っても切れない存在であることがこれまでの連載でもある程度お分かり頂けると思います。これまでは、「光と色」について主に物理的な側面からお話を進めてきましたが、今回から心理的、生理的な側面にもスポットを当ててみたいと思います。
色の心理的効果の伝達過程
人間の色の感じ方の大きな流れについては、本連載第 14 回で「色感覚」と「色知覚」という効果を中心にお話しましたが、その部分の註釈≪※1≫色情報の心理的効果の伝達過程において、更に「色感情効果」への発展にも少し触れました。
視覚機能の入り口の部分での心理物理的効果である「色感覚効果」が大脳へ伝達されて処理される過程で、興味深い色の見え方が生じてきます。私たちは日常、様々な色の組み合わせの中で生活していますので、異なる色刺激が空間的に隣接して同時に、あるいはまた時間的に相前後して肉眼へ入射してきています。
これら色刺激を網膜上の視細胞で受けて脳で色を認識することになるのですが、その色刺激情報の伝達・認識過程で、色刺激の入射の仕方に応じて視細胞の感度が生理的に変化したり、脳内での認識の仕方が影響を受けたりすることによって、色を単独で見る場合と比べてかなり異なった様相で色が認識されることが起こります。このような段階の色の認識を「色知覚効果」と称しています。

色知覚効果の内、私たちが日常無意識の内に体験しているお馴染みの現象に、各種「順応現象(暗順応、明順応、色順応)」や、複数種の色の差異が強調される「色対比現象」、複数の色が混じり合ってその中間の色になったように見える「色同化現象」等があります。今回は、その内、「順応現象」についてお話します。
暗順応 と 明順応
例えば映画館へ行った時、明るい部屋(明所視状態)から暗い映写室(暗所視状態)に入った直後は、室内のスクリーン以外の周辺や足元は真っ暗で殆ど何も見えません。しかし数分経つ内に、徐々に目が慣れてきて、通路の位置や座席の空き状態も分かってきます。このように、周囲の視環境が明所から暗所に急変した場合、その直後は暗いところがよく見えないのですが、暫くする内に徐々に眼の感度が高まってきて見えるようになってくることを、暗順応( dark adaptation )と言っています。
逆に、映写室(暗所視状態)から外の明るい部屋(明所視状態)へ出ると、その瞬間は眩しくて周囲が見えなくなりますが、じきに正常に見えるようになります。これを明順応( light adaptation )と言っています。
明るさの変化に対して人間の眼は、その感受性(感度)を生理的に調整して、その明るさに「順応」する能力を持っているのですが、明るさの変化する方向によって人間の眼の順応の仕方(応答の速さ)は異っています。
本連載の第 11 回および第 14 回でも触れましたように、人間の視細胞には錐体と杆体があり、明所視では錐体が、暗所視では杆体が機能するように生理的に役割分担しています。
一方、明→暗の変化に対する視細胞の時間応答特性(順応特性)は、錐体が短時間で応答するのに対して、杆体は “ slow response ” で、順応するのに数分から数十分を要します。
これを換言すると、錐体は(明るい所での)明暗の変化には素早く応答するのですが、暗くなると感度不足で見えなくなってしまい、一方、杆体は感度が高くて錐体より暗いところまで見えるのですが、高感度でフル稼働するまでに時間がかかってしまう、ということです。
このような視細胞の感度および時間応答特性が上記の映画館の場合の暗順応、明順応にどのように関与しているのでしょうか。
錐体が機能し、杆体は機能していない映写室外(明所)から、急に映写室内(暗所)に移ると、錐体は暗さに対応しようと生理的に感度を精一杯向上させるのですが、すぐ感度能力の限界に達してしまい、それ以下の暗さでは検知することができません。この時点で、杆体はまだ立ち上がり前で光を検知する準備が整っていないため、結局“眼”としては“真っ暗”にしか見えません。

しかし時間の経過とともに杆体が徐々に稼働し始め、ジワーッと錐体の感度レベルを越えて機能し始めるため、うっすらと暗闇が見え始め、さらに杆体の感度が上がるに従って、暗闇の中の様子(通路の様子や座席の空き状態)が分かってくるようになります。数十分経つと杆体の感度レベルも周囲の暗さに完全に順応した安定状態になります。
この状態(暗所に順応した状態)から映写室外(明所)に移動すると、そこは光が充満していますので、それまで高感度状態で機能してきた杆体に明所の多量の光が入射し、杆体の検知出力は一気に飽和してしまいます。これが、「眩しい」という感覚であって、何も見えない(杆体が機能しない)状態になります。しかし、これは一瞬で、明所で応答速度の速い錐体がすぐに明るさの変化に順応して、杆体に代わって機能するようになって正常に見えるようになる訳です。
このような人間の眼の暗順応・明順応に対応した例として、トンネル内の照明があります。
長いトンネル内では照明灯の設置間隔は均等ではなく、入口、出口に近い程、設置間隔が短く、トンネル中央部に行くほど間隔が長くなっていることに気がついた人も多いと思います。これはトンネルでの事故防止のための対応です。

昼間の明るいトンネル外からトンネルに入ると、(照明が不足すると)急に暗くなったと感じ、運転者の眼が慣れる(暗順応する)までは、視界が暗くて見通しが効かず、下手をすると事故に繋がりかねません。そこで、トンネルの入口近くでは、照明の設置間隔を短くして、できるだけ明るさを確保することによって、トンネル外との明るさのギャップを少なくして、視界が見えないという状態に陥らないようにしています。トンネルの奥へ進むに従って(時間が経過して)、暗順応が進んで暗くてもそこそこ見えるようになってきますので、照明の設置間隔は入口ほど密にする必要がなくなります。
暗いトンネルから明るい外へ出る時は、明順応が起こりますが、一瞬でも眩しくて視界が見えないとやはり危険ですので、明るさの変化をできるだけ少なくするためにトンネル内の出口近くは照明の設置間隔を密にしてあります。トンネル内は双方向通行が多いので、結果的に照明設置間隔はトンネル中央を中心にして対称ということになります。≪※1≫
色順応
眼の順応現象は視環境の「明るさ」だけではなく、「色」に対しても起こります。
例えば今、昼白色蛍光灯( ex. 相関色温度 5000 K )の下で白い紙を見ているとします。この状態で蛍光灯を消して、瞬時に白熱灯( ex. 色温度 2800 K )に切り替えたとします。昼白色蛍光灯と白熱灯の分光分布はそれぞれ下図のような特性で、白熱灯の方が長波長成分(赤味成分)がかなり多いため、切り替え直後は、紙の色が少し赤味を帯びたように見えます。しかし、じきにそのような感覚は無くなり、元の蛍光灯の下で見ていたのと同じような白に見えるようになります。
このような現象が色順応( color adaptation )です。

本連載第 12 回で説明しましたように、物体の色は「光源」、「物体」、「視覚」で決まります(物体色の 3 要素)が、光源と物体の 2 つの要素は物理的特性のみで決まるのに対して、視覚の要素は人間の眼と脳の生理的・心理的要素が関係してきます。
人間の感覚器官の感度は、(その本人は意識しない中で)外界からの物理的刺激変化を緩和しようとする生理的応答特性を持っています。≪※2≫
昼白色蛍光灯下で「白」と認識しているということは、視細胞の S 、 M 、 L 錐体の受ける刺激応答量がほぼ均等で、その結果、脳が「白」と判断していることになります。
この状態で蛍光灯から白熱灯に切り替えると、光源の分光分布の違いのため、長波長光が支配的になり、(照度変化が僅少であれば) L 錐体への刺激が急増、 S 錐体への刺激が急減するため、切り替え直後は赤味を帯びた色として認識されます。この刺激急変を緩和するように、 L 錐体の感度が鈍化し、 S 錐体の感度が鋭敏化する生理的反応(順応)が起こります。
その結果、蛍光灯下での S 、 M 、 L 錐体の刺激応答量比と同じ程度となり、脳は蛍光灯下での場合と同じような「白」と認識するに至る訳です。

色順応 と カメラのホワイトバランス機能
人間の眼にはこのような生理的な色順応が起こりますが、「機械の眼」ではどうでしょう。
最近のカメラは殆どがデジタルカメラになっていますが、このデジタルカメラには「ホワイトバランス」という機能が備わっていますね。このホワイトバランス機能をオートモードで使う場合が人間の眼の「色順応」に対応していると言えます。
写真撮影時の被写体照明光には様々な光源があり得ますが、光源の種類毎にその色味(色温度)も様々です。従って照明光源が異なれば、同一の被写体であっても、被写体からカメラへの反射光の分光分布は光源の種類に直接依存して変化します。
カメラの撮像素子は、可視域を3つの波長帯に分けた3種の画素群( B 、 G 、 R )から成っていますが、これら B 、G 、R 画素の感度が固定であれば、照明光源の色味(分光分布)の違いが撮像結果にストレートに影響を及ぼしてしまいます。
下の作例写真①、②、③をご覧下さい。
これらはカメラのホワイトバランスをマニュアルモードで 5000 K に設定( B 、G 、R の撮像素子を所定感度に固定)して、異種の色味(色温度)の光源・・・・・写真① は 2700 K の(赤っぽい)照明光、
写真②は、5000 K の(白っぽい)照明光、写真③は 8500 K(青白っぽい)照明光・・・・・で撮影したものです。撮影結果に照明光の色味(色温度)が大きく影響しているのがよく分かります。≪※3≫

ところが、この撮影現場にいる人間が見る色は、写真①や③のようには見えず、どの照明光でも写真②のように、ほぼ同じような自然な色調に見えています。
これは、照明光の色味の差異を抑えるように人間の眼では色順応が働いているからです≪※4≫
マニュアルでホワイトバランスを設定する場合、色温度値で指定しますが、これは、設定した色温度の照明光で撮影すると、画面全体の色バランスがとれた状態で、すなわち「白い紙が白く写る」ことを意味しています。写真②では照明光の色温度がホワイトバランス設定値( 5000 K )に一致しているため、色順応した肉眼で見たのと同様な自然な色調に仕上がっているということになります。
それに対して、写真①では、設定した色温度値( 5000 K )より低い色温度( 2700 K )の照明光ですので、撮像素子の
B 、G 、R 画素の設定感度に対して照明光の青成分が弱く、赤成分が強いため、撮影結果は(白い紙が)赤味を帯びて写ります。逆に、写真③では設定した色温度値(5000 K )より高い色温度( 8500 K )の照明光ですので、 B 、G 、R 画素の設定感度に対して照明光の青成分が強く、赤成分が弱いため、撮影結果は(白い紙が)青味を帯びて写ります。
ホワイトバランスをオートモードで使用すると、どんな色味の(白色)光源であっても、撮影画面内での撮像素子の B 、G 、R 感光量バランスが概ね均等になるように・・・・・つまり、「白い紙が白く写る」ように・・・・・カメラが B 、G 、R 撮像素子の感度比を自動的に調整しますので、一般的な撮影条件の場合には、照明光源の色味(色温度)をあまり気にせずに、ほぼ失敗なくそこそこのカラー写真が撮影できる訳です。つまり、ホワイトバランスをオートモードで使用する場合が、人間の色順応に対応するということになります。ホワイトバランス機能は、オートとマニュアルを使い分けるようになっています。
一般的にはオートで使われることが多いのですが、照明光の強い色味によってその場の雰囲気が特徴付けられている場合≪※5≫や、意図的に撮影画面全体の色調を演出するような場合等にはホワイトバランスをマニュアルで設定して撮影することになります。≪※6≫
注釈
≪※1≫ トンネルの照明設置間隔
暗順応、明順応対策という観点から考えると、トンネル中央部も出入口と同じ照明設置間隔にしても良いのではないかと思われますが、トンネル内は昼夜通しての点灯になりますので電気代の節約という観点から、安全を確保できる範囲で中央部の設置間隔は広めになっています。
≪※2≫ 人間の感覚器官の順応
明暗や色に対する順応現象は、人間の生物としての環境変化への適応能力の一つとして考えることができるでしょう。外界から生体への物理的刺激は時々刻々変化するものであり、生体の感じる感覚がその変化に忠実に応答するとすれば、間断なく感覚の変化に晒され続けることになり、心が落ち着く暇もないことになってしまいます。このようなストレスを緩和するように、無意識のうちに生理的に感覚器官の感度が調節されるように働く能力を得た結果が順応現象であると言えます。これは視覚に限らず、聴覚や触覚でも同様で、いわば生存のための生体の自己防衛のメカニズムであるとも言えます。
≪※3≫ 写真撮影の場合の「色温度」 ・・・・・ 「写真的色温度」
本連載の第33回で、「色温度」と「相関色温度」の定義を説明致しました。写真撮影に関しての照明光の色味について、今回便宜的に「色温度」という用語を使用しましたが、写真撮影(機械の眼)の場合には、厳密には「色温度」ではなく「写真的色温度」と表現すべきものです。
第33回で説明しました「色温度」も「相関色温度」も共にその色味は「人間の眼」すなわち視細胞
S 、 M 、 L 錐体(+脳)による評価によるものです。カメラの撮像素子( B 、 G 、 R )の分光感度特性は錐体( S 、 M 、 L )と一致している訳ではありませんので、「色温度」、「相関色温度」の定義を写真撮影にそのまま適用することはできません。 そこで、写真撮影時の照明光をカメラの撮像素子で測定した時の B 、R 感光量比に対して、それと同等の B 、R 感光量比を与える黒体の色温度値を借用して表現したものが「写真的色温度」です。
≪※4≫ 順応 と 恒常性
私たちが物体の色を認識する場合、ただ単に物体からの反射(透過)光の強さや分光情報のみで明るさや色を認識している訳ではなく、その物体が何であるか(例えば、紙なのか石なのか、紙の場合でも白い紙なのか赤い紙なのか・・・)、形状や表面状態はどうか、等々も同時に認識しています。
そのような多次元に亘る情報を脳内に蓄積された記憶情報等と無意識の中で参照した結果として物体の色を認識しています。その結果、照明条件、観察条件によってその色刺激が変化しても、その見え方(明るさや色)の変化を抑えるような順応効果・・・心理的生理的応答効果が働きます。
これが恒常性(明るさの恒常性、色恒常性)と呼ばれるもので順応(暗順応、明順応、色順応)と深く関係しています。物体の色に比較して光源の色の場合には、このような恒常性は起こりにくいと言われています。
≪※5≫ オートホワイトバランスによる撮影失敗
無分別にオートホワイトバランスを使うと、大失敗することがありますので注意が必要です。オートホワイトバランスがうまく機能するのは、撮影画面全体の色の分布にあまり偏りが無い場合であり、画面全体が青っぽいとか赤っぽいという場合には、その色調を打ち消すように働いてしまいます。
例えば、夕焼けで真っ赤に染まったシーンを、オートホワイトバランスのまま撮影すると、全く夕焼けのシーンらしくない(昼間に撮影したような赤味の無い)写真に仕上がってしまい、「小さな親切、大きなお世話」 ということになってしまいます。
≪※6≫ カラーフィルム写真(銀塩写真)の場合
最近は使われることが珍しくなってきましたが、カラーフィルム(銀塩フィルム)での撮影では、フィルムには色順応特性がありませんので、光源の分光分布の違いがそのまま撮影された物体の色の変化となって表れます。従って、カラーフィルム写真では、使用する照明光の種類(色温度)によって、フィルムタイプ(デイライトタイプ、タングステンタイプ)を選択する必要があります。
つまり、カラーフィルムは、デジタルカメラにおけるホワイトバランスをマニュアル設定した場合に相当します。デジタルカメラのホワイトバランスをマニュアルで 5500 K に設定すればデイライトタイプのカラーフィルムに相当し、ホワイトバランスを 3200 K に設定すれば、タングステンタイプのカラーフィルムに相当します。実際の場合の照明光の色味(色温度)は様々ですので、選択したカラーフィルムの色温度タイプがピッタリ一致するとは限らず、色温度差に応じて撮影結果の色調に影響が現れてしまいます。撮影意図に対してそれが問題になる場合は、各種濃度の色温度変換フィルタ( LB フィルタ)を用いて色補正を行うことも行われます。使用するフィルムに対して照明光の色温度が高い場合は、色温度を下げる(相対的に短波長成分を削る)色温度変換フィルタを、照明光の色温度が低い場合は、色温度を上げる(相対的に長波長成分を削る)色温度変換フィルタを使用します。
また、色温度変換フィルタとは別に色補正フィルタ( CC フィルタ)というものも準備されています。
例えば、或る種の蛍光ランプなどの場合には、可視域中央部(緑成分)が相対的に強いものもあります。肉眼では色順応によって不自然さは感じないのですが、フィルムで撮影すると緑味を帯びた色調になることがあります。このような場合は、可視域中央部の透過率が相対的に低いマゼンタ色の色補正フィルタ( CC フィルタ)によって色補正を行います。
カラーフィルムには、ネガカラーフィルムとリバーサルカラーフィルムがあります。
ネガカラーフィルムの場合には現像したフィルム(陰画)から焼き付けによって最終写真(陽画)に仕上げる段階である程度色補正が可能ですので、撮影時に多少の照明光の色温度ズレがあっても事後に或る程度の色補正処理は可能です。しかし、リバーサルカラーフィルムの場合には、現像即最終画像(陽画)となりますから、事後の色補正ができず、撮影時の条件設定はより厳しくなります。
光と色の話 第一部

第38回 色彩の心理 (その1)
・・・・・ 暗順応、明順応、色順応 ・・・・・
「光と色」は私たち人間の活動にとって極めて重要で、切っても切れない存在であることがこれまでの連載でもある程度お分かり頂けると思います。これまでは、「光と色」について主に物理的な側面からお話を進めてきましたが、今回から心理的、生理的な側面にもスポットを当ててみたいと思います。
色の心理的効果の伝達過程
人間の色の感じ方の大きな流れについては、本連載第 14 回で「色感覚」と「色知覚」という効果を中心にお話しましたが、その部分の註釈≪※1≫色情報の心理的効果の伝達過程において、更に「色感情効果」への発展にも少し触れました。
視覚機能の入り口の部分での心理物理的効果である「色感覚効果」が大脳へ伝達されて処理される過程で、興味深い色の見え方が生じてきます。私たちは日常、様々な色の組み合わせの中で生活していますので、異なる色刺激が空間的に隣接して同時に、あるいはまた時間的に相前後して肉眼へ入射してきています。
これら色刺激を網膜上の視細胞で受けて脳で色を認識することになるのですが、その色刺激情報の伝達・認識過程で、色刺激の入射の仕方に応じて視細胞の感度が生理的に変化したり、脳内での認識の仕方が影響を受けたりすることによって、色を単独で見る場合と比べてかなり異なった様相で色が認識されることが起こります。このような段階の色の認識を「色知覚効果」と称しています。

色知覚効果の内、私たちが日常無意識の内に体験しているお馴染みの現象に、各種「順応現象(暗順応、明順応、色順応)」や、複数種の色の差異が強調される「色対比現象」、複数の色が混じり合ってその中間の色になったように見える「色同化現象」等があります。今回は、その内、「順応現象」についてお話します。
暗順応 と 明順応
例えば映画館へ行った時、明るい部屋(明所視状態)から暗い映写室(暗所視状態)に入った直後は、室内のスクリーン以外の周辺や足元は真っ暗で殆ど何も見えません。しかし数分経つ内に、徐々に目が慣れてきて、通路の位置や座席の空き状態も分かってきます。このように、周囲の視環境が明所から暗所に急変した場合、その直後は暗いところがよく見えないのですが、暫くする内に徐々に眼の感度が高まってきて見えるようになってくることを、暗順応( dark adaptation )と言っています。
逆に、映写室(暗所視状態)から外の明るい部屋(明所視状態)へ出ると、その瞬間は眩しくて周囲が見えなくなりますが、じきに正常に見えるようになります。これを明順応( light adaptation )と言っています。
明るさの変化に対して人間の眼は、その感受性(感度)を生理的に調整して、その明るさに「順応」する能力を持っているのですが、明るさの変化する方向によって人間の眼の順応の仕方(応答の速さ)は異っています。
本連載の第 11 回および第 14 回でも触れましたように、人間の視細胞には錐体と杆体があり、明所視では錐体が、暗所視では杆体が機能するように生理的に役割分担しています。
一方、明→暗の変化に対する視細胞の時間応答特性(順応特性)は、錐体が短時間で応答するのに対して、杆体は “ slow response ” で、順応するのに数分から数十分を要します。
これを換言すると、錐体は(明るい所での)明暗の変化には素早く応答するのですが、暗くなると感度不足で見えなくなってしまい、一方、杆体は感度が高くて錐体より暗いところまで見えるのですが、高感度でフル稼働するまでに時間がかかってしまう、ということです。
このような視細胞の感度および時間応答特性が上記の映画館の場合の暗順応、明順応にどのように関与しているのでしょうか。
錐体が機能し、杆体は機能していない映写室外(明所)から、急に映写室内(暗所)に移ると、錐体は暗さに対応しようと生理的に感度を精一杯向上させるのですが、すぐ感度能力の限界に達してしまい、それ以下の暗さでは検知することができません。この時点で、杆体はまだ立ち上がり前で光を検知する準備が整っていないため、結局“眼”としては“真っ暗”にしか見えません。

しかし時間の経過とともに杆体が徐々に稼働し始め、ジワーッと錐体の感度レベルを越えて機能し始めるため、うっすらと暗闇が見え始め、さらに杆体の感度が上がるに従って、暗闇の中の様子(通路の様子や座席の空き状態)が分かってくるようになります。数十分経つと杆体の感度レベルも周囲の暗さに完全に順応した安定状態になります。
この状態(暗所に順応した状態)から映写室外(明所)に移動すると、そこは光が充満していますので、それまで高感度状態で機能してきた杆体に明所の多量の光が入射し、杆体の検知出力は一気に飽和してしまいます。これが、「眩しい」という感覚であって、何も見えない(杆体が機能しない)状態になります。しかし、これは一瞬で、明所で応答速度の速い錐体がすぐに明るさの変化に順応して、杆体に代わって機能するようになって正常に見えるようになる訳です。
このような人間の眼の暗順応・明順応に対応した例として、トンネル内の照明があります。
長いトンネル内では照明灯の設置間隔は均等ではなく、入口、出口に近い程、設置間隔が短く、トンネル中央部に行くほど間隔が長くなっていることに気がついた人も多いと思います。これはトンネルでの事故防止のための対応です。

昼間の明るいトンネル外からトンネルに入ると、(照明が不足すると)急に暗くなったと感じ、運転者の眼が慣れる(暗順応する)までは、視界が暗くて見通しが効かず、下手をすると事故に繋がりかねません。そこで、トンネルの入口近くでは、照明の設置間隔を短くして、できるだけ明るさを確保することによって、トンネル外との明るさのギャップを少なくして、視界が見えないという状態に陥らないようにしています。トンネルの奥へ進むに従って(時間が経過して)、暗順応が進んで暗くてもそこそこ見えるようになってきますので、照明の設置間隔は入口ほど密にする必要がなくなります。
暗いトンネルから明るい外へ出る時は、明順応が起こりますが、一瞬でも眩しくて視界が見えないとやはり危険ですので、明るさの変化をできるだけ少なくするためにトンネル内の出口近くは照明の設置間隔を密にしてあります。トンネル内は双方向通行が多いので、結果的に照明設置間隔はトンネル中央を中心にして対称ということになります。≪※1≫
色順応
眼の順応現象は視環境の「明るさ」だけではなく、「色」に対しても起こります。
例えば今、昼白色蛍光灯( ex. 相関色温度 5000 K )の下で白い紙を見ているとします。この状態で蛍光灯を消して、瞬時に白熱灯( ex. 色温度 2800 K )に切り替えたとします。昼白色蛍光灯と白熱灯の分光分布はそれぞれ下図のような特性で、白熱灯の方が長波長成分(赤味成分)がかなり多いため、切り替え直後は、紙の色が少し赤味を帯びたように見えます。しかし、じきにそのような感覚は無くなり、元の蛍光灯の下で見ていたのと同じような白に見えるようになります。
このような現象が色順応( color adaptation )です。

本連載第 12 回で説明しましたように、物体の色は「光源」、「物体」、「視覚」で決まります(物体色の 3 要素)が、光源と物体の 2 つの要素は物理的特性のみで決まるのに対して、視覚の要素は人間の眼と脳の生理的・心理的要素が関係してきます。
人間の感覚器官の感度は、(その本人は意識しない中で)外界からの物理的刺激変化を緩和しようとする生理的応答特性を持っています。≪※2≫
昼白色蛍光灯下で「白」と認識しているということは、視細胞の S 、 M 、 L 錐体の受ける刺激応答量がほぼ均等で、その結果、脳が「白」と判断していることになります。
この状態で蛍光灯から白熱灯に切り替えると、光源の分光分布の違いのため、長波長光が支配的になり、(照度変化が僅少であれば) L 錐体への刺激が急増、 S 錐体への刺激が急減するため、切り替え直後は赤味を帯びた色として認識されます。この刺激急変を緩和するように、 L 錐体の感度が鈍化し、 S 錐体の感度が鋭敏化する生理的反応(順応)が起こります。
その結果、蛍光灯下での S 、 M 、 L 錐体の刺激応答量比と同じ程度となり、脳は蛍光灯下での場合と同じような「白」と認識するに至る訳です。

色順応 と カメラのホワイトバランス機能
人間の眼にはこのような生理的な色順応が起こりますが、「機械の眼」ではどうでしょう。
最近のカメラは殆どがデジタルカメラになっていますが、このデジタルカメラには「ホワイトバランス」という機能が備わっていますね。このホワイトバランス機能をオートモードで使う場合が人間の眼の「色順応」に対応していると言えます。
写真撮影時の被写体照明光には様々な光源があり得ますが、光源の種類毎にその色味(色温度)も様々です。従って照明光源が異なれば、同一の被写体であっても、被写体からカメラへの反射光の分光分布は光源の種類に直接依存して変化します。
カメラの撮像素子は、可視域を3つの波長帯に分けた3種の画素群( B 、 G 、 R )から成っていますが、これら B 、G 、R 画素の感度が固定であれば、照明光源の色味(分光分布)の違いが撮像結果にストレートに影響を及ぼしてしまいます。
下の作例写真①、②、③をご覧下さい。
これらはカメラのホワイトバランスをマニュアルモードで 5000 K に設定( B 、G 、R の撮像素子を所定感度に固定)して、異種の色味(色温度)の光源・・・・・写真① は 2700 K の(赤っぽい)照明光、
写真②は、5000 K の(白っぽい)照明光、写真③は 8500 K(青白っぽい)照明光・・・・・で撮影したものです。撮影結果に照明光の色味(色温度)が大きく影響しているのがよく分かります。≪※3≫

ところが、この撮影現場にいる人間が見る色は、写真①や③のようには見えず、どの照明光でも写真②のように、ほぼ同じような自然な色調に見えています。
これは、照明光の色味の差異を抑えるように人間の眼では色順応が働いているからです≪※4≫
マニュアルでホワイトバランスを設定する場合、色温度値で指定しますが、これは、設定した色温度の照明光で撮影すると、画面全体の色バランスがとれた状態で、すなわち「白い紙が白く写る」ことを意味しています。写真②では照明光の色温度がホワイトバランス設定値( 5000 K )に一致しているため、色順応した肉眼で見たのと同様な自然な色調に仕上がっているということになります。
それに対して、写真①では、設定した色温度値( 5000 K )より低い色温度( 2700 K )の照明光ですので、撮像素子の
B 、G 、R 画素の設定感度に対して照明光の青成分が弱く、赤成分が強いため、撮影結果は(白い紙が)赤味を帯びて写ります。逆に、写真③では設定した色温度値(5000 K )より高い色温度( 8500 K )の照明光ですので、 B 、G 、R 画素の設定感度に対して照明光の青成分が強く、赤成分が弱いため、撮影結果は(白い紙が)青味を帯びて写ります。
ホワイトバランスをオートモードで使用すると、どんな色味の(白色)光源であっても、撮影画面内での撮像素子の B 、G 、R 感光量バランスが概ね均等になるように・・・・・つまり、「白い紙が白く写る」ように・・・・・カメラが B 、G 、R 撮像素子の感度比を自動的に調整しますので、一般的な撮影条件の場合には、照明光源の色味(色温度)をあまり気にせずに、ほぼ失敗なくそこそこのカラー写真が撮影できる訳です。つまり、ホワイトバランスをオートモードで使用する場合が、人間の色順応に対応するということになります。ホワイトバランス機能は、オートとマニュアルを使い分けるようになっています。
一般的にはオートで使われることが多いのですが、照明光の強い色味によってその場の雰囲気が特徴付けられている場合≪※5≫や、意図的に撮影画面全体の色調を演出するような場合等にはホワイトバランスをマニュアルで設定して撮影することになります。≪※6≫
注釈
≪※1≫ トンネルの照明設置間隔
暗順応、明順応対策という観点から考えると、トンネル中央部も出入口と同じ照明設置間隔にしても良いのではないかと思われますが、トンネル内は昼夜通しての点灯になりますので電気代の節約という観点から、安全を確保できる範囲で中央部の設置間隔は広めになっています。
≪※2≫ 人間の感覚器官の順応
明暗や色に対する順応現象は、人間の生物としての環境変化への適応能力の一つとして考えることができるでしょう。外界から生体への物理的刺激は時々刻々変化するものであり、生体の感じる感覚がその変化に忠実に応答するとすれば、間断なく感覚の変化に晒され続けることになり、心が落ち着く暇もないことになってしまいます。このようなストレスを緩和するように、無意識のうちに生理的に感覚器官の感度が調節されるように働く能力を得た結果が順応現象であると言えます。これは視覚に限らず、聴覚や触覚でも同様で、いわば生存のための生体の自己防衛のメカニズムであるとも言えます。
≪※3≫ 写真撮影の場合の「色温度」 ・・・・・ 「写真的色温度」
本連載の第33回で、「色温度」と「相関色温度」の定義を説明致しました。写真撮影に関しての照明光の色味について、今回便宜的に「色温度」という用語を使用しましたが、写真撮影(機械の眼)の場合には、厳密には「色温度」ではなく「写真的色温度」と表現すべきものです。
第33回で説明しました「色温度」も「相関色温度」も共にその色味は「人間の眼」すなわち視細胞
S 、 M 、 L 錐体(+脳)による評価によるものです。カメラの撮像素子( B 、 G 、 R )の分光感度特性は錐体( S 、 M 、 L )と一致している訳ではありませんので、「色温度」、「相関色温度」の定義を写真撮影にそのまま適用することはできません。 そこで、写真撮影時の照明光をカメラの撮像素子で測定した時の B 、R 感光量比に対して、それと同等の B 、R 感光量比を与える黒体の色温度値を借用して表現したものが「写真的色温度」です。
≪※4≫ 順応 と 恒常性
私たちが物体の色を認識する場合、ただ単に物体からの反射(透過)光の強さや分光情報のみで明るさや色を認識している訳ではなく、その物体が何であるか(例えば、紙なのか石なのか、紙の場合でも白い紙なのか赤い紙なのか・・・)、形状や表面状態はどうか、等々も同時に認識しています。
そのような多次元に亘る情報を脳内に蓄積された記憶情報等と無意識の中で参照した結果として物体の色を認識しています。その結果、照明条件、観察条件によってその色刺激が変化しても、その見え方(明るさや色)の変化を抑えるような順応効果・・・心理的生理的応答効果が働きます。
これが恒常性(明るさの恒常性、色恒常性)と呼ばれるもので順応(暗順応、明順応、色順応)と深く関係しています。物体の色に比較して光源の色の場合には、このような恒常性は起こりにくいと言われています。
≪※5≫ オートホワイトバランスによる撮影失敗
無分別にオートホワイトバランスを使うと、大失敗することがありますので注意が必要です。オートホワイトバランスがうまく機能するのは、撮影画面全体の色の分布にあまり偏りが無い場合であり、画面全体が青っぽいとか赤っぽいという場合には、その色調を打ち消すように働いてしまいます。
例えば、夕焼けで真っ赤に染まったシーンを、オートホワイトバランスのまま撮影すると、全く夕焼けのシーンらしくない(昼間に撮影したような赤味の無い)写真に仕上がってしまい、「小さな親切、大きなお世話」 ということになってしまいます。
≪※6≫ カラーフィルム写真(銀塩写真)の場合
最近は使われることが珍しくなってきましたが、カラーフィルム(銀塩フィルム)での撮影では、フィルムには色順応特性がありませんので、光源の分光分布の違いがそのまま撮影された物体の色の変化となって表れます。従って、カラーフィルム写真では、使用する照明光の種類(色温度)によって、フィルムタイプ(デイライトタイプ、タングステンタイプ)を選択する必要があります。
つまり、カラーフィルムは、デジタルカメラにおけるホワイトバランスをマニュアル設定した場合に相当します。デジタルカメラのホワイトバランスをマニュアルで 5500 K に設定すればデイライトタイプのカラーフィルムに相当し、ホワイトバランスを 3200 K に設定すれば、タングステンタイプのカラーフィルムに相当します。実際の場合の照明光の色味(色温度)は様々ですので、選択したカラーフィルムの色温度タイプがピッタリ一致するとは限らず、色温度差に応じて撮影結果の色調に影響が現れてしまいます。撮影意図に対してそれが問題になる場合は、各種濃度の色温度変換フィルタ( LB フィルタ)を用いて色補正を行うことも行われます。使用するフィルムに対して照明光の色温度が高い場合は、色温度を下げる(相対的に短波長成分を削る)色温度変換フィルタを、照明光の色温度が低い場合は、色温度を上げる(相対的に長波長成分を削る)色温度変換フィルタを使用します。
また、色温度変換フィルタとは別に色補正フィルタ( CC フィルタ)というものも準備されています。
例えば、或る種の蛍光ランプなどの場合には、可視域中央部(緑成分)が相対的に強いものもあります。肉眼では色順応によって不自然さは感じないのですが、フィルムで撮影すると緑味を帯びた色調になることがあります。このような場合は、可視域中央部の透過率が相対的に低いマゼンタ色の色補正フィルタ( CC フィルタ)によって色補正を行います。
カラーフィルムには、ネガカラーフィルムとリバーサルカラーフィルムがあります。
ネガカラーフィルムの場合には現像したフィルム(陰画)から焼き付けによって最終写真(陽画)に仕上げる段階である程度色補正が可能ですので、撮影時に多少の照明光の色温度ズレがあっても事後に或る程度の色補正処理は可能です。しかし、リバーサルカラーフィルムの場合には、現像即最終画像(陽画)となりますから、事後の色補正ができず、撮影時の条件設定はより厳しくなります。
光と色の話 第一部

第38回 色彩の心理 (その1)
・・・・・ 暗順応、明順応、色順応 ・・・・・
「光と色」は私たち人間の活動にとって極めて重要で、切っても切れない存在であることがこれまでの連載でもある程度お分かり頂けると思います。これまでは、「光と色」について主に物理的な側面からお話を進めてきましたが、今回から心理的、生理的な側面にもスポットを当ててみたいと思います。
色の心理的効果の伝達過程
人間の色の感じ方の大きな流れについては、本連載第 14 回で「色感覚」と「色知覚」という効果を中心にお話しましたが、その部分の註釈≪※1≫色情報の心理的効果の伝達過程において、更に「色感情効果」への発展にも少し触れました。
視覚機能の入り口の部分での心理物理的効果である「色感覚効果」が大脳へ伝達されて処理される過程で、興味深い色の見え方が生じてきます。私たちは日常、様々な色の組み合わせの中で生活していますので、異なる色刺激が空間的に隣接して同時に、あるいはまた時間的に相前後して肉眼へ入射してきています。
これら色刺激を網膜上の視細胞で受けて脳で色を認識することになるのですが、その色刺激情報の伝達・認識過程で、色刺激の入射の仕方に応じて視細胞の感度が生理的に変化したり、脳内での認識の仕方が影響を受けたりすることによって、色を単独で見る場合と比べてかなり異なった様相で色が認識されることが起こります。このような段階の色の認識を「色知覚効果」と称しています。

色知覚効果の内、私たちが日常無意識の内に体験しているお馴染みの現象に、各種「順応現象(暗順応、明順応、色順応)」や、複数種の色の差異が強調される「色対比現象」、複数の色が混じり合ってその中間の色になったように見える「色同化現象」等があります。今回は、その内、「順応現象」についてお話します。
暗順応 と 明順応
例えば映画館へ行った時、明るい部屋(明所視状態)から暗い映写室(暗所視状態)に入った直後は、室内のスクリーン以外の周辺や足元は真っ暗で殆ど何も見えません。しかし数分経つ内に、徐々に目が慣れてきて、通路の位置や座席の空き状態も分かってきます。このように、周囲の視環境が明所から暗所に急変した場合、その直後は暗いところがよく見えないのですが、暫くする内に徐々に眼の感度が高まってきて見えるようになってくることを、暗順応( dark adaptation )と言っています。
逆に、映写室(暗所視状態)から外の明るい部屋(明所視状態)へ出ると、その瞬間は眩しくて周囲が見えなくなりますが、じきに正常に見えるようになります。これを明順応( light adaptation )と言っています。
明るさの変化に対して人間の眼は、その感受性(感度)を生理的に調整して、その明るさに「順応」する能力を持っているのですが、明るさの変化する方向によって人間の眼の順応の仕方(応答の速さ)は異っています。
本連載の第 11 回および第 14 回でも触れましたように、人間の視細胞には錐体と杆体があり、明所視では錐体が、暗所視では杆体が機能するように生理的に役割分担しています。
一方、明→暗の変化に対する視細胞の時間応答特性(順応特性)は、錐体が短時間で応答するのに対して、杆体は “ slow response ” で、順応するのに数分から数十分を要します。
これを換言すると、錐体は(明るい所での)明暗の変化には素早く応答するのですが、暗くなると感度不足で見えなくなってしまい、一方、杆体は感度が高くて錐体より暗いところまで見えるのですが、高感度でフル稼働するまでに時間がかかってしまう、ということです。
このような視細胞の感度および時間応答特性が上記の映画館の場合の暗順応、明順応にどのように関与しているのでしょうか。
錐体が機能し、杆体は機能していない映写室外(明所)から、急に映写室内(暗所)に移ると、錐体は暗さに対応しようと生理的に感度を精一杯向上させるのですが、すぐ感度能力の限界に達してしまい、それ以下の暗さでは検知することができません。この時点で、杆体はまだ立ち上がり前で光を検知する準備が整っていないため、結局“眼”としては“真っ暗”にしか見えません。

しかし時間の経過とともに杆体が徐々に稼働し始め、ジワーッと錐体の感度レベルを越えて機能し始めるため、うっすらと暗闇が見え始め、さらに杆体の感度が上がるに従って、暗闇の中の様子(通路の様子や座席の空き状態)が分かってくるようになります。数十分経つと杆体の感度レベルも周囲の暗さに完全に順応した安定状態になります。
この状態(暗所に順応した状態)から映写室外(明所)に移動すると、そこは光が充満していますので、それまで高感度状態で機能してきた杆体に明所の多量の光が入射し、杆体の検知出力は一気に飽和してしまいます。これが、「眩しい」という感覚であって、何も見えない(杆体が機能しない)状態になります。しかし、これは一瞬で、明所で応答速度の速い錐体がすぐに明るさの変化に順応して、杆体に代わって機能するようになって正常に見えるようになる訳です。
このような人間の眼の暗順応・明順応に対応した例として、トンネル内の照明があります。
長いトンネル内では照明灯の設置間隔は均等ではなく、入口、出口に近い程、設置間隔が短く、トンネル中央部に行くほど間隔が長くなっていることに気がついた人も多いと思います。これはトンネルでの事故防止のための対応です。

昼間の明るいトンネル外からトンネルに入ると、(照明が不足すると)急に暗くなったと感じ、運転者の眼が慣れる(暗順応する)までは、視界が暗くて見通しが効かず、下手をすると事故に繋がりかねません。そこで、トンネルの入口近くでは、照明の設置間隔を短くして、できるだけ明るさを確保することによって、トンネル外との明るさのギャップを少なくして、視界が見えないという状態に陥らないようにしています。トンネルの奥へ進むに従って(時間が経過して)、暗順応が進んで暗くてもそこそこ見えるようになってきますので、照明の設置間隔は入口ほど密にする必要がなくなります。
暗いトンネルから明るい外へ出る時は、明順応が起こりますが、一瞬でも眩しくて視界が見えないとやはり危険ですので、明るさの変化をできるだけ少なくするためにトンネル内の出口近くは照明の設置間隔を密にしてあります。トンネル内は双方向通行が多いので、結果的に照明設置間隔はトンネル中央を中心にして対称ということになります。≪※1≫
色順応
眼の順応現象は視環境の「明るさ」だけではなく、「色」に対しても起こります。
例えば今、昼白色蛍光灯( ex. 相関色温度 5000 K )の下で白い紙を見ているとします。この状態で蛍光灯を消して、瞬時に白熱灯( ex. 色温度 2800 K )に切り替えたとします。昼白色蛍光灯と白熱灯の分光分布はそれぞれ下図のような特性で、白熱灯の方が長波長成分(赤味成分)がかなり多いため、切り替え直後は、紙の色が少し赤味を帯びたように見えます。しかし、じきにそのような感覚は無くなり、元の蛍光灯の下で見ていたのと同じような白に見えるようになります。
このような現象が色順応( color adaptation )です。

本連載第 12 回で説明しましたように、物体の色は「光源」、「物体」、「視覚」で決まります(物体色の 3 要素)が、光源と物体の 2 つの要素は物理的特性のみで決まるのに対して、視覚の要素は人間の眼と脳の生理的・心理的要素が関係してきます。
人間の感覚器官の感度は、(その本人は意識しない中で)外界からの物理的刺激変化を緩和しようとする生理的応答特性を持っています。≪※2≫
昼白色蛍光灯下で「白」と認識しているということは、視細胞の S 、 M 、 L 錐体の受ける刺激応答量がほぼ均等で、その結果、脳が「白」と判断していることになります。
この状態で蛍光灯から白熱灯に切り替えると、光源の分光分布の違いのため、長波長光が支配的になり、(照度変化が僅少であれば) L 錐体への刺激が急増、 S 錐体への刺激が急減するため、切り替え直後は赤味を帯びた色として認識されます。この刺激急変を緩和するように、 L 錐体の感度が鈍化し、 S 錐体の感度が鋭敏化する生理的反応(順応)が起こります。
その結果、蛍光灯下での S 、 M 、 L 錐体の刺激応答量比と同じ程度となり、脳は蛍光灯下での場合と同じような「白」と認識するに至る訳です。

色順応 と カメラのホワイトバランス機能
人間の眼にはこのような生理的な色順応が起こりますが、「機械の眼」ではどうでしょう。
最近のカメラは殆どがデジタルカメラになっていますが、このデジタルカメラには「ホワイトバランス」という機能が備わっていますね。このホワイトバランス機能をオートモードで使う場合が人間の眼の「色順応」に対応していると言えます。
写真撮影時の被写体照明光には様々な光源があり得ますが、光源の種類毎にその色味(色温度)も様々です。従って照明光源が異なれば、同一の被写体であっても、被写体からカメラへの反射光の分光分布は光源の種類に直接依存して変化します。
カメラの撮像素子は、可視域を3つの波長帯に分けた3種の画素群( B 、 G 、 R )から成っていますが、これら B 、G 、R 画素の感度が固定であれば、照明光源の色味(分光分布)の違いが撮像結果にストレートに影響を及ぼしてしまいます。
下の作例写真①、②、③をご覧下さい。
これらはカメラのホワイトバランスをマニュアルモードで 5000 K に設定( B 、G 、R の撮像素子を所定感度に固定)して、異種の色味(色温度)の光源・・・・・写真① は 2700 K の(赤っぽい)照明光、
写真②は、5000 K の(白っぽい)照明光、写真③は 8500 K(青白っぽい)照明光・・・・・で撮影したものです。撮影結果に照明光の色味(色温度)が大きく影響しているのがよく分かります。≪※3≫

ところが、この撮影現場にいる人間が見る色は、写真①や③のようには見えず、どの照明光でも写真②のように、ほぼ同じような自然な色調に見えています。
これは、照明光の色味の差異を抑えるように人間の眼では色順応が働いているからです≪※4≫
マニュアルでホワイトバランスを設定する場合、色温度値で指定しますが、これは、設定した色温度の照明光で撮影すると、画面全体の色バランスがとれた状態で、すなわち「白い紙が白く写る」ことを意味しています。写真②では照明光の色温度がホワイトバランス設定値( 5000 K )に一致しているため、色順応した肉眼で見たのと同様な自然な色調に仕上がっているということになります。
それに対して、写真①では、設定した色温度値( 5000 K )より低い色温度( 2700 K )の照明光ですので、撮像素子の
B 、G 、R 画素の設定感度に対して照明光の青成分が弱く、赤成分が強いため、撮影結果は(白い紙が)赤味を帯びて写ります。逆に、写真③では設定した色温度値(5000 K )より高い色温度( 8500 K )の照明光ですので、 B 、G 、R 画素の設定感度に対して照明光の青成分が強く、赤成分が弱いため、撮影結果は(白い紙が)青味を帯びて写ります。
ホワイトバランスをオートモードで使用すると、どんな色味の(白色)光源であっても、撮影画面内での撮像素子の B 、G 、R 感光量バランスが概ね均等になるように・・・・・つまり、「白い紙が白く写る」ように・・・・・カメラが B 、G 、R 撮像素子の感度比を自動的に調整しますので、一般的な撮影条件の場合には、照明光源の色味(色温度)をあまり気にせずに、ほぼ失敗なくそこそこのカラー写真が撮影できる訳です。つまり、ホワイトバランスをオートモードで使用する場合が、人間の色順応に対応するということになります。ホワイトバランス機能は、オートとマニュアルを使い分けるようになっています。
一般的にはオートで使われることが多いのですが、照明光の強い色味によってその場の雰囲気が特徴付けられている場合≪※5≫や、意図的に撮影画面全体の色調を演出するような場合等にはホワイトバランスをマニュアルで設定して撮影することになります。≪※6≫
注釈
≪※1≫ トンネルの照明設置間隔
暗順応、明順応対策という観点から考えると、トンネル中央部も出入口と同じ照明設置間隔にしても良いのではないかと思われますが、トンネル内は昼夜通しての点灯になりますので電気代の節約という観点から、安全を確保できる範囲で中央部の設置間隔は広めになっています。
≪※2≫ 人間の感覚器官の順応
明暗や色に対する順応現象は、人間の生物としての環境変化への適応能力の一つとして考えることができるでしょう。外界から生体への物理的刺激は時々刻々変化するものであり、生体の感じる感覚がその変化に忠実に応答するとすれば、間断なく感覚の変化に晒され続けることになり、心が落ち着く暇もないことになってしまいます。このようなストレスを緩和するように、無意識のうちに生理的に感覚器官の感度が調節されるように働く能力を得た結果が順応現象であると言えます。これは視覚に限らず、聴覚や触覚でも同様で、いわば生存のための生体の自己防衛のメカニズムであるとも言えます。
≪※3≫ 写真撮影の場合の「色温度」 ・・・・・ 「写真的色温度」
本連載の第33回で、「色温度」と「相関色温度」の定義を説明致しました。写真撮影に関しての照明光の色味について、今回便宜的に「色温度」という用語を使用しましたが、写真撮影(機械の眼)の場合には、厳密には「色温度」ではなく「写真的色温度」と表現すべきものです。
第33回で説明しました「色温度」も「相関色温度」も共にその色味は「人間の眼」すなわち視細胞
S 、 M 、 L 錐体(+脳)による評価によるものです。カメラの撮像素子( B 、 G 、 R )の分光感度特性は錐体( S 、 M 、 L )と一致している訳ではありませんので、「色温度」、「相関色温度」の定義を写真撮影にそのまま適用することはできません。 そこで、写真撮影時の照明光をカメラの撮像素子で測定した時の B 、R 感光量比に対して、それと同等の B 、R 感光量比を与える黒体の色温度値を借用して表現したものが「写真的色温度」です。
≪※4≫ 順応 と 恒常性
私たちが物体の色を認識する場合、ただ単に物体からの反射(透過)光の強さや分光情報のみで明るさや色を認識している訳ではなく、その物体が何であるか(例えば、紙なのか石なのか、紙の場合でも白い紙なのか赤い紙なのか・・・)、形状や表面状態はどうか、等々も同時に認識しています。
そのような多次元に亘る情報を脳内に蓄積された記憶情報等と無意識の中で参照した結果として物体の色を認識しています。その結果、照明条件、観察条件によってその色刺激が変化しても、その見え方(明るさや色)の変化を抑えるような順応効果・・・心理的生理的応答効果が働きます。
これが恒常性(明るさの恒常性、色恒常性)と呼ばれるもので順応(暗順応、明順応、色順応)と深く関係しています。物体の色に比較して光源の色の場合には、このような恒常性は起こりにくいと言われています。
≪※5≫ オートホワイトバランスによる撮影失敗
無分別にオートホワイトバランスを使うと、大失敗することがありますので注意が必要です。オートホワイトバランスがうまく機能するのは、撮影画面全体の色の分布にあまり偏りが無い場合であり、画面全体が青っぽいとか赤っぽいという場合には、その色調を打ち消すように働いてしまいます。
例えば、夕焼けで真っ赤に染まったシーンを、オートホワイトバランスのまま撮影すると、全く夕焼けのシーンらしくない(昼間に撮影したような赤味の無い)写真に仕上がってしまい、「小さな親切、大きなお世話」 ということになってしまいます。
≪※6≫ カラーフィルム写真(銀塩写真)の場合
最近は使われることが珍しくなってきましたが、カラーフィルム(銀塩フィルム)での撮影では、フィルムには色順応特性がありませんので、光源の分光分布の違いがそのまま撮影された物体の色の変化となって表れます。従って、カラーフィルム写真では、使用する照明光の種類(色温度)によって、フィルムタイプ(デイライトタイプ、タングステンタイプ)を選択する必要があります。
つまり、カラーフィルムは、デジタルカメラにおけるホワイトバランスをマニュアル設定した場合に相当します。デジタルカメラのホワイトバランスをマニュアルで 5500 K に設定すればデイライトタイプのカラーフィルムに相当し、ホワイトバランスを 3200 K に設定すれば、タングステンタイプのカラーフィルムに相当します。実際の場合の照明光の色味(色温度)は様々ですので、選択したカラーフィルムの色温度タイプがピッタリ一致するとは限らず、色温度差に応じて撮影結果の色調に影響が現れてしまいます。撮影意図に対してそれが問題になる場合は、各種濃度の色温度変換フィルタ( LB フィルタ)を用いて色補正を行うことも行われます。使用するフィルムに対して照明光の色温度が高い場合は、色温度を下げる(相対的に短波長成分を削る)色温度変換フィルタを、照明光の色温度が低い場合は、色温度を上げる(相対的に長波長成分を削る)色温度変換フィルタを使用します。
また、色温度変換フィルタとは別に色補正フィルタ( CC フィルタ)というものも準備されています。
例えば、或る種の蛍光ランプなどの場合には、可視域中央部(緑成分)が相対的に強いものもあります。肉眼では色順応によって不自然さは感じないのですが、フィルムで撮影すると緑味を帯びた色調になることがあります。このような場合は、可視域中央部の透過率が相対的に低いマゼンタ色の色補正フィルタ( CC フィルタ)によって色補正を行います。
カラーフィルムには、ネガカラーフィルムとリバーサルカラーフィルムがあります。
ネガカラーフィルムの場合には現像したフィルム(陰画)から焼き付けによって最終写真(陽画)に仕上げる段階である程度色補正が可能ですので、撮影時に多少の照明光の色温度ズレがあっても事後に或る程度の色補正処理は可能です。しかし、リバーサルカラーフィルムの場合には、現像即最終画像(陽画)となりますから、事後の色補正ができず、撮影時の条件設定はより厳しくなります。