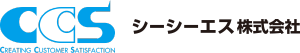光と色の話 第一部

第31回 三原色で表せる色
・・・・・ 青色 LED と 白色照明 ・・・・・
2014 年 10 月 7 日、ビッグニュースが飛び込んできました。2014 年ノーベル物理学賞に赤崎勇名城大学終身教授、天野浩名古屋大学大学院教授、中村修二カリフォルニア大学教授の3名の方の受賞が決まったとの報です。青色発光ダイオード( LED )の開発・実用化に対する大きな貢献が認められ、日本の科学技術の高さが改めて脚光を浴びたことで日本中が沸き返りました。赤色や黄緑色の LED は既に 1960 年代に存在していましたが、青色の LED については技術的障壁が高く、20 世紀中には実用化困難と見られていたのを覆し、材料開発から量産化技術までに道筋をつけ、今日の LED 新時代を実現させたことが高く評価されたということです。
可視域短波長側の青の LED が実現したことによって、19 世紀末からの白熱ランプやその後の蛍光ランプなどに代わるエネルギー効率の高い長寿命の LED 白色光源が実現し、大幅な省エネルギーにより地球環境保全にも大きく貢献することになると期待されています。
この吉報を伝えるマスコミの報道で、少し気になった表現がありました。「青色を実現したことによって、それまでに存在した赤、緑と合わせて3 原色が揃った」ことの意味を説明する段で、殆どのマスコミが 『赤、緑、青の三原色で“全ての色”が作り出せる』・・・という言い方をしていました。しかし、この表現は厳密に言うと正しくありません。三原色を混色してもどうしても作り出せない色が存在します。
三原色の光で作り出せる色の範囲(色再現域)
赤[ R ]、緑[ G ]、青[ B ]の三原色の光の加法混色で作り出せる色の範囲(色再現域)は、x y 色度図上で三原色の色度座標点 R 、G 、B を直線で結んだ △RGB の内側(および辺上)のみで、△RGB の外側の色は鮮やかすぎて作り出すことができません。これは、本連載の前回(第 30 回)の等色実験の説明の中で詳しく説明した通りです。
x y 色度図の外周の曲線(単色光軌跡 or スペクトル軌跡)は外側に膨らんだ形状をしていますので、如何なる三原色 [ R ]、[ G ]、[ B ] の組み合わせを選択しても、必ず △RGB には含まれない領域が残ってしまいます。≪※1≫

従って、上述のマスコミの報道は、厳密には 『赤、緑、青の 3 原色で“殆ど全ての色”が作り出せる』 と表現すべきものです。例えば、本連載の第 19 回で説明しましたように、虹の色は水滴によって屈折・分散された単色光の色ですので、その色度点は単色光軌跡(スペクトル軌跡)上に存在し、三原色による三角形の外側になります。テレビ画面上の虹や、書物に印刷された虹の色は、虹の色を完全に再現しているという訳ではなく、厳密に言えば“虹に近い色”を不自然でないように見せている、ということですね。この連載で使用している色度図についても、周辺部(単色光軌跡および純紫軌跡)近傍の色は実際の色を再現できているわけではありません。
x y 色度図では 3 色の加法混色結果(色再現域)が三角形で表される理由
では、なぜ三原色 [ R ]、[ G ]、[ B ] の加法混色結果の色が x y 色度図の △RGB の内側だけに限定されるのでしょうか?これには数学的な説明が必要になります。 x y 色度図というのは、数学的には、線形空間であるという基本的性質がありますが、この「線形」であるということが、2 色の混色結果の色度点がそれらの色度点を結ぶ直線上に来る、ということの直接の理由なのです。
3 種の色 [ R ]、[ G ]、[ B ] の混色は、例えば最初に [ R ] と [ G ] の 2 色を混色させた結果の色に、更に
[ B ] を混色させるという2段階に分けて考えられます。結局、3 種の色の混色結果の色度点は、必ず 3 種の色の色度点で形成される三角形 ( △RGB ) の内部に存在することになります。
「線形性」とは
数学的に「線形」である、というのは、数学的変換関係が一次式で表されるということを言います。変換が一次式で表現できる最も簡単な場合、例えば y = A x( A :定数) は、x と y は正比例の関係にあり、x y 平面でのグラフは原点を通る傾き A の直線になります。このように変数 ( x ) の変化量 △x に対する関数値 ( y ) の変化量 △y の比 ( △y / △x = A ) が一定で、グラフ上では直線に表示される性質を「線形」と言います。
この y = A ・x に対して、例えば y' = B ・y+ C = AB ・ x + C ( B , C :定数) という演算処理を施した場合、これは(横軸は x のままで)縦軸が y' の座標となり、その座標において、傾きが AB で y' 切片が C の直線を表します。
つまり、この演算によって x y 座標から x y' 座標に座標変換されたことになるのですが、グラフが直線であるという性質はそのまま受け継がれています。

これに対して、例えば、y'' = x ・ y = x ・( A ・ x ) = A ・x2 という変換の場合はどうでしょう。
xy'' 座標では 二次曲線(放物線)を描くことになり、元の x y 座標の直線という特徴は保存されないことになります。
以上を一般化していえば、一次式(変数のべき乗が 1 である式)によって変換されたものは、直線が直線として変換されるということになります。このような変換を線形変換と言っています。変換式が非一次式である場合には、直線が曲線に変換されてしまう(線形性が保存されない)非線形変換ということになります。
加法混色 と 色度図の「線形性」との関係
以上の線形性が、混色に対してどのように関与しているかを以下に説明します。
XYZ 表色系の元の原理表色系である RGB 表色系における三刺激値 ( R 、G 、B ) は、その定義式≪※2≫からわかりますように、目に入射する光が視覚に与える刺激の強さ(心理物理量)を表しており、R 、G 、B それぞれが目に入射する“光の強さ”に比例しています。
RGB 表色系において、三刺激値が R 、G 、B である色 [ F ]を考えます。これを 3 つの刺激値 R 、G 、B を 3 軸とする直交座標空間で考えると、この色 [ F ]は、 F( R , G , B )というベクトルとして解釈することができます。
一方、RGB 表色系での色度座標 ( r , g , b ) は、刺激値総量に対する各刺激値の比
 ,
, ,
,
で定義され、r + g + b = 1ですから、ベクトル F( R , G , B )が 平面 R + G + B = 1 と交わる点が、色度座標 ( r , g , b )であると解釈することができます。この色度座標ベクトルを f ( r , g , b ) と書くことにします。
今、二つの色 [ F1 ] と [ F2 ] を混色した結果が [ FM ] となった場合を考えます。
F1 ( R1 , G1 , B1 ) 、F2 ( R2 ,G2 ,B2 ) を混色した結果を FM ( RM ,GM ,BM ) とすると、各刺激値は RM = R1+R2 、GM = G1+G2 、BM = B1+B2 となりますから、
F1 ( R1 , G1 , B1 ) + F2 ( R2 ,G2 ,B2 )= FM ( R1 + R2 , G1 + G2 , B1 + B2 )
というベクトル演算式で表すことができます。この和ベクトル FM は、2 本のベクトル F1 と F2 で決まる平面内に存在し、ベクトル F1 と F2 を隣り合う 2 辺とする平行四辺形の対角線となっています。従って、各ベクトル F1 、F2 、FM を含む平面(平行四辺形)と、 R + G + B = 1 の平面の交わりは平面同士の交わりで直線となります。ベクトル F1 、F2 、FM と 平面
R + G + B = 1 の交点を示す色度座標ベクトル f1 ( r1 ,g1 ,b1 )、 f2 ( r2 ,g2 ,b2 )、 fM ( rM ,gM ,bM ) も、この直線上に存在することになります。
これは、2 色 [ F1 ] と [ F2 ] の混色結果 [ FM ] の色度点 fM ( rM ,gM ,bM ) が rg b 色度図上で 2 色の色度点 f1 ( r1 , g1 , b1 )、 f2 ( r2 , g2 , b2 ) を結んだ直線上にあることを意味しています。
また、混色結果の色度点 fM ( rM , gM , bM ) は、 F1 (
R1 , G1 , B1 ) と F2 ( R2 ,G2 ,B2 ) のベクトルの大きさ(すなわち刺激値の大きさ)の比で内分された位置に来ます≪※3≫。
rg b 色度図を r g 平面に投影した図である r g 色度図においても、この直線関係(線形性)は保存されます。

RGB 表色系の三刺激値 R 、G 、B に対して下記の座標変換を行った結果得られるのが XYZ 表色系の三刺激値 X 、Y 、Z です。

この座標変換は一次変換式ですから、「線形性」は保存され、RGB 表色系の r g 色度図上での直線は x y 色度図上でも直線で表されることになります。≪※4≫
LED による白色光源
赤、黄緑色は 1960 年代に、黄色は 1970 年代に実現されましたが、可視域の短波長側に位置する青が無いために、 LED による白色光を作り出すことはできませんでした。従って、青色 LED の実現以前は、 LED は照明用と言うよりは、彩度の高い赤、黄、黄緑などの有彩色の「表示用」として主に利用されてきました。青色 LED の実現によって LED による「白色」光源が可能になったことが、( LED の低消費電力をはじめ各種の特徴も相俟って) 一般照明分野に広く実用化されるに至ったことの最大要因であった訳です。
LED による白色光源の実現方法としては、本連載第 17 回 『混色(その2)・・・同時加法混色、減法混色の応用例・・・』 で紹介させていただいております。 大きく分けて、
①マルチチップ LED 方式(三原色 BGR 方式や補色方式)、
②シングルチップ LED 方式 (蛍光励起方式)
の方式がありますが、“一般照明用”の白色 LED としては、マルチチップ方式は殆ど使用されず、殆どがシングルチップによる蛍光励起方式によっています。これは、単色 LED 自体の発光分光分布の半値幅が狭いため、マルチチップ LED 方式では、白色光源として分光分布の凹凸が大きく、物体の色の見え方が良くない(演色性≪※5≫が良くない)ことやコスト面で不利であることなどの要因があるためです。


シングルチップ LED 方式 (蛍光励起方式)でも、従来主流であったBlue-YAGタイプ(補色蛍光方式: B + Y ⇒ W ) は、エネルギー効率面やコスト面でのメリットは大きいのですが、やはり分光分布特性の凹凸が激しく演色性が良くないこと、また、相関色温度≪※6≫も高くなりがちという欠点がありました。

近年の白色 LED は、紫外や青(もしくは紫)の LED を励起光源として、複数種の蛍光体の組み合わせを最適化することによって、可視域全般に凹凸の少ない連続スペクトルを実現し、演色性の高い白色光源を実現するようになってきています。≪※7≫

これによって、従来型光源(白熱ランプや蛍光ランプ)に代わる良質な白色光源としての資質が備わり、更に小型で低消費電力、高速応答性などの特徴を活かして、様々な用途に急速に普及し始めている訳です。
冒頭で触れましたマスコミの表現・・・『青色を実現したことによって、それまでに存在した赤、緑と合わせて三原色が揃った』という表現も、「白色光源」という視点からは、エネルギーの大きい可視域“短波長側”の LED を実現し、蛍光体技術との組み合わせで、(赤や緑の LED を併用するよりも)より良質な白色光源ができるようになった、ということに大きな意味があったと言うことができます。
この青色 LED の技術は更に進化して、現在では可視域よりも更に波長の短い(エネルギーの大きい)紫外 LED も実現されています。
注釈
≪※1≫
LED の分光分布は純粋の単色光ではなく、一般に半値幅が数十 nm 以下の狭い帯域幅の光源ですので、x y 色度図においては、外周の曲線(単色光軌跡)より少し内側に位置します。
3 原色をすべて(スペクトル軌跡上にある)単色光とした場合(例えば、RGB 表色系における等色実験の場合)でも、△RGB の領域(色再現域)は大きくなりますが、三角形の外側の領域は必ず残ります。

≪※2≫ RGB 表色系における 3 刺激値の定義

P ( λ ) :照明光の分光分布
ρ ( λ ) :物体の分光反射率
(光源色の場合は ρ ( λ ) = 1 とする。)
r ( λ ) , g ( λ ) , b ( λ ):RGB 表色系の等色関数
k : 定数
≪※3≫ x y 色度図における混色比
今、2 種の光色 [ G ] と [ R ] を考え、それらの色度座標をそれぞれ、 G ( xG , yG ) 、 R ( xR , yR )とします。 この 2 色を m : n の比で混色した場合の色[ F ]の色度座標を F ( xF , yF ) としますと、

となります。これは、色度図上で、混色結果の色度点 F ( xF , yF ) は、直線 GR を m : n で内分した点になるということを示しています。
x y 色度図が、線形空間であることによって、混色結果の色度点が 2 色の色度点を結ぶ直線上に来る、ということに加えて、その混色比に比例した内分点になる、ということになりますので、混色を扱う場合には XYZ 表色系( x y 色度図)は非常に相性が良いということが言えます。

≪※4≫ 均等色空間への非線形変換
次回(第 32 回)に説明を予定していますCIE L*u*v* 表色系や、CIE L*a*b* 表色系は、「非均等色差空間」である XYZ 表色系から( 1 / 3 乗の演算を含む)非一次式によって「均等色差空間」へ座標変換していますので、その代償として線形性は廃棄されています。従って、これらの「均等色差空間」では、混色結果が色度図上で直線にはなりません。
≪※5≫ 演色性
物体の色の見え方は、それを照明する光の特性によって変化します。照明による物体の色の見え方を演色といい、その演色の効果を決める照明光源の特性を演色性と言います。
≪※6≫ 色温度、相関色温度
一言で「白色光」と言っても、その分光分布は様々で、ロウソクや白熱ランプのように赤味を帯びて見えるものから、日中の太陽光のように、青白く見えるものまで色々あります。これらの白色光の色味を表すものとして、色温度および相関色温度という指数があります。色温度、相関色温度については次々回に採り上げたいと考えています。
≪※7≫ 蛍光発生と白色 LED
本連載の第 2 回の註釈≪※2≫と≪※3≫で、光の発生メカニズムとエネルギーの関係を簡単に説明致しました。大雑把に言えば、物質へ入射する光とその物質の電子との相互作用により、光のエネルギー △E が物質の電子エネルギーに受け渡される現象が物質による「光の吸収」であり、また、物質内電子のエネルギー状態の遷移(励起状態 EH から基底状態 EL への遷移)により、電子の持つエネルギー△E が原子外へ電磁波の形で放出されるエネルギーが「光(発光)」でした。
この電磁波(光)のエネルギーは電子のエネルギー準位の差となっており、光の振動数 ν に比例(波長に反比例)しています。
△E = EH - EL = hν = h ・ c / λ
( h はプランク定数で、h ≒ 6.63 × 10-34 Js )
通常の場合、「光の吸収」( EL → EH ) も、「光の放出」( EH → EL ) も授受されるエネルギー量はいずれも △E で等しいため、吸収される光と放出される光の波長は変わりません。

これに対して、蛍光の発生はそれよりもう少し複雑で、蛍光物質においては複数以上の励起状態の準位が関係してきます。ここでは説明を簡単にするためにこれらの励起準位を EH と E'H します。
( EH > E'H )
基底状態にあった電子が光(励起光)のエネルギー △E を吸収して、先ず高エネルギー準位の EH に励起されます。非蛍光プロセスでの発光では EH から直接元の規定状態 EL へ戻るのですが、蛍光プロセスにおいては、EH から一旦別の励起エネルギー準位の E'H ( E'H < EH ) に移ります。このエネルギー差 ( EH - E'H ) は光として放出されるのではなく、熱(振動)エネルギー等として発散されます。次いで励起電子が準位 E'H から基底状態 EL へ遷移する際に △E' ( = E'H - EL ) だけのエネルギーを電磁波として外部へ放出するのですが、これが「蛍光」です。
励起光吸収時のエネルギー △E よりも蛍光発光エネルギー △E' の方が小さいので、蛍光の波長は必ず励起光の波長よりも長くなります。
通常の熱放射型光源(白熱ランプなど)や放電型ランプ(水銀ランプなど)は、ランプに通電することによって高レベルのエネルギー準位に電気的に励起された電子が低エネルギー準位に遷移する過程でエネルギー差を電磁波(光)の形で原子の外へ放出するものです。 これに対して蛍光ランプは、蛍光物質に照射される電磁波(紫外放射)のエネルギーを(長波長側に)波長変換して可視光として再放出するものです。
上記の蛍光発生原理の説明は、話を単純にするために励起状態の準位の数を 2 つだけで説明しましたが、実際の蛍光物質においては、励起準位が多数存在し、励起された電子が多数の励起準位から基底準位へ遷移します。従って、放出される蛍光の波長は単一波長ではなく、数十 nm 以上の広い波長範囲幅を持っているのが一般的です。つまり蛍光の帯域幅は、(赤や緑などの)単色 LED の帯域幅よりも広くできますので、マルチチップ LED 方式よりも蛍光励起方式の方が白色光源としてより望ましい特性を達成し易いということができます。特に蛍光体を複数種併用して異なる波長の蛍光を同時発生させる「三原色蛍光方式」は連続スペクトルの良質な白色光を達成する主流技術であると言えます。
青は、赤や緑よりも波長が短いため、青色 LED を実現するためには、バンドギャップ △E がより大きい LED に適した半導体材料が必要です。この半導体材料の開発の障壁が非常に高かったため、青色 LED の 20 世紀中の実現が絶望視されていたのですが、その障壁を突き破ったのが今回のノーベル賞受賞者の方々です。
光と色の話 第一部

第31回 三原色で表せる色
・・・・・ 青色 LED と 白色照明 ・・・・・
2014 年 10 月 7 日、ビッグニュースが飛び込んできました。2014 年ノーベル物理学賞に赤崎勇名城大学終身教授、天野浩名古屋大学大学院教授、中村修二カリフォルニア大学教授の3名の方の受賞が決まったとの報です。青色発光ダイオード( LED )の開発・実用化に対する大きな貢献が認められ、日本の科学技術の高さが改めて脚光を浴びたことで日本中が沸き返りました。赤色や黄緑色の LED は既に 1960 年代に存在していましたが、青色の LED については技術的障壁が高く、20 世紀中には実用化困難と見られていたのを覆し、材料開発から量産化技術までに道筋をつけ、今日の LED 新時代を実現させたことが高く評価されたということです。
可視域短波長側の青の LED が実現したことによって、19 世紀末からの白熱ランプやその後の蛍光ランプなどに代わるエネルギー効率の高い長寿命の LED 白色光源が実現し、大幅な省エネルギーにより地球環境保全にも大きく貢献することになると期待されています。
この吉報を伝えるマスコミの報道で、少し気になった表現がありました。「青色を実現したことによって、それまでに存在した赤、緑と合わせて3 原色が揃った」ことの意味を説明する段で、殆どのマスコミが 『赤、緑、青の三原色で“全ての色”が作り出せる』・・・という言い方をしていました。しかし、この表現は厳密に言うと正しくありません。三原色を混色してもどうしても作り出せない色が存在します。
三原色の光で作り出せる色の範囲(色再現域)
赤[ R ]、緑[ G ]、青[ B ]の三原色の光の加法混色で作り出せる色の範囲(色再現域)は、x y 色度図上で三原色の色度座標点 R 、G 、B を直線で結んだ △RGB の内側(および辺上)のみで、△RGB の外側の色は鮮やかすぎて作り出すことができません。これは、本連載の前回(第 30 回)の等色実験の説明の中で詳しく説明した通りです。
x y 色度図の外周の曲線(単色光軌跡 or スペクトル軌跡)は外側に膨らんだ形状をしていますので、如何なる三原色 [ R ]、[ G ]、[ B ] の組み合わせを選択しても、必ず △RGB には含まれない領域が残ってしまいます。≪※1≫

従って、上述のマスコミの報道は、厳密には 『赤、緑、青の 3 原色で“殆ど全ての色”が作り出せる』 と表現すべきものです。例えば、本連載の第 19 回で説明しましたように、虹の色は水滴によって屈折・分散された単色光の色ですので、その色度点は単色光軌跡(スペクトル軌跡)上に存在し、三原色による三角形の外側になります。テレビ画面上の虹や、書物に印刷された虹の色は、虹の色を完全に再現しているという訳ではなく、厳密に言えば“虹に近い色”を不自然でないように見せている、ということですね。この連載で使用している色度図についても、周辺部(単色光軌跡および純紫軌跡)近傍の色は実際の色を再現できているわけではありません。
x y 色度図では 3 色の加法混色結果(色再現域)が三角形で表される理由
では、なぜ三原色 [ R ]、[ G ]、[ B ] の加法混色結果の色が x y 色度図の △RGB の内側だけに限定されるのでしょうか?これには数学的な説明が必要になります。 x y 色度図というのは、数学的には、線形空間であるという基本的性質がありますが、この「線形」であるということが、2 色の混色結果の色度点がそれらの色度点を結ぶ直線上に来る、ということの直接の理由なのです。
3 種の色 [ R ]、[ G ]、[ B ] の混色は、例えば最初に [ R ] と [ G ] の 2 色を混色させた結果の色に、更に
[ B ] を混色させるという2段階に分けて考えられます。結局、3 種の色の混色結果の色度点は、必ず 3 種の色の色度点で形成される三角形 ( △RGB ) の内部に存在することになります。
「線形性」とは
数学的に「線形」である、というのは、数学的変換関係が一次式で表されるということを言います。変換が一次式で表現できる最も簡単な場合、例えば y = A x( A :定数) は、x と y は正比例の関係にあり、x y 平面でのグラフは原点を通る傾き A の直線になります。このように変数 ( x ) の変化量 △x に対する関数値 ( y ) の変化量 △y の比 ( △y / △x = A ) が一定で、グラフ上では直線に表示される性質を「線形」と言います。
この y = A ・x に対して、例えば y' = B ・y+ C = AB ・ x + C ( B , C :定数) という演算処理を施した場合、これは(横軸は x のままで)縦軸が y' の座標となり、その座標において、傾きが AB で y' 切片が C の直線を表します。
つまり、この演算によって x y 座標から x y' 座標に座標変換されたことになるのですが、グラフが直線であるという性質はそのまま受け継がれています。

これに対して、例えば、y'' = x ・ y = x ・( A ・ x ) = A ・x2 という変換の場合はどうでしょう。
xy'' 座標では 二次曲線(放物線)を描くことになり、元の x y 座標の直線という特徴は保存されないことになります。
以上を一般化していえば、一次式(変数のべき乗が 1 である式)によって変換されたものは、直線が直線として変換されるということになります。このような変換を線形変換と言っています。変換式が非一次式である場合には、直線が曲線に変換されてしまう(線形性が保存されない)非線形変換ということになります。
加法混色 と 色度図の「線形性」との関係
以上の線形性が、混色に対してどのように関与しているかを以下に説明します。
XYZ 表色系の元の原理表色系である RGB 表色系における三刺激値 ( R 、G 、B ) は、その定義式≪※2≫からわかりますように、目に入射する光が視覚に与える刺激の強さ(心理物理量)を表しており、R 、G 、B それぞれが目に入射する“光の強さ”に比例しています。
RGB 表色系において、三刺激値が R 、G 、B である色 [ F ]を考えます。これを 3 つの刺激値 R 、G 、B を 3 軸とする直交座標空間で考えると、この色 [ F ]は、 F( R , G , B )というベクトルとして解釈することができます。
一方、RGB 表色系での色度座標 ( r , g , b ) は、刺激値総量に対する各刺激値の比
 ,
, ,
,
で定義され、r + g + b = 1ですから、ベクトル F( R , G , B )が 平面 R + G + B = 1 と交わる点が、色度座標 ( r , g , b )であると解釈することができます。この色度座標ベクトルを f ( r , g , b ) と書くことにします。
今、二つの色 [ F1 ] と [ F2 ] を混色した結果が [ FM ] となった場合を考えます。
F1 ( R1 , G1 , B1 ) 、F2 ( R2 ,G2 ,B2 ) を混色した結果を FM ( RM ,GM ,BM ) とすると、各刺激値は RM = R1+R2 、GM = G1+G2 、BM = B1+B2 となりますから、
F1 ( R1 , G1 , B1 ) + F2 ( R2 ,G2 ,B2 )= FM ( R1 + R2 , G1 + G2 , B1 + B2 )
というベクトル演算式で表すことができます。この和ベクトル FM は、2 本のベクトル F1 と F2 で決まる平面内に存在し、ベクトル F1 と F2 を隣り合う 2 辺とする平行四辺形の対角線となっています。従って、各ベクトル F1 、F2 、FM を含む平面(平行四辺形)と、 R + G + B = 1 の平面の交わりは平面同士の交わりで直線となります。ベクトル F1 、F2 、FM と 平面
R + G + B = 1 の交点を示す色度座標ベクトル f1 ( r1 ,g1 ,b1 )、 f2 ( r2 ,g2 ,b2 )、 fM ( rM ,gM ,bM ) も、この直線上に存在することになります。
これは、2 色 [ F1 ] と [ F2 ] の混色結果 [ FM ] の色度点 fM ( rM ,gM ,bM ) が rg b 色度図上で 2 色の色度点 f1 ( r1 , g1 , b1 )、 f2 ( r2 , g2 , b2 ) を結んだ直線上にあることを意味しています。
また、混色結果の色度点 fM ( rM , gM , bM ) は、 F1 (
R1 , G1 , B1 ) と F2 ( R2 ,G2 ,B2 ) のベクトルの大きさ(すなわち刺激値の大きさ)の比で内分された位置に来ます≪※3≫。
rg b 色度図を r g 平面に投影した図である r g 色度図においても、この直線関係(線形性)は保存されます。

RGB 表色系の三刺激値 R 、G 、B に対して下記の座標変換を行った結果得られるのが XYZ 表色系の三刺激値 X 、Y 、Z です。

この座標変換は一次変換式ですから、「線形性」は保存され、RGB 表色系の r g 色度図上での直線は x y 色度図上でも直線で表されることになります。≪※4≫
LED による白色光源
赤、黄緑色は 1960 年代に、黄色は 1970 年代に実現されましたが、可視域の短波長側に位置する青が無いために、 LED による白色光を作り出すことはできませんでした。従って、青色 LED の実現以前は、 LED は照明用と言うよりは、彩度の高い赤、黄、黄緑などの有彩色の「表示用」として主に利用されてきました。青色 LED の実現によって LED による「白色」光源が可能になったことが、( LED の低消費電力をはじめ各種の特徴も相俟って) 一般照明分野に広く実用化されるに至ったことの最大要因であった訳です。
LED による白色光源の実現方法としては、本連載第 17 回 『混色(その2)・・・同時加法混色、減法混色の応用例・・・』 で紹介させていただいております。 大きく分けて、
①マルチチップ LED 方式(三原色 BGR 方式や補色方式)、
②シングルチップ LED 方式 (蛍光励起方式)
の方式がありますが、“一般照明用”の白色 LED としては、マルチチップ方式は殆ど使用されず、殆どがシングルチップによる蛍光励起方式によっています。これは、単色 LED 自体の発光分光分布の半値幅が狭いため、マルチチップ LED 方式では、白色光源として分光分布の凹凸が大きく、物体の色の見え方が良くない(演色性≪※5≫が良くない)ことやコスト面で不利であることなどの要因があるためです。


シングルチップ LED 方式 (蛍光励起方式)でも、従来主流であったBlue-YAGタイプ(補色蛍光方式: B + Y ⇒ W ) は、エネルギー効率面やコスト面でのメリットは大きいのですが、やはり分光分布特性の凹凸が激しく演色性が良くないこと、また、相関色温度≪※6≫も高くなりがちという欠点がありました。

近年の白色 LED は、紫外や青(もしくは紫)の LED を励起光源として、複数種の蛍光体の組み合わせを最適化することによって、可視域全般に凹凸の少ない連続スペクトルを実現し、演色性の高い白色光源を実現するようになってきています。≪※7≫

これによって、従来型光源(白熱ランプや蛍光ランプ)に代わる良質な白色光源としての資質が備わり、更に小型で低消費電力、高速応答性などの特徴を活かして、様々な用途に急速に普及し始めている訳です。
冒頭で触れましたマスコミの表現・・・『青色を実現したことによって、それまでに存在した赤、緑と合わせて三原色が揃った』という表現も、「白色光源」という視点からは、エネルギーの大きい可視域“短波長側”の LED を実現し、蛍光体技術との組み合わせで、(赤や緑の LED を併用するよりも)より良質な白色光源ができるようになった、ということに大きな意味があったと言うことができます。
この青色 LED の技術は更に進化して、現在では可視域よりも更に波長の短い(エネルギーの大きい)紫外 LED も実現されています。
注釈
≪※1≫
LED の分光分布は純粋の単色光ではなく、一般に半値幅が数十 nm 以下の狭い帯域幅の光源ですので、x y 色度図においては、外周の曲線(単色光軌跡)より少し内側に位置します。
3 原色をすべて(スペクトル軌跡上にある)単色光とした場合(例えば、RGB 表色系における等色実験の場合)でも、△RGB の領域(色再現域)は大きくなりますが、三角形の外側の領域は必ず残ります。

≪※2≫ RGB 表色系における 3 刺激値の定義

P ( λ ) :照明光の分光分布
ρ ( λ ) :物体の分光反射率
(光源色の場合は ρ ( λ ) = 1 とする。)
r ( λ ) , g ( λ ) , b ( λ ):RGB 表色系の等色関数
k : 定数
≪※3≫ x y 色度図における混色比
今、2 種の光色 [ G ] と [ R ] を考え、それらの色度座標をそれぞれ、 G ( xG , yG ) 、 R ( xR , yR )とします。 この 2 色を m : n の比で混色した場合の色[ F ]の色度座標を F ( xF , yF ) としますと、

となります。これは、色度図上で、混色結果の色度点 F ( xF , yF ) は、直線 GR を m : n で内分した点になるということを示しています。
x y 色度図が、線形空間であることによって、混色結果の色度点が 2 色の色度点を結ぶ直線上に来る、ということに加えて、その混色比に比例した内分点になる、ということになりますので、混色を扱う場合には XYZ 表色系( x y 色度図)は非常に相性が良いということが言えます。

≪※4≫ 均等色空間への非線形変換
次回(第 32 回)に説明を予定していますCIE L*u*v* 表色系や、CIE L*a*b* 表色系は、「非均等色差空間」である XYZ 表色系から( 1 / 3 乗の演算を含む)非一次式によって「均等色差空間」へ座標変換していますので、その代償として線形性は廃棄されています。従って、これらの「均等色差空間」では、混色結果が色度図上で直線にはなりません。
≪※5≫ 演色性
物体の色の見え方は、それを照明する光の特性によって変化します。照明による物体の色の見え方を演色といい、その演色の効果を決める照明光源の特性を演色性と言います。
≪※6≫ 色温度、相関色温度
一言で「白色光」と言っても、その分光分布は様々で、ロウソクや白熱ランプのように赤味を帯びて見えるものから、日中の太陽光のように、青白く見えるものまで色々あります。これらの白色光の色味を表すものとして、色温度および相関色温度という指数があります。色温度、相関色温度については次々回に採り上げたいと考えています。
≪※7≫ 蛍光発生と白色 LED
本連載の第 2 回の註釈≪※2≫と≪※3≫で、光の発生メカニズムとエネルギーの関係を簡単に説明致しました。大雑把に言えば、物質へ入射する光とその物質の電子との相互作用により、光のエネルギー △E が物質の電子エネルギーに受け渡される現象が物質による「光の吸収」であり、また、物質内電子のエネルギー状態の遷移(励起状態 EH から基底状態 EL への遷移)により、電子の持つエネルギー△E が原子外へ電磁波の形で放出されるエネルギーが「光(発光)」でした。
この電磁波(光)のエネルギーは電子のエネルギー準位の差となっており、光の振動数 ν に比例(波長に反比例)しています。
△E = EH - EL = hν = h ・ c / λ
( h はプランク定数で、h ≒ 6.63 × 10-34 Js )
通常の場合、「光の吸収」( EL → EH ) も、「光の放出」( EH → EL ) も授受されるエネルギー量はいずれも △E で等しいため、吸収される光と放出される光の波長は変わりません。

これに対して、蛍光の発生はそれよりもう少し複雑で、蛍光物質においては複数以上の励起状態の準位が関係してきます。ここでは説明を簡単にするためにこれらの励起準位を EH と E'H します。
( EH > E'H )
基底状態にあった電子が光(励起光)のエネルギー △E を吸収して、先ず高エネルギー準位の EH に励起されます。非蛍光プロセスでの発光では EH から直接元の規定状態 EL へ戻るのですが、蛍光プロセスにおいては、EH から一旦別の励起エネルギー準位の E'H ( E'H < EH ) に移ります。このエネルギー差 ( EH - E'H ) は光として放出されるのではなく、熱(振動)エネルギー等として発散されます。次いで励起電子が準位 E'H から基底状態 EL へ遷移する際に △E' ( = E'H - EL ) だけのエネルギーを電磁波として外部へ放出するのですが、これが「蛍光」です。
励起光吸収時のエネルギー △E よりも蛍光発光エネルギー △E' の方が小さいので、蛍光の波長は必ず励起光の波長よりも長くなります。
通常の熱放射型光源(白熱ランプなど)や放電型ランプ(水銀ランプなど)は、ランプに通電することによって高レベルのエネルギー準位に電気的に励起された電子が低エネルギー準位に遷移する過程でエネルギー差を電磁波(光)の形で原子の外へ放出するものです。 これに対して蛍光ランプは、蛍光物質に照射される電磁波(紫外放射)のエネルギーを(長波長側に)波長変換して可視光として再放出するものです。
上記の蛍光発生原理の説明は、話を単純にするために励起状態の準位の数を 2 つだけで説明しましたが、実際の蛍光物質においては、励起準位が多数存在し、励起された電子が多数の励起準位から基底準位へ遷移します。従って、放出される蛍光の波長は単一波長ではなく、数十 nm 以上の広い波長範囲幅を持っているのが一般的です。つまり蛍光の帯域幅は、(赤や緑などの)単色 LED の帯域幅よりも広くできますので、マルチチップ LED 方式よりも蛍光励起方式の方が白色光源としてより望ましい特性を達成し易いということができます。特に蛍光体を複数種併用して異なる波長の蛍光を同時発生させる「三原色蛍光方式」は連続スペクトルの良質な白色光を達成する主流技術であると言えます。
青は、赤や緑よりも波長が短いため、青色 LED を実現するためには、バンドギャップ △E がより大きい LED に適した半導体材料が必要です。この半導体材料の開発の障壁が非常に高かったため、青色 LED の 20 世紀中の実現が絶望視されていたのですが、その障壁を突き破ったのが今回のノーベル賞受賞者の方々です。
光と色の話 第一部

第31回 三原色で表せる色
・・・・・ 青色 LED と 白色照明 ・・・・・
2014 年 10 月 7 日、ビッグニュースが飛び込んできました。2014 年ノーベル物理学賞に赤崎勇名城大学終身教授、天野浩名古屋大学大学院教授、中村修二カリフォルニア大学教授の3名の方の受賞が決まったとの報です。青色発光ダイオード( LED )の開発・実用化に対する大きな貢献が認められ、日本の科学技術の高さが改めて脚光を浴びたことで日本中が沸き返りました。赤色や黄緑色の LED は既に 1960 年代に存在していましたが、青色の LED については技術的障壁が高く、20 世紀中には実用化困難と見られていたのを覆し、材料開発から量産化技術までに道筋をつけ、今日の LED 新時代を実現させたことが高く評価されたということです。
可視域短波長側の青の LED が実現したことによって、19 世紀末からの白熱ランプやその後の蛍光ランプなどに代わるエネルギー効率の高い長寿命の LED 白色光源が実現し、大幅な省エネルギーにより地球環境保全にも大きく貢献することになると期待されています。
この吉報を伝えるマスコミの報道で、少し気になった表現がありました。「青色を実現したことによって、それまでに存在した赤、緑と合わせて3 原色が揃った」ことの意味を説明する段で、殆どのマスコミが 『赤、緑、青の三原色で“全ての色”が作り出せる』・・・という言い方をしていました。しかし、この表現は厳密に言うと正しくありません。三原色を混色してもどうしても作り出せない色が存在します。
三原色の光で作り出せる色の範囲(色再現域)
赤[ R ]、緑[ G ]、青[ B ]の三原色の光の加法混色で作り出せる色の範囲(色再現域)は、x y 色度図上で三原色の色度座標点 R 、G 、B を直線で結んだ △RGB の内側(および辺上)のみで、△RGB の外側の色は鮮やかすぎて作り出すことができません。これは、本連載の前回(第 30 回)の等色実験の説明の中で詳しく説明した通りです。
x y 色度図の外周の曲線(単色光軌跡 or スペクトル軌跡)は外側に膨らんだ形状をしていますので、如何なる三原色 [ R ]、[ G ]、[ B ] の組み合わせを選択しても、必ず △RGB には含まれない領域が残ってしまいます。≪※1≫

従って、上述のマスコミの報道は、厳密には 『赤、緑、青の 3 原色で“殆ど全ての色”が作り出せる』 と表現すべきものです。例えば、本連載の第 19 回で説明しましたように、虹の色は水滴によって屈折・分散された単色光の色ですので、その色度点は単色光軌跡(スペクトル軌跡)上に存在し、三原色による三角形の外側になります。テレビ画面上の虹や、書物に印刷された虹の色は、虹の色を完全に再現しているという訳ではなく、厳密に言えば“虹に近い色”を不自然でないように見せている、ということですね。この連載で使用している色度図についても、周辺部(単色光軌跡および純紫軌跡)近傍の色は実際の色を再現できているわけではありません。
x y 色度図では 3 色の加法混色結果(色再現域)が三角形で表される理由
では、なぜ三原色 [ R ]、[ G ]、[ B ] の加法混色結果の色が x y 色度図の △RGB の内側だけに限定されるのでしょうか?これには数学的な説明が必要になります。 x y 色度図というのは、数学的には、線形空間であるという基本的性質がありますが、この「線形」であるということが、2 色の混色結果の色度点がそれらの色度点を結ぶ直線上に来る、ということの直接の理由なのです。
3 種の色 [ R ]、[ G ]、[ B ] の混色は、例えば最初に [ R ] と [ G ] の 2 色を混色させた結果の色に、更に
[ B ] を混色させるという2段階に分けて考えられます。結局、3 種の色の混色結果の色度点は、必ず 3 種の色の色度点で形成される三角形 ( △RGB ) の内部に存在することになります。
「線形性」とは
数学的に「線形」である、というのは、数学的変換関係が一次式で表されるということを言います。変換が一次式で表現できる最も簡単な場合、例えば y = A x( A :定数) は、x と y は正比例の関係にあり、x y 平面でのグラフは原点を通る傾き A の直線になります。このように変数 ( x ) の変化量 △x に対する関数値 ( y ) の変化量 △y の比 ( △y / △x = A ) が一定で、グラフ上では直線に表示される性質を「線形」と言います。
この y = A ・x に対して、例えば y' = B ・y+ C = AB ・ x + C ( B , C :定数) という演算処理を施した場合、これは(横軸は x のままで)縦軸が y' の座標となり、その座標において、傾きが AB で y' 切片が C の直線を表します。
つまり、この演算によって x y 座標から x y' 座標に座標変換されたことになるのですが、グラフが直線であるという性質はそのまま受け継がれています。

これに対して、例えば、y'' = x ・ y = x ・( A ・ x ) = A ・x2 という変換の場合はどうでしょう。
xy'' 座標では 二次曲線(放物線)を描くことになり、元の x y 座標の直線という特徴は保存されないことになります。
以上を一般化していえば、一次式(変数のべき乗が 1 である式)によって変換されたものは、直線が直線として変換されるということになります。このような変換を線形変換と言っています。変換式が非一次式である場合には、直線が曲線に変換されてしまう(線形性が保存されない)非線形変換ということになります。
加法混色 と 色度図の「線形性」との関係
以上の線形性が、混色に対してどのように関与しているかを以下に説明します。
XYZ 表色系の元の原理表色系である RGB 表色系における三刺激値 ( R 、G 、B ) は、その定義式≪※2≫からわかりますように、目に入射する光が視覚に与える刺激の強さ(心理物理量)を表しており、R 、G 、B それぞれが目に入射する“光の強さ”に比例しています。
RGB 表色系において、三刺激値が R 、G 、B である色 [ F ]を考えます。これを 3 つの刺激値 R 、G 、B を 3 軸とする直交座標空間で考えると、この色 [ F ]は、 F( R , G , B )というベクトルとして解釈することができます。
一方、RGB 表色系での色度座標 ( r , g , b ) は、刺激値総量に対する各刺激値の比
 ,
, ,
,
で定義され、r + g + b = 1ですから、ベクトル F( R , G , B )が 平面 R + G + B = 1 と交わる点が、色度座標 ( r , g , b )であると解釈することができます。この色度座標ベクトルを f ( r , g , b ) と書くことにします。
今、二つの色 [ F1 ] と [ F2 ] を混色した結果が [ FM ] となった場合を考えます。
F1 ( R1 , G1 , B1 ) 、F2 ( R2 ,G2 ,B2 ) を混色した結果を FM ( RM ,GM ,BM ) とすると、各刺激値は RM = R1+R2 、GM = G1+G2 、BM = B1+B2 となりますから、
F1 ( R1 , G1 , B1 ) + F2 ( R2 ,G2 ,B2 )= FM ( R1 + R2 , G1 + G2 , B1 + B2 )
というベクトル演算式で表すことができます。この和ベクトル FM は、2 本のベクトル F1 と F2 で決まる平面内に存在し、ベクトル F1 と F2 を隣り合う 2 辺とする平行四辺形の対角線となっています。従って、各ベクトル F1 、F2 、FM を含む平面(平行四辺形)と、 R + G + B = 1 の平面の交わりは平面同士の交わりで直線となります。ベクトル F1 、F2 、FM と 平面
R + G + B = 1 の交点を示す色度座標ベクトル f1 ( r1 ,g1 ,b1 )、 f2 ( r2 ,g2 ,b2 )、 fM ( rM ,gM ,bM ) も、この直線上に存在することになります。
これは、2 色 [ F1 ] と [ F2 ] の混色結果 [ FM ] の色度点 fM ( rM ,gM ,bM ) が rg b 色度図上で 2 色の色度点 f1 ( r1 , g1 , b1 )、 f2 ( r2 , g2 , b2 ) を結んだ直線上にあることを意味しています。
また、混色結果の色度点 fM ( rM , gM , bM ) は、 F1 (
R1 , G1 , B1 ) と F2 ( R2 ,G2 ,B2 ) のベクトルの大きさ(すなわち刺激値の大きさ)の比で内分された位置に来ます≪※3≫。
rg b 色度図を r g 平面に投影した図である r g 色度図においても、この直線関係(線形性)は保存されます。

RGB 表色系の三刺激値 R 、G 、B に対して下記の座標変換を行った結果得られるのが XYZ 表色系の三刺激値 X 、Y 、Z です。

この座標変換は一次変換式ですから、「線形性」は保存され、RGB 表色系の r g 色度図上での直線は x y 色度図上でも直線で表されることになります。≪※4≫
LED による白色光源
赤、黄緑色は 1960 年代に、黄色は 1970 年代に実現されましたが、可視域の短波長側に位置する青が無いために、 LED による白色光を作り出すことはできませんでした。従って、青色 LED の実現以前は、 LED は照明用と言うよりは、彩度の高い赤、黄、黄緑などの有彩色の「表示用」として主に利用されてきました。青色 LED の実現によって LED による「白色」光源が可能になったことが、( LED の低消費電力をはじめ各種の特徴も相俟って) 一般照明分野に広く実用化されるに至ったことの最大要因であった訳です。
LED による白色光源の実現方法としては、本連載第 17 回 『混色(その2)・・・同時加法混色、減法混色の応用例・・・』 で紹介させていただいております。 大きく分けて、
①マルチチップ LED 方式(三原色 BGR 方式や補色方式)、
②シングルチップ LED 方式 (蛍光励起方式)
の方式がありますが、“一般照明用”の白色 LED としては、マルチチップ方式は殆ど使用されず、殆どがシングルチップによる蛍光励起方式によっています。これは、単色 LED 自体の発光分光分布の半値幅が狭いため、マルチチップ LED 方式では、白色光源として分光分布の凹凸が大きく、物体の色の見え方が良くない(演色性≪※5≫が良くない)ことやコスト面で不利であることなどの要因があるためです。


シングルチップ LED 方式 (蛍光励起方式)でも、従来主流であったBlue-YAGタイプ(補色蛍光方式: B + Y ⇒ W ) は、エネルギー効率面やコスト面でのメリットは大きいのですが、やはり分光分布特性の凹凸が激しく演色性が良くないこと、また、相関色温度≪※6≫も高くなりがちという欠点がありました。

近年の白色 LED は、紫外や青(もしくは紫)の LED を励起光源として、複数種の蛍光体の組み合わせを最適化することによって、可視域全般に凹凸の少ない連続スペクトルを実現し、演色性の高い白色光源を実現するようになってきています。≪※7≫

これによって、従来型光源(白熱ランプや蛍光ランプ)に代わる良質な白色光源としての資質が備わり、更に小型で低消費電力、高速応答性などの特徴を活かして、様々な用途に急速に普及し始めている訳です。
冒頭で触れましたマスコミの表現・・・『青色を実現したことによって、それまでに存在した赤、緑と合わせて三原色が揃った』という表現も、「白色光源」という視点からは、エネルギーの大きい可視域“短波長側”の LED を実現し、蛍光体技術との組み合わせで、(赤や緑の LED を併用するよりも)より良質な白色光源ができるようになった、ということに大きな意味があったと言うことができます。
この青色 LED の技術は更に進化して、現在では可視域よりも更に波長の短い(エネルギーの大きい)紫外 LED も実現されています。
注釈
≪※1≫
LED の分光分布は純粋の単色光ではなく、一般に半値幅が数十 nm 以下の狭い帯域幅の光源ですので、x y 色度図においては、外周の曲線(単色光軌跡)より少し内側に位置します。
3 原色をすべて(スペクトル軌跡上にある)単色光とした場合(例えば、RGB 表色系における等色実験の場合)でも、△RGB の領域(色再現域)は大きくなりますが、三角形の外側の領域は必ず残ります。

≪※2≫ RGB 表色系における 3 刺激値の定義

P ( λ ) :照明光の分光分布
ρ ( λ ) :物体の分光反射率
(光源色の場合は ρ ( λ ) = 1 とする。)
r ( λ ) , g ( λ ) , b ( λ ):RGB 表色系の等色関数
k : 定数
≪※3≫ x y 色度図における混色比
今、2 種の光色 [ G ] と [ R ] を考え、それらの色度座標をそれぞれ、 G ( xG , yG ) 、 R ( xR , yR )とします。 この 2 色を m : n の比で混色した場合の色[ F ]の色度座標を F ( xF , yF ) としますと、

となります。これは、色度図上で、混色結果の色度点 F ( xF , yF ) は、直線 GR を m : n で内分した点になるということを示しています。
x y 色度図が、線形空間であることによって、混色結果の色度点が 2 色の色度点を結ぶ直線上に来る、ということに加えて、その混色比に比例した内分点になる、ということになりますので、混色を扱う場合には XYZ 表色系( x y 色度図)は非常に相性が良いということが言えます。

≪※4≫ 均等色空間への非線形変換
次回(第 32 回)に説明を予定していますCIE L*u*v* 表色系や、CIE L*a*b* 表色系は、「非均等色差空間」である XYZ 表色系から( 1 / 3 乗の演算を含む)非一次式によって「均等色差空間」へ座標変換していますので、その代償として線形性は廃棄されています。従って、これらの「均等色差空間」では、混色結果が色度図上で直線にはなりません。
≪※5≫ 演色性
物体の色の見え方は、それを照明する光の特性によって変化します。照明による物体の色の見え方を演色といい、その演色の効果を決める照明光源の特性を演色性と言います。
≪※6≫ 色温度、相関色温度
一言で「白色光」と言っても、その分光分布は様々で、ロウソクや白熱ランプのように赤味を帯びて見えるものから、日中の太陽光のように、青白く見えるものまで色々あります。これらの白色光の色味を表すものとして、色温度および相関色温度という指数があります。色温度、相関色温度については次々回に採り上げたいと考えています。
≪※7≫ 蛍光発生と白色 LED
本連載の第 2 回の註釈≪※2≫と≪※3≫で、光の発生メカニズムとエネルギーの関係を簡単に説明致しました。大雑把に言えば、物質へ入射する光とその物質の電子との相互作用により、光のエネルギー △E が物質の電子エネルギーに受け渡される現象が物質による「光の吸収」であり、また、物質内電子のエネルギー状態の遷移(励起状態 EH から基底状態 EL への遷移)により、電子の持つエネルギー△E が原子外へ電磁波の形で放出されるエネルギーが「光(発光)」でした。
この電磁波(光)のエネルギーは電子のエネルギー準位の差となっており、光の振動数 ν に比例(波長に反比例)しています。
△E = EH - EL = hν = h ・ c / λ
( h はプランク定数で、h ≒ 6.63 × 10-34 Js )
通常の場合、「光の吸収」( EL → EH ) も、「光の放出」( EH → EL ) も授受されるエネルギー量はいずれも △E で等しいため、吸収される光と放出される光の波長は変わりません。

これに対して、蛍光の発生はそれよりもう少し複雑で、蛍光物質においては複数以上の励起状態の準位が関係してきます。ここでは説明を簡単にするためにこれらの励起準位を EH と E'H します。
( EH > E'H )
基底状態にあった電子が光(励起光)のエネルギー △E を吸収して、先ず高エネルギー準位の EH に励起されます。非蛍光プロセスでの発光では EH から直接元の規定状態 EL へ戻るのですが、蛍光プロセスにおいては、EH から一旦別の励起エネルギー準位の E'H ( E'H < EH ) に移ります。このエネルギー差 ( EH - E'H ) は光として放出されるのではなく、熱(振動)エネルギー等として発散されます。次いで励起電子が準位 E'H から基底状態 EL へ遷移する際に △E' ( = E'H - EL ) だけのエネルギーを電磁波として外部へ放出するのですが、これが「蛍光」です。
励起光吸収時のエネルギー △E よりも蛍光発光エネルギー △E' の方が小さいので、蛍光の波長は必ず励起光の波長よりも長くなります。
通常の熱放射型光源(白熱ランプなど)や放電型ランプ(水銀ランプなど)は、ランプに通電することによって高レベルのエネルギー準位に電気的に励起された電子が低エネルギー準位に遷移する過程でエネルギー差を電磁波(光)の形で原子の外へ放出するものです。 これに対して蛍光ランプは、蛍光物質に照射される電磁波(紫外放射)のエネルギーを(長波長側に)波長変換して可視光として再放出するものです。
上記の蛍光発生原理の説明は、話を単純にするために励起状態の準位の数を 2 つだけで説明しましたが、実際の蛍光物質においては、励起準位が多数存在し、励起された電子が多数の励起準位から基底準位へ遷移します。従って、放出される蛍光の波長は単一波長ではなく、数十 nm 以上の広い波長範囲幅を持っているのが一般的です。つまり蛍光の帯域幅は、(赤や緑などの)単色 LED の帯域幅よりも広くできますので、マルチチップ LED 方式よりも蛍光励起方式の方が白色光源としてより望ましい特性を達成し易いということができます。特に蛍光体を複数種併用して異なる波長の蛍光を同時発生させる「三原色蛍光方式」は連続スペクトルの良質な白色光を達成する主流技術であると言えます。
青は、赤や緑よりも波長が短いため、青色 LED を実現するためには、バンドギャップ △E がより大きい LED に適した半導体材料が必要です。この半導体材料の開発の障壁が非常に高かったため、青色 LED の 20 世紀中の実現が絶望視されていたのですが、その障壁を突き破ったのが今回のノーベル賞受賞者の方々です。