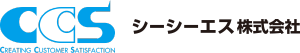光と色の話 第一部

第9回 輝度の性質
輝度の観察方向と観察距離
はじめに
私達の生活する照明空間での「明るさ」の評価には、「照度」と並んで「輝度」がよく使用されます。「輝度」は、光源の明るさ(輝きの程度)の指標として用いられますが、光源だけではなく、反射面(壁面や天井など)の明るさを評価する場合にもよく使われます。また、マシンビジョンにおいても「輝度(放射輝度)」はワークを照明する光源(特に明視野照明の場合など)を評価する場合に重要な明るさの指標になります。 今回は、輝度の重要な特性についてお話します。
照度と距離の関係 ・・・・・ 照度に関する距離の逆2乗則
輝度は、立体角や面積の幾何学的要素で規定される測光量でした。≪※1≫
従って、輝度の性質を考える場合には、光源面や反射面での光の「拡散特性」、すなわち光が光源面や反射面からどちらの方向にどのような強さで発散・進行していくのかが問題になります。 物体表面で光が反射するとき、反射光はどのような反射の仕方をするのでしょうか? 最も単純な場合として、1 本の直進光線が物体の反射面で反射する場合を考えて見ましょう。

鏡の場合は、図( 1a )のように光線が物体面に入射角 θ i で入射した場合、物体面の法線を挟んで反対側に、入射角 θ i と等しい反射角方向( θ r = θ i )のみに光が反射されます( 正反射 または 鏡面反射 と呼ばれます)。 つまり、鏡面を正反射方向( θ r = θ i )から見ると極めて明るく見えますが、正反射方向以外の方向( θ r ≠ θ i )から見ると「真っ暗」です。
一方、全く光沢性の感じられない、例えば白いチョークの表面や舗装道路上に引かれた白線のような反射面では、正反射方向への反射が特に強い訳ではなく、見る角度を変えても、明るさは殆ど変わりません。この場合は、反射光は多方向に拡散し、その光度が反射角 θ r に応じて単調連続的に変化した拡散反射になります。理想的な拡散反射面の場合、その面をどちらの方向から見てもその面の「明るさ(輝度)」は変わらず一定になりますが、このような拡散反射面では、反射光方向 θ r による光度(放射強度)分布 I ( θ r ) は、入射角 θ i に関係なく、立体的には 図( 1c )のように球状(断面は円形)の拡散反射特性を示します。≪※2≫
このような拡散反射特性を示す反射面を「均等拡散反射面」と言います。その内、物体への吸収が全く無く、全て反射される理想的反射面の場合を「完全拡散反射面」と言います 上記図( 1a ) と 図( 1c ) の場合は両極端な場合ですが、一般には、図( 1b )のように、物体表面への入射角 θ i に等しい反射角方向( θ r = θ i )への反射成分(正反射成分)が比較的多くを占め、その他の成分は、様々な方向へ拡散反射されます。≪※3≫ つまり、正反射方向以外の方向から見ても或る程度の明るさで見えます。光沢性が強い反射面ほど正反射成分の比率が大きくなり、その究極が図( 1a )の鏡面反射となります。 このような一般の拡散反射特性は、入射角 θ i が変化すると正反射方向(反射角 θ r )も変化するため、一般には入射角 θ i と反射角 θ r の両方の関数となります。 I = I ( θ i , θ r )
以上は反射面における光の拡散の説明ですが、透過物体面においても同様な光の拡散が発生します。≪※4≫
光源面における配光特性
反射面(や透過面)における拡散反射(透過)特性は上述のように説明されますが、光源面の場合には、その面が光を受けて反射(透過)する訳ではなく、自ら光を発しています。
光源面のある微小エリアから、光がどの方向にどれだけの「強さ(光度、放射強度)」で射出されているかを示す特性を「配光特性」と言います。
光源の配光特性が、上述の反射面における拡散反射(透過)特性に対応していると考えることができます。つまり、光を反射する面や透過する面は、理論的には光源の概念を拡張した「二次光源」として取り扱うことができる訳です。光源についても反射面の場合と同様に考えて、どの方向から見ても輝度が一定な光源面を「均等拡散光源」と言います。≪※5≫
従って、以降の説明では、反射面における反射光や透過面における透過光も「二次光源」として理論的には光源の一種として取扱うことにします。

輝度の性質(1)
均等拡散面(光源面や反射面)の輝度は、観察する方向に関係なく一定
光源面(あるいは反射面)の微小面積 A [ m2 ] の法線方向の光度を I0 [ cd ] 、その方向の輝度を L0 [ cd / m2 ] とすれば、輝度の定義に基いて

となります。 一方、法線と角度 θ をなす方向の光度を I ( θ )、
その方向の輝度を L ( θ ) [ cd / m2 ]とすると、同様に輝度の定義に基いて


と書くことができます。なお、分母において cos θ がかかっているのは、微小面積 A を斜め θ 方向から見ると、見かけの面積は
A ・ cos θ になることを表わしています。 均等拡散面(均等拡散光源および均等拡散反射面)の光度は、
I ( θ ) = I0 ・ cos θ で表わされますから、結局、斜め θ 方向の輝度 L ( θ ) は

となり、θ の値に関わらず、一定になるという訳です。つまり、 θ 方向の光度は cos θ 分暗くなりますが、見かけの面積も
cos θ だけ狭くなりますので、結果として両者が相殺されて輝度は一定になる訳です。逆に言えば、どの方向から見ても輝度が変わらない面(光源面、反射面)は均等拡散面である、ということができます。
例えば、蛍光ランプを見る場合、管の中央部を真正面から見ているとすれば、管の周辺部はかなり角度のついた斜め方向から見ていることになります。蛍光ランプの管面は殆ど均等拡散面になっていますので、管の中央部も周辺部もほぼ同じ「明るさ」に見えます。

輝度の性質(2) 輝度は“一般的には”観察距離によって変化しない。
前回(第 8 回)に詳しく述べましたように、「照度」は、基本的に光源から遠ざかるほど暗くなっていきます。これに対して、「輝度」は光源と観察者との距離が変わっても、“一般には”変化しないという、重要な性質があります。
例えば、テレビを見る時、1 m の距離から見ても、3 m の距離から見ても、画面の明るさ感に差はありません。また、天井の蛍光灯に照らされた白い壁面を 1 m の距離から見ても、3 m の位置から見ても壁面の明るさ感は変わりません。これは、我々人間はテレビの画面や壁面に無意識的に眼のピントを合わせて見ているからで、その時の明るさ感は「輝度」で評価しているからなのです。
では、なぜ「輝度」で評価すると明るさ感が変わらないのでしょうか?

では、なぜ「輝度」で評価すると明るさ感が変わらないのでしょうか?
私たちは眼のレンズ(角膜と水晶体)を通して視界の像を網膜上に結像させて物を見ています。肉眼が感じる「明るさ」は、網膜上に分布する視細胞が光によってどれだけ刺激を受けるかによって決まります。視細胞が受ける刺激の量は、網膜の単位面積にどれだけの光束が入射するか、つまり、網膜面の照度によって決まります。
同じ光源(あるいは物体)でもそれが近くにある時の視角は大きく(立体角 ω1 )なりますので、光源(あるいは物体)から発して眼のレンズを通る光束も多くなりますが、網膜上に結像される像の大きさも大きくなります。つまり距離が近いほど光源(物体)は大きく見えます。逆に、光源(物体)が遠くなると、視角は小さくなり(立体角 ω2 )、光源(物体)から発して眼のレンズを通る光束も少なくなりますが、同時に網膜上に結像される像の大きさも小さくなります。(距離が遠いほど小さく見えます。)
照度は、「単位面積あたりに入射する光束」でした。結局、眼のレンズを通過する光束と像の大きさ(像倍率)が相殺し、網膜面の照度(単位面積あたりの光束)は光源(物体)の距離にかかわらず一定になってしまうのです。

通常私達が生活する照明空間では、一般的には上記のような説明が成り立つ場合が多く、輝度は観察距離によって変化せず一定として取り扱われることが、半ば常識的になっています。しかしいつも必ずそうなるとは限りませんので注意が必要です≪※6≫。
注釈
≪※1≫ 「輝度」の定義
「輝度」は、“見かけの単位面積 [ m2 ] 当りの光度 [ cd ] ” でした。「光度」は “単位立体角 [ sr ] 当りの光束 [ lm ] ” でしたから、「輝度」は結局、“見かけの単位面積 [ m2 ] 当りかつ単位立体角 [ sr ] 当りの光束 [ lm ] ” ということもできます。
同様に、「放射輝度」は、“見かけの単位面積 [ m2 ] 当りの放射強度 [ W / sr ] ” でした。「放射強度」は “単位立体角 [ sr ] 当りの放射束 [ W ] ” ですから、「放射輝度」は結局、“見かけの単位面積 [ m2 ] 当りかつ単位立体角 [ sr ] 当りの放射束
[ W ] ” ということもできます。
≪※2≫ 均等拡散面の拡散反射特性
これを数式で記述すると
I ( θ r ) = I0・cos θ r
となります。ただし、I0 は、その面の法線( θ r = 0°)方向への光度です。
≪※3≫ 物体面での光の反射
物体表面に入射角 θ i で入射した光の内の一部は物体内部に入り込むことなく反射角 θ r 方向(法線を挟んで対象の θ r = θ i 方向)へ鏡面反射されます。また、残りの光は物体の内部に入り込みますが、物体を構成する分子(原子・電子)により散乱を受けて進行方向が変化したり、あるいは吸収を受けたりします。物体の特性によって散乱・吸収のされ方は色々ですが、空気中とは違って物体内部は分子が極めて稠密に存在しますので、散乱された光は更にまた別の分子群により多重に散乱を受け四方八方あらゆる方向へ進行方向が変わるとともに物質特有の吸収を受けます。その結果、入射媒質側の空間へ射出される散乱光成分も発生します。巨視的に見ればこの散乱光も反射光に含まれますので、その結果として図( 1c )に示すように、反射光の方向は正反射方向だけではなく、色々な方向に分布することになります。
つまり、物体面からの反射光は、一般には、表面で直接される反射光成分と、物体内に入り込んだ光の散乱光成分が合成されたものとなっています。 前者は照明光源の分光成分(照明光源の色)そのままであり、後者はその物体特有の吸収特性が反映された分光成分(物体の色)を示します。
鏡の場合には、内部に入り込む光の成分は僅かですので殆どが「鏡面反射」となります。一方、白いチョークの表面のような場合は、表面反射成分は僅かで殆どがチョークの内部に光が入り込み、多重散乱を受けた結果、図( 1c )のような拡散反射特性を示します。チョークの場合、入射光の入射角度が変化しても、この拡散反射特性は殆ど変化しません。
一般の物体の場合は、上記の鏡とチョークの中間的な特性を示します。光沢性のある物体の場合は、比較的鏡面反射成分が強めであり、非光沢性の物体の場合には鏡面反射成分がそれほど強くありません。
以上は、物体表面が理想的「平面」である場合ですが、実際の物体の表面を拡大して見ると細かな凹凸構造があるのが一般的です。従って、同じ物質(材質)であっても、微視的に見れば表面凹凸のどの部分に光が入射するかによって正反射光成分の方向が変わります。
例えば、通称「梨地」面と呼ばれるワークはこのような条件によって物体表面の場所によって巨視的な拡散反射特性は変動します。

≪※4≫ 透過面での光の拡散特性
光線が或る物体に入射して透過して行く場合も、その透過光については、上述の反射の場合と同様にその物体の特性に依存した拡散透過特性が観察されます。薄い板状物体に入射角 θ i で直線光線が入射した場合を考えます。完全透明板( 2a )の場合は、透過角 θ t = θ i ですなわち「素通し」となります。一方均等拡散板( 2c )の場合には、透過光の拡散特性は入射角 θ i に関係なく球状(断面は円形)となり、これは、I ( θ t ) = I0 ・ cos θ t と書くことができます。一般の半透明板は( 2b )のような特性を示し、入射角 θ i に依存してその拡散特性は変化します。

≪※5≫ 均等拡散光源
均等拡散光源では、光源面の法線方向の光度 I0 に対して θ 方向の光度 I ( θ ) が
I ( θ ) = I0 ・ cos θ
で表わされます。≪※2≫ の均等拡散反射の特性表記と同じ表現になっています。
≪※6≫ 輝度が観察距離によって変化しないための前提条件
「輝度は観察距離によって変化しない」という上記の説明が条件によっては成り立たない場合もあります。 下記(1)~(3)のような場合は、輝度が観察距離によって変動することになりますので注意が必要です。
(1) 光源面(反射面)の特性が均等拡散性から大きく外れる場合
輝度が観察距離に依存しないための前提条件の一つとして、光源面(あるいは反射面)の特性が均等拡散性であることがあります。
パッケージに実装された LED 光源には、集光レンズや反射鏡が併設されたものもあり、配光特性が非常に狭い場合があります。このような光源の場合には、輝度が距離によって変化する場合があります。

(2) 介在する媒質による光の吸収・散乱が無視できない場合
媒質が空気以外であったり、また空気であっても距離が何十 m 、何百 m も離れる場合は、その間の空気層での光の吸収や散乱による光束の低下が無視できなくなります。例えば、霧の立ち込めた中での街灯の輝度は、観察距離によって変化します。また、観察距離が短くても水族館の水槽内の照明の輝度は、観察距離によって変化します。
(3) 観察距離が極端に短い場合
視角の大きさに依存する光束と像倍率が互いに相殺するのは、レンズの光軸に比較的近い光路を通った結像光学系(近軸光学系といいます。)の場合です。距離が極端に近くなると、レンズ周辺部に入射する光線の角度が大きくなり、近軸光学系の領域から外れてきて、光束と像倍率の両者の関係が相殺しきれなくなってきて、観察距離によって輝度が変化する結果となります。
光と色の話 第一部

第9回 輝度の性質
輝度の観察方向と観察距離
はじめに
私達の生活する照明空間での「明るさ」の評価には、「照度」と並んで「輝度」がよく使用されます。「輝度」は、光源の明るさ(輝きの程度)の指標として用いられますが、光源だけではなく、反射面(壁面や天井など)の明るさを評価する場合にもよく使われます。また、マシンビジョンにおいても「輝度(放射輝度)」はワークを照明する光源(特に明視野照明の場合など)を評価する場合に重要な明るさの指標になります。 今回は、輝度の重要な特性についてお話します。
照度と距離の関係 ・・・・・ 照度に関する距離の逆2乗則
輝度は、立体角や面積の幾何学的要素で規定される測光量でした。≪※1≫
従って、輝度の性質を考える場合には、光源面や反射面での光の「拡散特性」、すなわち光が光源面や反射面からどちらの方向にどのような強さで発散・進行していくのかが問題になります。 物体表面で光が反射するとき、反射光はどのような反射の仕方をするのでしょうか? 最も単純な場合として、1 本の直進光線が物体の反射面で反射する場合を考えて見ましょう。

鏡の場合は、図( 1a )のように光線が物体面に入射角 θ i で入射した場合、物体面の法線を挟んで反対側に、入射角 θ i と等しい反射角方向( θ r = θ i )のみに光が反射されます( 正反射 または 鏡面反射 と呼ばれます)。 つまり、鏡面を正反射方向( θ r = θ i )から見ると極めて明るく見えますが、正反射方向以外の方向( θ r ≠ θ i )から見ると「真っ暗」です。
一方、全く光沢性の感じられない、例えば白いチョークの表面や舗装道路上に引かれた白線のような反射面では、正反射方向への反射が特に強い訳ではなく、見る角度を変えても、明るさは殆ど変わりません。この場合は、反射光は多方向に拡散し、その光度が反射角 θ r に応じて単調連続的に変化した拡散反射になります。理想的な拡散反射面の場合、その面をどちらの方向から見てもその面の「明るさ(輝度)」は変わらず一定になりますが、このような拡散反射面では、反射光方向 θ r による光度(放射強度)分布 I ( θ r ) は、入射角 θ i に関係なく、立体的には 図( 1c )のように球状(断面は円形)の拡散反射特性を示します。≪※2≫
このような拡散反射特性を示す反射面を「均等拡散反射面」と言います。その内、物体への吸収が全く無く、全て反射される理想的反射面の場合を「完全拡散反射面」と言います 上記図( 1a ) と 図( 1c ) の場合は両極端な場合ですが、一般には、図( 1b )のように、物体表面への入射角 θ i に等しい反射角方向( θ r = θ i )への反射成分(正反射成分)が比較的多くを占め、その他の成分は、様々な方向へ拡散反射されます。≪※3≫ つまり、正反射方向以外の方向から見ても或る程度の明るさで見えます。光沢性が強い反射面ほど正反射成分の比率が大きくなり、その究極が図( 1a )の鏡面反射となります。 このような一般の拡散反射特性は、入射角 θ i が変化すると正反射方向(反射角 θ r )も変化するため、一般には入射角 θ i と反射角 θ r の両方の関数となります。 I = I ( θ i , θ r )
以上は反射面における光の拡散の説明ですが、透過物体面においても同様な光の拡散が発生します。≪※4≫
光源面における配光特性
反射面(や透過面)における拡散反射(透過)特性は上述のように説明されますが、光源面の場合には、その面が光を受けて反射(透過)する訳ではなく、自ら光を発しています。
光源面のある微小エリアから、光がどの方向にどれだけの「強さ(光度、放射強度)」で射出されているかを示す特性を「配光特性」と言います。
光源の配光特性が、上述の反射面における拡散反射(透過)特性に対応していると考えることができます。つまり、光を反射する面や透過する面は、理論的には光源の概念を拡張した「二次光源」として取り扱うことができる訳です。光源についても反射面の場合と同様に考えて、どの方向から見ても輝度が一定な光源面を「均等拡散光源」と言います。≪※5≫
従って、以降の説明では、反射面における反射光や透過面における透過光も「二次光源」として理論的には光源の一種として取扱うことにします。

輝度の性質(1)
均等拡散面(光源面や反射面)の輝度は、観察する方向に関係なく一定
光源面(あるいは反射面)の微小面積 A [ m2 ] の法線方向の光度を I0 [ cd ] 、その方向の輝度を L0 [ cd / m2 ] とすれば、輝度の定義に基いて

となります。 一方、法線と角度 θ をなす方向の光度を I ( θ )、
その方向の輝度を L ( θ ) [ cd / m2 ]とすると、同様に輝度の定義に基いて


と書くことができます。なお、分母において cos θ がかかっているのは、微小面積 A を斜め θ 方向から見ると、見かけの面積は
A ・ cos θ になることを表わしています。 均等拡散面(均等拡散光源および均等拡散反射面)の光度は、
I ( θ ) = I0 ・ cos θ で表わされますから、結局、斜め θ 方向の輝度 L ( θ ) は

となり、θ の値に関わらず、一定になるという訳です。つまり、 θ 方向の光度は cos θ 分暗くなりますが、見かけの面積も
cos θ だけ狭くなりますので、結果として両者が相殺されて輝度は一定になる訳です。逆に言えば、どの方向から見ても輝度が変わらない面(光源面、反射面)は均等拡散面である、ということができます。
例えば、蛍光ランプを見る場合、管の中央部を真正面から見ているとすれば、管の周辺部はかなり角度のついた斜め方向から見ていることになります。蛍光ランプの管面は殆ど均等拡散面になっていますので、管の中央部も周辺部もほぼ同じ「明るさ」に見えます。

輝度の性質(2) 輝度は“一般的には”観察距離によって変化しない。
前回(第 8 回)に詳しく述べましたように、「照度」は、基本的に光源から遠ざかるほど暗くなっていきます。これに対して、「輝度」は光源と観察者との距離が変わっても、“一般には”変化しないという、重要な性質があります。
例えば、テレビを見る時、1 m の距離から見ても、3 m の距離から見ても、画面の明るさ感に差はありません。また、天井の蛍光灯に照らされた白い壁面を 1 m の距離から見ても、3 m の位置から見ても壁面の明るさ感は変わりません。これは、我々人間はテレビの画面や壁面に無意識的に眼のピントを合わせて見ているからで、その時の明るさ感は「輝度」で評価しているからなのです。
では、なぜ「輝度」で評価すると明るさ感が変わらないのでしょうか?

では、なぜ「輝度」で評価すると明るさ感が変わらないのでしょうか?
私たちは眼のレンズ(角膜と水晶体)を通して視界の像を網膜上に結像させて物を見ています。肉眼が感じる「明るさ」は、網膜上に分布する視細胞が光によってどれだけ刺激を受けるかによって決まります。視細胞が受ける刺激の量は、網膜の単位面積にどれだけの光束が入射するか、つまり、網膜面の照度によって決まります。
同じ光源(あるいは物体)でもそれが近くにある時の視角は大きく(立体角 ω1 )なりますので、光源(あるいは物体)から発して眼のレンズを通る光束も多くなりますが、網膜上に結像される像の大きさも大きくなります。つまり距離が近いほど光源(物体)は大きく見えます。逆に、光源(物体)が遠くなると、視角は小さくなり(立体角 ω2 )、光源(物体)から発して眼のレンズを通る光束も少なくなりますが、同時に網膜上に結像される像の大きさも小さくなります。(距離が遠いほど小さく見えます。)
照度は、「単位面積あたりに入射する光束」でした。結局、眼のレンズを通過する光束と像の大きさ(像倍率)が相殺し、網膜面の照度(単位面積あたりの光束)は光源(物体)の距離にかかわらず一定になってしまうのです。

通常私達が生活する照明空間では、一般的には上記のような説明が成り立つ場合が多く、輝度は観察距離によって変化せず一定として取り扱われることが、半ば常識的になっています。しかしいつも必ずそうなるとは限りませんので注意が必要です≪※6≫。
注釈
≪※1≫ 「輝度」の定義
「輝度」は、“見かけの単位面積 [ m2 ] 当りの光度 [ cd ] ” でした。「光度」は “単位立体角 [ sr ] 当りの光束 [ lm ] ” でしたから、「輝度」は結局、“見かけの単位面積 [ m2 ] 当りかつ単位立体角 [ sr ] 当りの光束 [ lm ] ” ということもできます。
同様に、「放射輝度」は、“見かけの単位面積 [ m2 ] 当りの放射強度 [ W / sr ] ” でした。「放射強度」は “単位立体角 [ sr ] 当りの放射束 [ W ] ” ですから、「放射輝度」は結局、“見かけの単位面積 [ m2 ] 当りかつ単位立体角 [ sr ] 当りの放射束
[ W ] ” ということもできます。
≪※2≫ 均等拡散面の拡散反射特性
これを数式で記述すると
I ( θ r ) = I0・cos θ r
となります。ただし、I0 は、その面の法線( θ r = 0°)方向への光度です。
≪※3≫ 物体面での光の反射
物体表面に入射角 θ i で入射した光の内の一部は物体内部に入り込むことなく反射角 θ r 方向(法線を挟んで対象の θ r = θ i 方向)へ鏡面反射されます。また、残りの光は物体の内部に入り込みますが、物体を構成する分子(原子・電子)により散乱を受けて進行方向が変化したり、あるいは吸収を受けたりします。物体の特性によって散乱・吸収のされ方は色々ですが、空気中とは違って物体内部は分子が極めて稠密に存在しますので、散乱された光は更にまた別の分子群により多重に散乱を受け四方八方あらゆる方向へ進行方向が変わるとともに物質特有の吸収を受けます。その結果、入射媒質側の空間へ射出される散乱光成分も発生します。巨視的に見ればこの散乱光も反射光に含まれますので、その結果として図( 1c )に示すように、反射光の方向は正反射方向だけではなく、色々な方向に分布することになります。
つまり、物体面からの反射光は、一般には、表面で直接される反射光成分と、物体内に入り込んだ光の散乱光成分が合成されたものとなっています。 前者は照明光源の分光成分(照明光源の色)そのままであり、後者はその物体特有の吸収特性が反映された分光成分(物体の色)を示します。
鏡の場合には、内部に入り込む光の成分は僅かですので殆どが「鏡面反射」となります。一方、白いチョークの表面のような場合は、表面反射成分は僅かで殆どがチョークの内部に光が入り込み、多重散乱を受けた結果、図( 1c )のような拡散反射特性を示します。チョークの場合、入射光の入射角度が変化しても、この拡散反射特性は殆ど変化しません。
一般の物体の場合は、上記の鏡とチョークの中間的な特性を示します。光沢性のある物体の場合は、比較的鏡面反射成分が強めであり、非光沢性の物体の場合には鏡面反射成分がそれほど強くありません。
以上は、物体表面が理想的「平面」である場合ですが、実際の物体の表面を拡大して見ると細かな凹凸構造があるのが一般的です。従って、同じ物質(材質)であっても、微視的に見れば表面凹凸のどの部分に光が入射するかによって正反射光成分の方向が変わります。
例えば、通称「梨地」面と呼ばれるワークはこのような条件によって物体表面の場所によって巨視的な拡散反射特性は変動します。

≪※4≫ 透過面での光の拡散特性
光線が或る物体に入射して透過して行く場合も、その透過光については、上述の反射の場合と同様にその物体の特性に依存した拡散透過特性が観察されます。薄い板状物体に入射角 θ i で直線光線が入射した場合を考えます。完全透明板( 2a )の場合は、透過角 θ t = θ i ですなわち「素通し」となります。一方均等拡散板( 2c )の場合には、透過光の拡散特性は入射角 θ i に関係なく球状(断面は円形)となり、これは、I ( θ t ) = I0 ・ cos θ t と書くことができます。一般の半透明板は( 2b )のような特性を示し、入射角 θ i に依存してその拡散特性は変化します。

≪※5≫ 均等拡散光源
均等拡散光源では、光源面の法線方向の光度 I0 に対して θ 方向の光度 I ( θ ) が
I ( θ ) = I0 ・ cos θ
で表わされます。≪※2≫ の均等拡散反射の特性表記と同じ表現になっています。
≪※6≫ 輝度が観察距離によって変化しないための前提条件
「輝度は観察距離によって変化しない」という上記の説明が条件によっては成り立たない場合もあります。 下記(1)~(3)のような場合は、輝度が観察距離によって変動することになりますので注意が必要です。
(1) 光源面(反射面)の特性が均等拡散性から大きく外れる場合
輝度が観察距離に依存しないための前提条件の一つとして、光源面(あるいは反射面)の特性が均等拡散性であることがあります。
パッケージに実装された LED 光源には、集光レンズや反射鏡が併設されたものもあり、配光特性が非常に狭い場合があります。このような光源の場合には、輝度が距離によって変化する場合があります。

(2) 介在する媒質による光の吸収・散乱が無視できない場合
媒質が空気以外であったり、また空気であっても距離が何十 m 、何百 m も離れる場合は、その間の空気層での光の吸収や散乱による光束の低下が無視できなくなります。例えば、霧の立ち込めた中での街灯の輝度は、観察距離によって変化します。また、観察距離が短くても水族館の水槽内の照明の輝度は、観察距離によって変化します。
(3) 観察距離が極端に短い場合
視角の大きさに依存する光束と像倍率が互いに相殺するのは、レンズの光軸に比較的近い光路を通った結像光学系(近軸光学系といいます。)の場合です。距離が極端に近くなると、レンズ周辺部に入射する光線の角度が大きくなり、近軸光学系の領域から外れてきて、光束と像倍率の両者の関係が相殺しきれなくなってきて、観察距離によって輝度が変化する結果となります。
光と色の話 第一部

第9回 輝度の性質
輝度の観察方向と観察距離
はじめに
私達の生活する照明空間での「明るさ」の評価には、「照度」と並んで「輝度」がよく使用されます。「輝度」は、光源の明るさ(輝きの程度)の指標として用いられますが、光源だけではなく、反射面(壁面や天井など)の明るさを評価する場合にもよく使われます。また、マシンビジョンにおいても「輝度(放射輝度)」はワークを照明する光源(特に明視野照明の場合など)を評価する場合に重要な明るさの指標になります。 今回は、輝度の重要な特性についてお話します。
照度と距離の関係 ・・・・・ 照度に関する距離の逆2乗則
輝度は、立体角や面積の幾何学的要素で規定される測光量でした。≪※1≫
従って、輝度の性質を考える場合には、光源面や反射面での光の「拡散特性」、すなわち光が光源面や反射面からどちらの方向にどのような強さで発散・進行していくのかが問題になります。 物体表面で光が反射するとき、反射光はどのような反射の仕方をするのでしょうか? 最も単純な場合として、1 本の直進光線が物体の反射面で反射する場合を考えて見ましょう。

鏡の場合は、図( 1a )のように光線が物体面に入射角 θ i で入射した場合、物体面の法線を挟んで反対側に、入射角 θ i と等しい反射角方向( θ r = θ i )のみに光が反射されます( 正反射 または 鏡面反射 と呼ばれます)。 つまり、鏡面を正反射方向( θ r = θ i )から見ると極めて明るく見えますが、正反射方向以外の方向( θ r ≠ θ i )から見ると「真っ暗」です。
一方、全く光沢性の感じられない、例えば白いチョークの表面や舗装道路上に引かれた白線のような反射面では、正反射方向への反射が特に強い訳ではなく、見る角度を変えても、明るさは殆ど変わりません。この場合は、反射光は多方向に拡散し、その光度が反射角 θ r に応じて単調連続的に変化した拡散反射になります。理想的な拡散反射面の場合、その面をどちらの方向から見てもその面の「明るさ(輝度)」は変わらず一定になりますが、このような拡散反射面では、反射光方向 θ r による光度(放射強度)分布 I ( θ r ) は、入射角 θ i に関係なく、立体的には 図( 1c )のように球状(断面は円形)の拡散反射特性を示します。≪※2≫
このような拡散反射特性を示す反射面を「均等拡散反射面」と言います。その内、物体への吸収が全く無く、全て反射される理想的反射面の場合を「完全拡散反射面」と言います 上記図( 1a ) と 図( 1c ) の場合は両極端な場合ですが、一般には、図( 1b )のように、物体表面への入射角 θ i に等しい反射角方向( θ r = θ i )への反射成分(正反射成分)が比較的多くを占め、その他の成分は、様々な方向へ拡散反射されます。≪※3≫ つまり、正反射方向以外の方向から見ても或る程度の明るさで見えます。光沢性が強い反射面ほど正反射成分の比率が大きくなり、その究極が図( 1a )の鏡面反射となります。 このような一般の拡散反射特性は、入射角 θ i が変化すると正反射方向(反射角 θ r )も変化するため、一般には入射角 θ i と反射角 θ r の両方の関数となります。 I = I ( θ i , θ r )
以上は反射面における光の拡散の説明ですが、透過物体面においても同様な光の拡散が発生します。≪※4≫
光源面における配光特性
反射面(や透過面)における拡散反射(透過)特性は上述のように説明されますが、光源面の場合には、その面が光を受けて反射(透過)する訳ではなく、自ら光を発しています。
光源面のある微小エリアから、光がどの方向にどれだけの「強さ(光度、放射強度)」で射出されているかを示す特性を「配光特性」と言います。
光源の配光特性が、上述の反射面における拡散反射(透過)特性に対応していると考えることができます。つまり、光を反射する面や透過する面は、理論的には光源の概念を拡張した「二次光源」として取り扱うことができる訳です。光源についても反射面の場合と同様に考えて、どの方向から見ても輝度が一定な光源面を「均等拡散光源」と言います。≪※5≫
従って、以降の説明では、反射面における反射光や透過面における透過光も「二次光源」として理論的には光源の一種として取扱うことにします。

輝度の性質(1)
均等拡散面(光源面や反射面)の輝度は、観察する方向に関係なく一定
光源面(あるいは反射面)の微小面積 A [ m2 ] の法線方向の光度を I0 [ cd ] 、その方向の輝度を L0 [ cd / m2 ] とすれば、輝度の定義に基いて

となります。 一方、法線と角度 θ をなす方向の光度を I ( θ )、
その方向の輝度を L ( θ ) [ cd / m2 ]とすると、同様に輝度の定義に基いて


と書くことができます。なお、分母において cos θ がかかっているのは、微小面積 A を斜め θ 方向から見ると、見かけの面積は
A ・ cos θ になることを表わしています。 均等拡散面(均等拡散光源および均等拡散反射面)の光度は、
I ( θ ) = I0 ・ cos θ で表わされますから、結局、斜め θ 方向の輝度 L ( θ ) は

となり、θ の値に関わらず、一定になるという訳です。つまり、 θ 方向の光度は cos θ 分暗くなりますが、見かけの面積も
cos θ だけ狭くなりますので、結果として両者が相殺されて輝度は一定になる訳です。逆に言えば、どの方向から見ても輝度が変わらない面(光源面、反射面)は均等拡散面である、ということができます。
例えば、蛍光ランプを見る場合、管の中央部を真正面から見ているとすれば、管の周辺部はかなり角度のついた斜め方向から見ていることになります。蛍光ランプの管面は殆ど均等拡散面になっていますので、管の中央部も周辺部もほぼ同じ「明るさ」に見えます。

輝度の性質(2) 輝度は“一般的には”観察距離によって変化しない。
前回(第 8 回)に詳しく述べましたように、「照度」は、基本的に光源から遠ざかるほど暗くなっていきます。これに対して、「輝度」は光源と観察者との距離が変わっても、“一般には”変化しないという、重要な性質があります。
例えば、テレビを見る時、1 m の距離から見ても、3 m の距離から見ても、画面の明るさ感に差はありません。また、天井の蛍光灯に照らされた白い壁面を 1 m の距離から見ても、3 m の位置から見ても壁面の明るさ感は変わりません。これは、我々人間はテレビの画面や壁面に無意識的に眼のピントを合わせて見ているからで、その時の明るさ感は「輝度」で評価しているからなのです。
では、なぜ「輝度」で評価すると明るさ感が変わらないのでしょうか?

では、なぜ「輝度」で評価すると明るさ感が変わらないのでしょうか?
私たちは眼のレンズ(角膜と水晶体)を通して視界の像を網膜上に結像させて物を見ています。肉眼が感じる「明るさ」は、網膜上に分布する視細胞が光によってどれだけ刺激を受けるかによって決まります。視細胞が受ける刺激の量は、網膜の単位面積にどれだけの光束が入射するか、つまり、網膜面の照度によって決まります。
同じ光源(あるいは物体)でもそれが近くにある時の視角は大きく(立体角 ω1 )なりますので、光源(あるいは物体)から発して眼のレンズを通る光束も多くなりますが、網膜上に結像される像の大きさも大きくなります。つまり距離が近いほど光源(物体)は大きく見えます。逆に、光源(物体)が遠くなると、視角は小さくなり(立体角 ω2 )、光源(物体)から発して眼のレンズを通る光束も少なくなりますが、同時に網膜上に結像される像の大きさも小さくなります。(距離が遠いほど小さく見えます。)
照度は、「単位面積あたりに入射する光束」でした。結局、眼のレンズを通過する光束と像の大きさ(像倍率)が相殺し、網膜面の照度(単位面積あたりの光束)は光源(物体)の距離にかかわらず一定になってしまうのです。

通常私達が生活する照明空間では、一般的には上記のような説明が成り立つ場合が多く、輝度は観察距離によって変化せず一定として取り扱われることが、半ば常識的になっています。しかしいつも必ずそうなるとは限りませんので注意が必要です≪※6≫。
注釈
≪※1≫ 「輝度」の定義
「輝度」は、“見かけの単位面積 [ m2 ] 当りの光度 [ cd ] ” でした。「光度」は “単位立体角 [ sr ] 当りの光束 [ lm ] ” でしたから、「輝度」は結局、“見かけの単位面積 [ m2 ] 当りかつ単位立体角 [ sr ] 当りの光束 [ lm ] ” ということもできます。
同様に、「放射輝度」は、“見かけの単位面積 [ m2 ] 当りの放射強度 [ W / sr ] ” でした。「放射強度」は “単位立体角 [ sr ] 当りの放射束 [ W ] ” ですから、「放射輝度」は結局、“見かけの単位面積 [ m2 ] 当りかつ単位立体角 [ sr ] 当りの放射束
[ W ] ” ということもできます。
≪※2≫ 均等拡散面の拡散反射特性
これを数式で記述すると
I ( θ r ) = I0・cos θ r
となります。ただし、I0 は、その面の法線( θ r = 0°)方向への光度です。
≪※3≫ 物体面での光の反射
物体表面に入射角 θ i で入射した光の内の一部は物体内部に入り込むことなく反射角 θ r 方向(法線を挟んで対象の θ r = θ i 方向)へ鏡面反射されます。また、残りの光は物体の内部に入り込みますが、物体を構成する分子(原子・電子)により散乱を受けて進行方向が変化したり、あるいは吸収を受けたりします。物体の特性によって散乱・吸収のされ方は色々ですが、空気中とは違って物体内部は分子が極めて稠密に存在しますので、散乱された光は更にまた別の分子群により多重に散乱を受け四方八方あらゆる方向へ進行方向が変わるとともに物質特有の吸収を受けます。その結果、入射媒質側の空間へ射出される散乱光成分も発生します。巨視的に見ればこの散乱光も反射光に含まれますので、その結果として図( 1c )に示すように、反射光の方向は正反射方向だけではなく、色々な方向に分布することになります。
つまり、物体面からの反射光は、一般には、表面で直接される反射光成分と、物体内に入り込んだ光の散乱光成分が合成されたものとなっています。 前者は照明光源の分光成分(照明光源の色)そのままであり、後者はその物体特有の吸収特性が反映された分光成分(物体の色)を示します。
鏡の場合には、内部に入り込む光の成分は僅かですので殆どが「鏡面反射」となります。一方、白いチョークの表面のような場合は、表面反射成分は僅かで殆どがチョークの内部に光が入り込み、多重散乱を受けた結果、図( 1c )のような拡散反射特性を示します。チョークの場合、入射光の入射角度が変化しても、この拡散反射特性は殆ど変化しません。
一般の物体の場合は、上記の鏡とチョークの中間的な特性を示します。光沢性のある物体の場合は、比較的鏡面反射成分が強めであり、非光沢性の物体の場合には鏡面反射成分がそれほど強くありません。
以上は、物体表面が理想的「平面」である場合ですが、実際の物体の表面を拡大して見ると細かな凹凸構造があるのが一般的です。従って、同じ物質(材質)であっても、微視的に見れば表面凹凸のどの部分に光が入射するかによって正反射光成分の方向が変わります。
例えば、通称「梨地」面と呼ばれるワークはこのような条件によって物体表面の場所によって巨視的な拡散反射特性は変動します。

≪※4≫ 透過面での光の拡散特性
光線が或る物体に入射して透過して行く場合も、その透過光については、上述の反射の場合と同様にその物体の特性に依存した拡散透過特性が観察されます。薄い板状物体に入射角 θ i で直線光線が入射した場合を考えます。完全透明板( 2a )の場合は、透過角 θ t = θ i ですなわち「素通し」となります。一方均等拡散板( 2c )の場合には、透過光の拡散特性は入射角 θ i に関係なく球状(断面は円形)となり、これは、I ( θ t ) = I0 ・ cos θ t と書くことができます。一般の半透明板は( 2b )のような特性を示し、入射角 θ i に依存してその拡散特性は変化します。

≪※5≫ 均等拡散光源
均等拡散光源では、光源面の法線方向の光度 I0 に対して θ 方向の光度 I ( θ ) が
I ( θ ) = I0 ・ cos θ
で表わされます。≪※2≫ の均等拡散反射の特性表記と同じ表現になっています。
≪※6≫ 輝度が観察距離によって変化しないための前提条件
「輝度は観察距離によって変化しない」という上記の説明が条件によっては成り立たない場合もあります。 下記(1)~(3)のような場合は、輝度が観察距離によって変動することになりますので注意が必要です。
(1) 光源面(反射面)の特性が均等拡散性から大きく外れる場合
輝度が観察距離に依存しないための前提条件の一つとして、光源面(あるいは反射面)の特性が均等拡散性であることがあります。
パッケージに実装された LED 光源には、集光レンズや反射鏡が併設されたものもあり、配光特性が非常に狭い場合があります。このような光源の場合には、輝度が距離によって変化する場合があります。

(2) 介在する媒質による光の吸収・散乱が無視できない場合
媒質が空気以外であったり、また空気であっても距離が何十 m 、何百 m も離れる場合は、その間の空気層での光の吸収や散乱による光束の低下が無視できなくなります。例えば、霧の立ち込めた中での街灯の輝度は、観察距離によって変化します。また、観察距離が短くても水族館の水槽内の照明の輝度は、観察距離によって変化します。
(3) 観察距離が極端に短い場合
視角の大きさに依存する光束と像倍率が互いに相殺するのは、レンズの光軸に比較的近い光路を通った結像光学系(近軸光学系といいます。)の場合です。距離が極端に近くなると、レンズ周辺部に入射する光線の角度が大きくなり、近軸光学系の領域から外れてきて、光束と像倍率の両者の関係が相殺しきれなくなってきて、観察距離によって輝度が変化する結果となります。