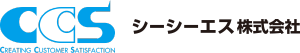光と色の話 第一部

第3回 可視域とは?
はじめに
広義の「光」は、紫外、可視、赤外に分けられますが、紫外と可視、あるいは、可視と赤外の境界はどこにあり、何故その波長帯が境界になっているのでしょうか?
人間の眼の「可視域」
「可視」とはその文字が示す通り、「みることができる」という意味ですが、人間の眼の明るさを感じる感度というのは、光の波長に対して一定ではありません。可視域のほぼ中央部(波長 555 nm )に感度のピークがあり、短波長側あるいは長波長側に向かって徐々に感度が低下して行き、ついには感度ゼロ、すなわち光のエネルギーはあっても全く明るさを感じなくなります。
この特性は個人個人によっても微妙に異なっており、また同一人物でも心理的要因で変動したり、また年齢によって変化していくことも知られています。

しかし、「明るさ」を客観的・定量的に評価する必要性があるため、人類の平均的な視覚特性を代表するものとして「標準分光視感効率」≪※1≫ が定められました。図ではおよそ 720 nm 以上、あるいは、およそ 420 nm 以下では感度(応答度)がゼロになっているように見えますが、完全にゼロになっている訳ではありません。この形状からも分かりますように、紫外と可視、あるいは可視と赤外の境界波長は明確に何 nm と区切られる訳ではなく、「可視域」の境界は曖昧で、各種規格や学会、団体等でもその規定は一致している訳ではありません。≪※2≫
では、この可視域の両端が、これらの波長帯に存在するのは何故なのでしょうか? 短波長側(紫外と可視の境界)と長波長側(可視と赤外の境界)について、それぞれ考えてみましょう。
紫外と可視の境界(短波長側)
光、すなわち電磁波は波長が短くなるほどエネルギーが強くなり、生体への悪影響も大きくなっていきますが、可視から紫外にわたる波長領域でも、特に人間の眼に与える影響が問題になってきます。光に対して人間の眼の最も敏感な部分は眼底にある網膜(視細胞)なのですが、「光」に敏感な為に紫外などの光子エネルギーの大きい短波長成分に対しては特に損傷を受けやすいことになります。

それを避けるために網膜に至るまでの角膜、水晶体、硝子体などの組織が光子エネルギーの強い紫外成分を吸収し、網膜に紫外成分が直接到達しないようになっています。つまり、角膜や水晶体や硝子体が短波長カットフィルタの役割を果たしているのです。当然多量の紫外照射を受けると角膜や水晶体も損傷を受けてしまいます。このように、短波長側の可視限界は網膜(視細胞)保護のためであると言えます。
可視と赤外の境界(長波長側)
可視域よりも短い波長の光は、上述のように角膜や水晶体、硝子体等の組織によってブロックされて網膜(視細胞)に到達できないため、人間の眼は「明るさ」を感じることができないのですが、可視域よりも長い波長の光についてはどうなのでしょうか? 網膜に到達する光の波長は、実は可視域だけではなく赤外域の千数百 nm にまで至っています。つまり、およそ 780 ~ 千数百 nm の波長の赤外域の光も網膜に達しているのですが、人間の眼はこの赤外域の光に対して全く「明るさ」を感じることがないのです。これは何故なのでしょうか?
自然界には様々な「色」の物体がありますが、その「色」の原因となる波長毎の反射率特性(分光反射率特性)を、可視域だけでなく赤外域にまでわたって調べてみると、面白い傾向があります。

物体の「色」毎に可視域の分光反射率特性が異なっており、その特性は様々な凹凸形状をとっていることがわかります。しかしその一方で赤外域の分光反射率特性にはあまり凹凸が無く単純な形状であることがわかります。例外はありますが、一般に多くの自然界の動植物の分光反射率特性は、可視域でその色に応じた特徴的な凹凸があり、赤外域ではあまり凹凸がなく単純な特性であることが多いようです。

人類は太古の時代よりこの地球環境に適応し植物の実や動物を食料として種を保ってきたのですが、地上で生きていくためには、例えば植物の果実が熟して “ 食べごろ ” であることを知らなければなりません。果実が熟すことは主に「色」や形で判断するのは我々自身の生活体験からもよく分かります。青い果実から徐々に色が変化し、赤く熟した果実になるということは、その果実の可視域の分光反射率特性が変化していくということです。一方赤外域の分光反射率特性は果実の熟し加減にはあまり関係しないようです。
人間が生を保つ為の情報量が圧倒的に可視域に集中しており、 “ 見えてもあまり役に立たない ” 赤外は見えなくてもあまり支障が無い、ということがわかります。このように、長波長側の可視限界は人類の地上環境への適応の結果ということがおおいに考えられます。
このように考えると、環境への適合という手段で我々生物は特性を最適化 してきたのだなぁと改めて感じます。
「器械の眼」の「可視域」
人間の眼の「可視域」は上述のような事情でおよそ 380 ~ 780 nm の範囲になっていると考えられますが、カメラなどの「器械の眼」の感度はどうなっているのでしょうか?
マシンビジョンでは CCD カメラや C - MOS カメラなどと呼ばれるカメラがよく使用されます。これらのカメラの撮像素子にはほとんどがシリコン ( Si ) 系の半導体受光素子≪※3≫が使われているようです。半導体受光素子は、 p 型半導体と n 型半導体の接合部で光を電気に変換しているのですが、この光電変換の感度特性は半導体素材によって決まります。シリコン半導体受光素子の場合、およそ 200 nm 近辺から 1100 nm 近辺の波長範囲に感度をもち、人間の可視域をカバーしていますので、カメラの撮像素子を初めとして多種多様な用途の「器械の眼」として最も多く使用されています。
また人間の可視域以外の波長範囲に対しては、シリコン ( Si ) だけではカバーしきれないので、対象の波長域に応じて各種の受光素子が使い分けられています。
紫外域についてはシリコン ( Si ) 以外にも、ガリウム・リン ( GaP ) 、ガリウム・ヒ素・リン ( GaAsP ) などが使われますし、赤外域については、インジウム・ガリウム・ヒ素 ( InGaAs ) 、インジウム・アンチモン ( InSb ) 、水銀・カドミウム・テルル ( HgCdTe ) などが使われます。≪※4≫

このように紫外から赤外に至るまで、様々な種類の受光素子が開発されていますが、その器械が何をする為の器械であるか、器械の目的によって「器械の眼」には、どの受光素子が適するのかが決まります。
このとき、各種の受光素子をそのまま搭載するのではなく、多くの場合はその器械の目的に応じて最適の分光応答度に調整します。例えば、人間の眼で見た明るさを評価したい場合には、シリコン受光素子に適切な分光透過率特性の光学フィルタをかけてトータルの分光応答度が人間の平均的な視覚特性(標準分光視感効率 V ( λ ) )の形状になるようにします。≪※5≫
注釈
≪※1≫
以前は、「標準比視感度」という用語が使用されていましたが、最近は学会等を中心に「標準分光視感効率」という用語が使われるようになっています。
≪※2≫
| 【 ISO 】 | 360 ~ 830 nm ( TC 2 - 35 PHOTOMETRY draft ) |
|---|---|
| 【法律(計量法)】 | 360 ~ 830 nm (計量法第 19 章照度計第一節検定第 794 条 |
| 【照明学会】 | 360 nm ないし 400 nm から 760 nm ないし 830 nm まで (測色では 380 nm から 780 nm とするのが慣例) |
| 【 JIS Z 8120 光学用語 】 | 一般に可視放射の波長範囲の 短波長限界は 360 ~ 400 nm 、 長波長限界は 760 ~ 830 nm にあると考えてよい |
≪※3≫
光を電気信号に変換する半導体電子部品のこと。光が半導体受光素子に当ると、 “ 内部光電効果 ” によって、入射光の強弱に応じて電流や電圧の出力が変化します。フォトダイオード、フォトトランジスタ、太陽電池、 CCD 撮像素子、 C - MOS 撮像素子などの半導体受光素子がよく使用されます。ここでは触れていませんが、更に半導体以外にも、 “ 外部光電効果 ” を利用した光電子増倍管などの光電管類もあります。
≪※4≫
この図では、各種受光素子が感度を有する波長帯を示していますが、これらの波長帯の中でも感度の高低分布があります。
≪※5≫
器械の眼に具備すべき分光応答度特性の実現方法として、受光素子(センサー)に光学フィルタをかける方法(フィルタ方式)で説明しましたが、別の実現方法としては「分光方式」があります。
「分光方式」は、評価対象の光を波長成分ごと(例えば 10 nm ピッチ)に分けて測定し、その測定値に目的とする作用関数を数値で掛け算し合算する方法です。本連載の第1回の注釈≪※6≫のような計算です。
≪※6≫
第2回に、波長が短い光ほど光子エネルギーが大きいことをお話しました。波長の短い紫外領域の中でも波長の短い UV - C の領域は、生体に対して大きな損傷を与えてしまいますが、これを利用してバクテリア、ウィルス、カビなどの菌種を殺すための光源(放射源)が殺菌灯です。図に示すような波長 260 nm 近辺の紫外放射は、細菌やウィルスの核酸( DNA )を破壊して殺菌する効果が大きいと言われています。主に、医療用(手術室や、医用器具の殺菌など)、食品用(食材や調理器具の殺菌など)、化粧品工場、製薬工場などでよく使用されているようです。また、魚類用水槽にもよく使用され、飼育水の殺菌による魚病防止、飼育水の透明度維持(藻の抑制)や臭い防止、食べ残しの餌の腐敗防止などに効果を発揮しているようです。
≪※7≫
JIS Z 8811 - 1968 「殺菌紫外線の測定方法」に規定された殺菌効果特性
≪※8≫
レンズやミラーなどの光学系を介して対象の光を評価する場合は、当然ながらその光学系の特性(分光透過率、分光反射率など)も考慮に入れて器械の眼の特性を設定してやる必要があります。特に、紫外域や赤外域の場合は光学系(光学材料)の透過・反射特性が問題になることが多いので注意が必要です。
光と色の話 第一部

第3回 可視域とは?
はじめに
広義の「光」は、紫外、可視、赤外に分けられますが、紫外と可視、あるいは、可視と赤外の境界はどこにあり、何故その波長帯が境界になっているのでしょうか?
人間の眼の「可視域」
「可視」とはその文字が示す通り、「みることができる」という意味ですが、人間の眼の明るさを感じる感度というのは、光の波長に対して一定ではありません。可視域のほぼ中央部(波長 555 nm )に感度のピークがあり、短波長側あるいは長波長側に向かって徐々に感度が低下して行き、ついには感度ゼロ、すなわち光のエネルギーはあっても全く明るさを感じなくなります。
この特性は個人個人によっても微妙に異なっており、また同一人物でも心理的要因で変動したり、また年齢によって変化していくことも知られています。

しかし、「明るさ」を客観的・定量的に評価する必要性があるため、人類の平均的な視覚特性を代表するものとして「標準分光視感効率」≪※1≫ が定められました。図ではおよそ 720 nm 以上、あるいは、およそ 420 nm 以下では感度(応答度)がゼロになっているように見えますが、完全にゼロになっている訳ではありません。この形状からも分かりますように、紫外と可視、あるいは可視と赤外の境界波長は明確に何 nm と区切られる訳ではなく、「可視域」の境界は曖昧で、各種規格や学会、団体等でもその規定は一致している訳ではありません。≪※2≫
では、この可視域の両端が、これらの波長帯に存在するのは何故なのでしょうか? 短波長側(紫外と可視の境界)と長波長側(可視と赤外の境界)について、それぞれ考えてみましょう。
紫外と可視の境界(短波長側)
光、すなわち電磁波は波長が短くなるほどエネルギーが強くなり、生体への悪影響も大きくなっていきますが、可視から紫外にわたる波長領域でも、特に人間の眼に与える影響が問題になってきます。光に対して人間の眼の最も敏感な部分は眼底にある網膜(視細胞)なのですが、「光」に敏感な為に紫外などの光子エネルギーの大きい短波長成分に対しては特に損傷を受けやすいことになります。

それを避けるために網膜に至るまでの角膜、水晶体、硝子体などの組織が光子エネルギーの強い紫外成分を吸収し、網膜に紫外成分が直接到達しないようになっています。つまり、角膜や水晶体や硝子体が短波長カットフィルタの役割を果たしているのです。当然多量の紫外照射を受けると角膜や水晶体も損傷を受けてしまいます。このように、短波長側の可視限界は網膜(視細胞)保護のためであると言えます。
可視と赤外の境界(長波長側)
可視域よりも短い波長の光は、上述のように角膜や水晶体、硝子体等の組織によってブロックされて網膜(視細胞)に到達できないため、人間の眼は「明るさ」を感じることができないのですが、可視域よりも長い波長の光についてはどうなのでしょうか? 網膜に到達する光の波長は、実は可視域だけではなく赤外域の千数百 nm にまで至っています。つまり、およそ 780 ~ 千数百 nm の波長の赤外域の光も網膜に達しているのですが、人間の眼はこの赤外域の光に対して全く「明るさ」を感じることがないのです。これは何故なのでしょうか?
自然界には様々な「色」の物体がありますが、その「色」の原因となる波長毎の反射率特性(分光反射率特性)を、可視域だけでなく赤外域にまでわたって調べてみると、面白い傾向があります。

物体の「色」毎に可視域の分光反射率特性が異なっており、その特性は様々な凹凸形状をとっていることがわかります。しかしその一方で赤外域の分光反射率特性にはあまり凹凸が無く単純な形状であることがわかります。例外はありますが、一般に多くの自然界の動植物の分光反射率特性は、可視域でその色に応じた特徴的な凹凸があり、赤外域ではあまり凹凸がなく単純な特性であることが多いようです。

人類は太古の時代よりこの地球環境に適応し植物の実や動物を食料として種を保ってきたのですが、地上で生きていくためには、例えば植物の果実が熟して “ 食べごろ ” であることを知らなければなりません。果実が熟すことは主に「色」や形で判断するのは我々自身の生活体験からもよく分かります。青い果実から徐々に色が変化し、赤く熟した果実になるということは、その果実の可視域の分光反射率特性が変化していくということです。一方赤外域の分光反射率特性は果実の熟し加減にはあまり関係しないようです。
人間が生を保つ為の情報量が圧倒的に可視域に集中しており、 “ 見えてもあまり役に立たない ” 赤外は見えなくてもあまり支障が無い、ということがわかります。このように、長波長側の可視限界は人類の地上環境への適応の結果ということがおおいに考えられます。
このように考えると、環境への適合という手段で我々生物は特性を最適化 してきたのだなぁと改めて感じます。
「器械の眼」の「可視域」
人間の眼の「可視域」は上述のような事情でおよそ 380 ~ 780 nm の範囲になっていると考えられますが、カメラなどの「器械の眼」の感度はどうなっているのでしょうか?
マシンビジョンでは CCD カメラや C - MOS カメラなどと呼ばれるカメラがよく使用されます。これらのカメラの撮像素子にはほとんどがシリコン ( Si ) 系の半導体受光素子≪※3≫が使われているようです。半導体受光素子は、 p 型半導体と n 型半導体の接合部で光を電気に変換しているのですが、この光電変換の感度特性は半導体素材によって決まります。シリコン半導体受光素子の場合、およそ 200 nm 近辺から 1100 nm 近辺の波長範囲に感度をもち、人間の可視域をカバーしていますので、カメラの撮像素子を初めとして多種多様な用途の「器械の眼」として最も多く使用されています。
また人間の可視域以外の波長範囲に対しては、シリコン ( Si ) だけではカバーしきれないので、対象の波長域に応じて各種の受光素子が使い分けられています。
紫外域についてはシリコン ( Si ) 以外にも、ガリウム・リン ( GaP ) 、ガリウム・ヒ素・リン ( GaAsP ) などが使われますし、赤外域については、インジウム・ガリウム・ヒ素 ( InGaAs ) 、インジウム・アンチモン ( InSb ) 、水銀・カドミウム・テルル ( HgCdTe ) などが使われます。≪※4≫

このように紫外から赤外に至るまで、様々な種類の受光素子が開発されていますが、その器械が何をする為の器械であるか、器械の目的によって「器械の眼」には、どの受光素子が適するのかが決まります。
このとき、各種の受光素子をそのまま搭載するのではなく、多くの場合はその器械の目的に応じて最適の分光応答度に調整します。例えば、人間の眼で見た明るさを評価したい場合には、シリコン受光素子に適切な分光透過率特性の光学フィルタをかけてトータルの分光応答度が人間の平均的な視覚特性(標準分光視感効率 V ( λ ) )の形状になるようにします。≪※5≫
注釈
≪※1≫
以前は、「標準比視感度」という用語が使用されていましたが、最近は学会等を中心に「標準分光視感効率」という用語が使われるようになっています。
≪※2≫
| 【 ISO 】 | 360 ~ 830 nm ( TC 2 - 35 PHOTOMETRY draft ) |
|---|---|
| 【法律(計量法)】 | 360 ~ 830 nm (計量法第 19 章照度計第一節検定第 794 条 |
| 【照明学会】 | 360 nm ないし 400 nm から 760 nm ないし 830 nm まで (測色では 380 nm から 780 nm とするのが慣例) |
| 【 JIS Z 8120 光学用語 】 | 一般に可視放射の波長範囲の 短波長限界は 360 ~ 400 nm 、 長波長限界は 760 ~ 830 nm にあると考えてよい |
≪※3≫
光を電気信号に変換する半導体電子部品のこと。光が半導体受光素子に当ると、 “ 内部光電効果 ” によって、入射光の強弱に応じて電流や電圧の出力が変化します。フォトダイオード、フォトトランジスタ、太陽電池、 CCD 撮像素子、 C - MOS 撮像素子などの半導体受光素子がよく使用されます。ここでは触れていませんが、更に半導体以外にも、 “ 外部光電効果 ” を利用した光電子増倍管などの光電管類もあります。
≪※4≫
この図では、各種受光素子が感度を有する波長帯を示していますが、これらの波長帯の中でも感度の高低分布があります。
≪※5≫
器械の眼に具備すべき分光応答度特性の実現方法として、受光素子(センサー)に光学フィルタをかける方法(フィルタ方式)で説明しましたが、別の実現方法としては「分光方式」があります。
「分光方式」は、評価対象の光を波長成分ごと(例えば 10 nm ピッチ)に分けて測定し、その測定値に目的とする作用関数を数値で掛け算し合算する方法です。本連載の第1回の注釈≪※6≫のような計算です。
≪※6≫
第2回に、波長が短い光ほど光子エネルギーが大きいことをお話しました。波長の短い紫外領域の中でも波長の短い UV - C の領域は、生体に対して大きな損傷を与えてしまいますが、これを利用してバクテリア、ウィルス、カビなどの菌種を殺すための光源(放射源)が殺菌灯です。図に示すような波長 260 nm 近辺の紫外放射は、細菌やウィルスの核酸( DNA )を破壊して殺菌する効果が大きいと言われています。主に、医療用(手術室や、医用器具の殺菌など)、食品用(食材や調理器具の殺菌など)、化粧品工場、製薬工場などでよく使用されているようです。また、魚類用水槽にもよく使用され、飼育水の殺菌による魚病防止、飼育水の透明度維持(藻の抑制)や臭い防止、食べ残しの餌の腐敗防止などに効果を発揮しているようです。
≪※7≫
JIS Z 8811 - 1968 「殺菌紫外線の測定方法」に規定された殺菌効果特性
≪※8≫
レンズやミラーなどの光学系を介して対象の光を評価する場合は、当然ながらその光学系の特性(分光透過率、分光反射率など)も考慮に入れて器械の眼の特性を設定してやる必要があります。特に、紫外域や赤外域の場合は光学系(光学材料)の透過・反射特性が問題になることが多いので注意が必要です。
光と色の話 第一部

第3回 可視域とは?
はじめに
広義の「光」は、紫外、可視、赤外に分けられますが、紫外と可視、あるいは、可視と赤外の境界はどこにあり、何故その波長帯が境界になっているのでしょうか?
人間の眼の「可視域」
「可視」とはその文字が示す通り、「みることができる」という意味ですが、人間の眼の明るさを感じる感度というのは、光の波長に対して一定ではありません。可視域のほぼ中央部(波長 555 nm )に感度のピークがあり、短波長側あるいは長波長側に向かって徐々に感度が低下して行き、ついには感度ゼロ、すなわち光のエネルギーはあっても全く明るさを感じなくなります。
この特性は個人個人によっても微妙に異なっており、また同一人物でも心理的要因で変動したり、また年齢によって変化していくことも知られています。

しかし、「明るさ」を客観的・定量的に評価する必要性があるため、人類の平均的な視覚特性を代表するものとして「標準分光視感効率」≪※1≫ が定められました。図ではおよそ 720 nm 以上、あるいは、およそ 420 nm 以下では感度(応答度)がゼロになっているように見えますが、完全にゼロになっている訳ではありません。この形状からも分かりますように、紫外と可視、あるいは可視と赤外の境界波長は明確に何 nm と区切られる訳ではなく、「可視域」の境界は曖昧で、各種規格や学会、団体等でもその規定は一致している訳ではありません。≪※2≫
では、この可視域の両端が、これらの波長帯に存在するのは何故なのでしょうか? 短波長側(紫外と可視の境界)と長波長側(可視と赤外の境界)について、それぞれ考えてみましょう。
紫外と可視の境界(短波長側)
光、すなわち電磁波は波長が短くなるほどエネルギーが強くなり、生体への悪影響も大きくなっていきますが、可視から紫外にわたる波長領域でも、特に人間の眼に与える影響が問題になってきます。光に対して人間の眼の最も敏感な部分は眼底にある網膜(視細胞)なのですが、「光」に敏感な為に紫外などの光子エネルギーの大きい短波長成分に対しては特に損傷を受けやすいことになります。

それを避けるために網膜に至るまでの角膜、水晶体、硝子体などの組織が光子エネルギーの強い紫外成分を吸収し、網膜に紫外成分が直接到達しないようになっています。つまり、角膜や水晶体や硝子体が短波長カットフィルタの役割を果たしているのです。当然多量の紫外照射を受けると角膜や水晶体も損傷を受けてしまいます。このように、短波長側の可視限界は網膜(視細胞)保護のためであると言えます。
可視と赤外の境界(長波長側)
可視域よりも短い波長の光は、上述のように角膜や水晶体、硝子体等の組織によってブロックされて網膜(視細胞)に到達できないため、人間の眼は「明るさ」を感じることができないのですが、可視域よりも長い波長の光についてはどうなのでしょうか? 網膜に到達する光の波長は、実は可視域だけではなく赤外域の千数百 nm にまで至っています。つまり、およそ 780 ~ 千数百 nm の波長の赤外域の光も網膜に達しているのですが、人間の眼はこの赤外域の光に対して全く「明るさ」を感じることがないのです。これは何故なのでしょうか?
自然界には様々な「色」の物体がありますが、その「色」の原因となる波長毎の反射率特性(分光反射率特性)を、可視域だけでなく赤外域にまでわたって調べてみると、面白い傾向があります。

物体の「色」毎に可視域の分光反射率特性が異なっており、その特性は様々な凹凸形状をとっていることがわかります。しかしその一方で赤外域の分光反射率特性にはあまり凹凸が無く単純な形状であることがわかります。例外はありますが、一般に多くの自然界の動植物の分光反射率特性は、可視域でその色に応じた特徴的な凹凸があり、赤外域ではあまり凹凸がなく単純な特性であることが多いようです。

人類は太古の時代よりこの地球環境に適応し植物の実や動物を食料として種を保ってきたのですが、地上で生きていくためには、例えば植物の果実が熟して “ 食べごろ ” であることを知らなければなりません。果実が熟すことは主に「色」や形で判断するのは我々自身の生活体験からもよく分かります。青い果実から徐々に色が変化し、赤く熟した果実になるということは、その果実の可視域の分光反射率特性が変化していくということです。一方赤外域の分光反射率特性は果実の熟し加減にはあまり関係しないようです。
人間が生を保つ為の情報量が圧倒的に可視域に集中しており、 “ 見えてもあまり役に立たない ” 赤外は見えなくてもあまり支障が無い、ということがわかります。このように、長波長側の可視限界は人類の地上環境への適応の結果ということがおおいに考えられます。
このように考えると、環境への適合という手段で我々生物は特性を最適化 してきたのだなぁと改めて感じます。
「器械の眼」の「可視域」
人間の眼の「可視域」は上述のような事情でおよそ 380 ~ 780 nm の範囲になっていると考えられますが、カメラなどの「器械の眼」の感度はどうなっているのでしょうか?
マシンビジョンでは CCD カメラや C - MOS カメラなどと呼ばれるカメラがよく使用されます。これらのカメラの撮像素子にはほとんどがシリコン ( Si ) 系の半導体受光素子≪※3≫が使われているようです。半導体受光素子は、 p 型半導体と n 型半導体の接合部で光を電気に変換しているのですが、この光電変換の感度特性は半導体素材によって決まります。シリコン半導体受光素子の場合、およそ 200 nm 近辺から 1100 nm 近辺の波長範囲に感度をもち、人間の可視域をカバーしていますので、カメラの撮像素子を初めとして多種多様な用途の「器械の眼」として最も多く使用されています。
また人間の可視域以外の波長範囲に対しては、シリコン ( Si ) だけではカバーしきれないので、対象の波長域に応じて各種の受光素子が使い分けられています。
紫外域についてはシリコン ( Si ) 以外にも、ガリウム・リン ( GaP ) 、ガリウム・ヒ素・リン ( GaAsP ) などが使われますし、赤外域については、インジウム・ガリウム・ヒ素 ( InGaAs ) 、インジウム・アンチモン ( InSb ) 、水銀・カドミウム・テルル ( HgCdTe ) などが使われます。≪※4≫

このように紫外から赤外に至るまで、様々な種類の受光素子が開発されていますが、その器械が何をする為の器械であるか、器械の目的によって「器械の眼」には、どの受光素子が適するのかが決まります。
このとき、各種の受光素子をそのまま搭載するのではなく、多くの場合はその器械の目的に応じて最適の分光応答度に調整します。例えば、人間の眼で見た明るさを評価したい場合には、シリコン受光素子に適切な分光透過率特性の光学フィルタをかけてトータルの分光応答度が人間の平均的な視覚特性(標準分光視感効率 V ( λ ) )の形状になるようにします。≪※5≫
注釈
≪※1≫
以前は、「標準比視感度」という用語が使用されていましたが、最近は学会等を中心に「標準分光視感効率」という用語が使われるようになっています。
≪※2≫
| 【 ISO 】 | 360 ~ 830 nm ( TC 2 - 35 PHOTOMETRY draft ) |
|---|---|
| 【法律(計量法)】 | 360 ~ 830 nm (計量法第 19 章照度計第一節検定第 794 条 |
| 【照明学会】 | 360 nm ないし 400 nm から 760 nm ないし 830 nm まで (測色では 380 nm から 780 nm とするのが慣例) |
| 【 JIS Z 8120 光学用語 】 | 一般に可視放射の波長範囲の 短波長限界は 360 ~ 400 nm 、 長波長限界は 760 ~ 830 nm にあると考えてよい |
≪※3≫
光を電気信号に変換する半導体電子部品のこと。光が半導体受光素子に当ると、 “ 内部光電効果 ” によって、入射光の強弱に応じて電流や電圧の出力が変化します。フォトダイオード、フォトトランジスタ、太陽電池、 CCD 撮像素子、 C - MOS 撮像素子などの半導体受光素子がよく使用されます。ここでは触れていませんが、更に半導体以外にも、 “ 外部光電効果 ” を利用した光電子増倍管などの光電管類もあります。
≪※4≫
この図では、各種受光素子が感度を有する波長帯を示していますが、これらの波長帯の中でも感度の高低分布があります。
≪※5≫
器械の眼に具備すべき分光応答度特性の実現方法として、受光素子(センサー)に光学フィルタをかける方法(フィルタ方式)で説明しましたが、別の実現方法としては「分光方式」があります。
「分光方式」は、評価対象の光を波長成分ごと(例えば 10 nm ピッチ)に分けて測定し、その測定値に目的とする作用関数を数値で掛け算し合算する方法です。本連載の第1回の注釈≪※6≫のような計算です。
≪※6≫
第2回に、波長が短い光ほど光子エネルギーが大きいことをお話しました。波長の短い紫外領域の中でも波長の短い UV - C の領域は、生体に対して大きな損傷を与えてしまいますが、これを利用してバクテリア、ウィルス、カビなどの菌種を殺すための光源(放射源)が殺菌灯です。図に示すような波長 260 nm 近辺の紫外放射は、細菌やウィルスの核酸( DNA )を破壊して殺菌する効果が大きいと言われています。主に、医療用(手術室や、医用器具の殺菌など)、食品用(食材や調理器具の殺菌など)、化粧品工場、製薬工場などでよく使用されているようです。また、魚類用水槽にもよく使用され、飼育水の殺菌による魚病防止、飼育水の透明度維持(藻の抑制)や臭い防止、食べ残しの餌の腐敗防止などに効果を発揮しているようです。
≪※7≫
JIS Z 8811 - 1968 「殺菌紫外線の測定方法」に規定された殺菌効果特性
≪※8≫
レンズやミラーなどの光学系を介して対象の光を評価する場合は、当然ながらその光学系の特性(分光透過率、分光反射率など)も考慮に入れて器械の眼の特性を設定してやる必要があります。特に、紫外域や赤外域の場合は光学系(光学材料)の透過・反射特性が問題になることが多いので注意が必要です。