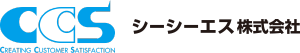光と色の話 第二部

第13回 UVメータと分光的測定誤差
測光・測色機器の測定誤差には大別して、測定器の仕組み・構造などの所謂ハードウェアに起因するものと、測定者による使い方に起因するものに分けられます。測定器取り扱いの不注意や理解不足による誤差発生については、本連載の第6回、第7回で照度計や輝度計の場合の例を具体的にお話ししました。
測定器のハードウェアに起因する誤差にも様々な要因がありますが、今回はその内の代表的なものとして分光的測定誤差を採り上げてみたいと思います。分光的測定誤差については、既に本連載 (第10回)でも、可視域でのLED測光の場合について「異色測光誤差」≪※1≫という表現で具体的に説明致しましたが、今回は特に、紫外・赤外域での放射測定において問題化し易い分光的測定誤差について、測定値の単位表記との関連も含めて論じてみたいと思います。
放射量(物理エネルギー)測定 と“実効”放射量測定
光(放射)を測定する対象は大きく分けて、その光自身が有する純粋な物理的エネルギーを評価する測定と、(その光が及ぼす)或る特定の作用効果を評価する測定に分けることが出来ます。前者は、試料光が持つ分光分布をどの波長に対しても均等な重みづけ(フラットな分光的評価関数)で評価して、その光自体の物理エネルギー量である放射量(放射束、放射強度、放射照度、放射輝度等)を測定するものです。また後者は、試料光を受ける側にどれだけの作用・効果を及ぼすかということを、その作用・効果に対応した波長毎の重み付け(分光的作用関数)で、謂わば“実効”放射量を測定するもので、例えば可視域においては人間の視覚に及ぼす刺激量を測定する測光(光束、光度、照度、輝度等の測定)や測色(3刺激値X、Y、Zの測定)等が代表的な例です。
紫外や赤外の測定においても同様に、試料光自体の物理エネルギー量の測定(放射量測定)の場合と、その放射を受ける側の影響・効果を測定・評価する測定(“実効”放射量測定)に分けられます。紫外・赤外域において試料光が及ぼす作用効果にも様々なものがあり、例えば紫外域における(人間に対する)有害紫外放射、殺菌効果作用、樹脂の紫外線硬化作用、赤外域における温熱効果作用、白内障・・・・等、様々な作用効果が知られています。人間に対する有害紫外放射にも、人体の部位(眼や皮膚など)によって、その作用・効果の分光的作用関数は当然異なります。
測定器の分光応答度 と 分光的測定誤差
測定器の分光的評価関数である分光応答度は、放射量測定の場合には分光的にフラットであること、“実効”放射量測定の場合にはその効果に対する分光的作用関数に合致していること、が必要になります。これらの分光応答度を実現する方法としては、分光方式とフィルタ方式があります。
分光方式の測光機器の場合は、試料光の分光分布を波長成分毎に細かく分割して測定したデータに対して数値設定された分光的評価関数(放射量測定の場合には定数、“実効”放射量測定の場合には分光的作用関数)を用いて測定値を算出しますので、原理的に分光的測定誤差は非常に小さく抑えられます。また分光方式は、複数種類の分光的評価関数をデータとして持っておくことができますので、放射量測定にも“実効”放射量測定にも容易に対応できます。
フィルタ方式は、使用する受光素子に光学フィルタを掛けて目的の分光的評価関数に合わせた分光応答度を作り出すものです。受光素子の分光応答度と光学フィルタの分光透過率の組合せで出来上がる受光センサの実際の分光応答度は、目的とする分光的評価関数に対して、対象とする全波長域に亘って精度良く一致させることはなかなか困難で、(第10回の標準分光視感効率
V( λ )に対する解説図のように)差異のある波長域がどうしても残ってしまいます。
このような特性のフィルタ方式の受光センサで測定した場合、試料光の分光分布に依存して誤差の発生の仕方が変動する現象が生じます。分光応答度の差異が大きい波長域に、試料光の分光分布の高い部分が重なると、どうしても測定誤差が大きく出てしまいます。つまり、試料光の分光分布に依存して誤差の発生量が変動するということになってしまいます。これが分光的測定誤差です。
このように、分光的測定誤差の観点からは、測定原理的に分光方式の方が望ましいのですが、分光方式の測定器はどうしても高価になり勝ちで取り扱いにも注意が必要なため、安価で取り扱いやすいフィルタ方式が多方面で使われています。
分光的測定誤差が生じ易いフィルタ方式の場合でも、試料光の分光分布が既知の場合等は、測定器の校正光源の分光分布との関係から予め補正係数(CCF:color compensating factor)を求めておいて、ナマの測定値にその補正係数を乗じることによって、誤差を補正することは可能です。しかし、試料光の分光分布が不明な場合には補正処理ができませんし、分光分布が変動する場合には、全てに対して補正係数を準備しておくことは現実問題としてなかなか対応が難しいという問題があります。
このような分光的測定誤差は、別に可視域での測定に特有な訳ではなく、当然の事ながら紫外域や赤外域での測定でも同じことが起こり、測定単位表示との関係もあって、より問題化し易いと言えます。以下にUVメータの場合について具体的に考えてみます。
UVメータの分光応答度特性
一口にUVメータと言っても、測定対象とする紫外波長域も様々であり、機種によって受光センサの分光応答度も異なっています≪※2≫。 一般用のUVメータ(紫外線強度計)として供給されているもの(特に小型のハンディタイプのもの)は、フィルタ方式のものが多く、センサの分光応答度は、例えば右図のように、測定対象波長範囲全体に亘ってフラットになっている訳ではありません≪※3≫。 このような分光応答度のセンサで測定した結果が、波長毎の重みづけが異なっているのに、物理エネルギー量としての放射量測定値(ワット [ W ] 単位系)で表示されています。 この測定値表示の意味を理解せずに、表示された測定値をそのまま受け取ってしまうと、大きな測定誤差に繋がってしまうことがあるので注意が必要です。この測定値の解釈には、測定器の校正条件が大きく関係しています。

放射量測定値の校正
測定器の校正は、校正に適した分光分布を持つ特定種類の管理された標準光源を規定された条件で点灯させ、校正光源と測定器を所定の位置関係に配置した条件の下で行われます。この条件下においては、放射量値が、校正値として例えばUV放射照度計の場合は [ W/m2 ] 単位の放射照度値で値付けされていますので、測定器をその条件下で動作させて校正値の表示となるように測定器を調整して校正する訳です。
従って、校正光源と同等の分光分布を持つ試料光の場合に限り、測定結果も物理的エネルギーとしての放射量の絶対値として受け取ることができます。しかし、校正光源と異なる分光分布の試料光の場合には、当然分光的測定誤差が生じてしまいます。
なお、試料光の分光分布が校正光源の分光分布と異なっていても、試料光の分光分布が既知である場合には、(理論的には上述しました様に手間はかかりますが)補正係数により分光的測定誤差を補正することは可能です。また、試料光の分光分布が固定されている条件の場合には、分光的測定誤差の発生も一定比率になりますので、相対値としての比較測定はできると言えます。
可視域での測光の場合、フィルタ方式の測定器の分光応答度は、理論的分光評価関数、例えば標準分光視感効率 V( λ ) に対して、完全には一致しきれずに差異が残っている波長帯が存在するのですが、全体的には概ね近似しています。これに対して、UVメータの場合、物理エネルギーとしての放射量測定の為には理論的にフラットな分光応答度であるべきところが、実際には上図の様なかけ離れた分光応答度特性の形状である場合が殆どです。従って、可視域での測光の場合に比べて、分光的測定誤差の出方は格段に大きくなってしまいます。つまり、試料光の分光分布が不明確な場合、フィルタ方式のUVメータでの測定値は絶対値としては大きな分光的測定誤差の発生リスクを孕んでいると言えます。
放射量の単位 と“実効”放射量の単位
可視域の測光の場合には、分光的評価関数(標準分光視感効率 V( λ ) 等)に対応した単位系も明確に規定され、それに対応する測光量の単位系( lm、cd、lx 等)もきっちりと整備されています(第一部第7回≪※2≫)。標準分光視感効率 V( λ )は人間の視覚の代表特性で、作用関数としては人間生活に極めて密着したものであるため、他の作用関数に対して圧倒的に重要で、多方面に亘って盛んに使用されており、測定器の使用者側にもかなり周知されています。放射量([ W ]単位系)と “実効”放射量である測光量([ lm ] 単位系)が混同されることは殆ど無く、概ね適正に使い分けられている場合が多いと考えられます。
それに対して、紫外や赤外でもその目的によってはそれに応じた分光的作用関数が規定されてはいますが、その用途は極めて限定的・専門的であって、可視域の標準分光視感効率 V( λ ) のように、非常に広い範囲の人間生活に亘って一般的に高頻度に使用されている訳ではないのが実情です。そのような背景もあって、紫外域や赤外域の測定においては、特別の場合≪※4≫を除いて、それぞれの作用・効果毎に個別の単位系が整備されている訳ではありません。
“実効”放射量(例えば紫外放射による日焼けへの影響、等)を評価したい場合でも、その影響・効果に対する分光的作用関数をあまり意識せずに汎用のフィルタ方式のUVメータを使用して測定している場合もあるようです。この場合の測定値は(かなりの分光的測定誤差を含んでいる可能性はあるものの) [ W ] 単位系で放射量値が表示されており、“実効”放射量値ではないのですが、表示単位上は区別も無いため、つい“実効”放射量を測定しているものと思い込んでいる場合もあると思われます。
あるいはまた、一般のUVメータの測定値は [ W ] 単位系で表示されますので、使用者側の意識として、特定の作用関数での測定(“実効”放射量の測定)という概念が抜け落ちてしまい、試料光の分光分布に関わらず、紫外放射自体の強度(すなわち放射量)の絶対値を測定していると誤解して使っている場合が結構多いのが実情ではないでしょうか。
従って、フィルタ方式の測定器によって“実効”放射量を評価したい場合には、便宜上、光源の種類を特定(相対分光分布を固定)した条件の下で、目的とする分光的作用関数(分光応答度)で試料光の物理エネルギーとしての放射量( [ W ] 単位系)を評価・測定するということが行われています。つまり、特定の同一分光分布の光源の下で、という前提での相対比較評価であって、試料光の分光分布が異なれば同じ土俵では適切な定量的比較が困難になってしまうことになります。
以上の様な事情から、フィルタ方式のUVメータを使用する場合は、測定目的の作用関数と測定器の分光応答度、および校正光源について、確認しておくことが非常に重要です。
つまり、その測定器を校正した光源(放射源)と同等の相対分光分布の試料光を測定した時のみ、分光的測定誤差が概ね無視しうる測定結果が得られることになります。これらの両者が異なっていれば、分光的測定誤差が大きく生じる可能性があり、正確な測定はできません。なお、試料光の分光分布が変動しない、という前提条件が有る場合には、分光的測定誤差の発生も一定比率になりますので、絶対値測定ではなく、相対比較測定に使用することは可能です。
以上の説明は、紫外域での測定(UVメータ)を例に説明致しましたが、赤外域での測定(IRメータ)でも、原理的には全く同様なことが言えます。
註釈
≪※1≫ “異色”測光誤差
可視域を対象とする測光・測色では、分光的測定誤差のことを、試料光の分光分布の違いが試料光の“色味”の違いに直結するため「異色測光誤差」と表現することもあります。紫外・赤外においても同様の分光的測定誤差を便宜的に異色測光誤差と称する場合もあるようですが、紫外・赤外では「色」という概念は適用できないので、“異色”測光誤差と言うのは適切な表現とは言えず、その上位概念である分光的測定誤差と言うべきでしょう。
≪※2≫ 紫外域の波長域細分化
紫外域は凡そ 10~380 nm の波長範囲を指しますが、一口に紫外放射と言っても、生ずる作用効果はその波長によって非常に多種多様です。このような事情もあって紫外域は一般に右図の様に細分化して議論されています。市販のフィルタ式UVメータの殆どは近紫外域が測定対象であり、実際にはUV—A用、UV—B用 、UV—C用という様に更に細分化されています。

≪※3≫ UVメータの分光応答度
UVメータに用いられる受光素子はシリコン系の受光素子が一般的ですが、シリコン系の受光素子自体の分光応答度は一般に可視から近赤外にかけての応答度が高く、可視から紫外にかけての短波長側は波長が短くなるほど応答度が低くなっており、近紫外域をどうにかやっとカバーしているような特性になっています。従って、UVメータの受光素子としては、主応答度のある可視~近赤外域をカットして、応答度の低い紫外域を使うということになります。放射測定のために紫外域での分光応答度をフラットにしようとすれば、まだ何とか残っている応答度を更にフィルタで削ることになってしまうため、測定器としての検出能力が更に低下してしまうことになってしまいます。このような事情から、放射量測定用と謳ったフィルタ方式のUVメータの分光応答度でも分光応答度はフラットではないものが殆どであるのが実情です。
≪※4≫ 紫外域での“実効”放射量の単位表記
紫外域での“実効”放射量の単位表記殺菌紫外や有害紫外放射などの特殊な紫外測定については、以下のように、それらの“実効”放射量を明確に示す特別の単位表記が規定されています。
例えば殺菌効果に対しては、右上図のような(等放射パワーに対する)波長毎の殺菌効果作用関数が規定されており、殺菌灯の殺菌力はこれによって測定することになります(第一部第3回参照)。
殺菌紫外の“実効”放射束の単位として“殺菌ワット G−watt”という単位表記が規定されており、例えば殺菌紫外放射照度は [ G−W/m2 ] という単位表記になります。 (JIS Z 8811—1968殺菌紫外線の測定方法)
また、有害紫外放射の測定については、右下図のような(等放射パワーに対する)波長毎の相対分光有害作用関数が規定されており、これに基づく実効的な有害放射束は ”有害ワット W(haz) ” という単位系の表示が規定されています。(”haz” は ”hazard” の意味)
例えば有害紫外放射照度は[ W/m2 (haz) ] という単位表記になります。(JIS Z 8812—1987 有害紫外放射の測定方法)


光と色の話 第二部

第13回 UVメータと分光的測定誤差
測光・測色機器の測定誤差には大別して、測定器の仕組み・構造などの所謂ハードウェアに起因するものと、測定者による使い方に起因するものに分けられます。測定器取り扱いの不注意や理解不足による誤差発生については、本連載の第6回、第7回で照度計や輝度計の場合の例を具体的にお話ししました。
測定器のハードウェアに起因する誤差にも様々な要因がありますが、今回はその内の代表的なものとして分光的測定誤差を採り上げてみたいと思います。分光的測定誤差については、既に本連載 (第10回)でも、可視域でのLED測光の場合について「異色測光誤差」≪※1≫という表現で具体的に説明致しましたが、今回は特に、紫外・赤外域での放射測定において問題化し易い分光的測定誤差について、測定値の単位表記との関連も含めて論じてみたいと思います。
放射量(物理エネルギー)測定 と“実効”放射量測定
光(放射)を測定する対象は大きく分けて、その光自身が有する純粋な物理的エネルギーを評価する測定と、(その光が及ぼす)或る特定の作用効果を評価する測定に分けることが出来ます。前者は、試料光が持つ分光分布をどの波長に対しても均等な重みづけ(フラットな分光的評価関数)で評価して、その光自体の物理エネルギー量である放射量(放射束、放射強度、放射照度、放射輝度等)を測定するものです。また後者は、試料光を受ける側にどれだけの作用・効果を及ぼすかということを、その作用・効果に対応した波長毎の重み付け(分光的作用関数)で、謂わば“実効”放射量を測定するもので、例えば可視域においては人間の視覚に及ぼす刺激量を測定する測光(光束、光度、照度、輝度等の測定)や測色(3刺激値X、Y、Zの測定)等が代表的な例です。
紫外や赤外の測定においても同様に、試料光自体の物理エネルギー量の測定(放射量測定)の場合と、その放射を受ける側の影響・効果を測定・評価する測定(“実効”放射量測定)に分けられます。紫外・赤外域において試料光が及ぼす作用効果にも様々なものがあり、例えば紫外域における(人間に対する)有害紫外放射、殺菌効果作用、樹脂の紫外線硬化作用、赤外域における温熱効果作用、白内障・・・・等、様々な作用効果が知られています。人間に対する有害紫外放射にも、人体の部位(眼や皮膚など)によって、その作用・効果の分光的作用関数は当然異なります。
測定器の分光応答度 と 分光的測定誤差
測定器の分光的評価関数である分光応答度は、放射量測定の場合には分光的にフラットであること、“実効”放射量測定の場合にはその効果に対する分光的作用関数に合致していること、が必要になります。これらの分光応答度を実現する方法としては、分光方式とフィルタ方式があります。
分光方式の測光機器の場合は、試料光の分光分布を波長成分毎に細かく分割して測定したデータに対して数値設定された分光的評価関数(放射量測定の場合には定数、“実効”放射量測定の場合には分光的作用関数)を用いて測定値を算出しますので、原理的に分光的測定誤差は非常に小さく抑えられます。また分光方式は、複数種類の分光的評価関数をデータとして持っておくことができますので、放射量測定にも“実効”放射量測定にも容易に対応できます。
フィルタ方式は、使用する受光素子に光学フィルタを掛けて目的の分光的評価関数に合わせた分光応答度を作り出すものです。受光素子の分光応答度と光学フィルタの分光透過率の組合せで出来上がる受光センサの実際の分光応答度は、目的とする分光的評価関数に対して、対象とする全波長域に亘って精度良く一致させることはなかなか困難で、(第10回の標準分光視感効率
V( λ )に対する解説図のように)差異のある波長域がどうしても残ってしまいます。
このような特性のフィルタ方式の受光センサで測定した場合、試料光の分光分布に依存して誤差の発生の仕方が変動する現象が生じます。分光応答度の差異が大きい波長域に、試料光の分光分布の高い部分が重なると、どうしても測定誤差が大きく出てしまいます。つまり、試料光の分光分布に依存して誤差の発生量が変動するということになってしまいます。これが分光的測定誤差です。
このように、分光的測定誤差の観点からは、測定原理的に分光方式の方が望ましいのですが、分光方式の測定器はどうしても高価になり勝ちで取り扱いにも注意が必要なため、安価で取り扱いやすいフィルタ方式が多方面で使われています。
分光的測定誤差が生じ易いフィルタ方式の場合でも、試料光の分光分布が既知の場合等は、測定器の校正光源の分光分布との関係から予め補正係数(CCF:color compensating factor)を求めておいて、ナマの測定値にその補正係数を乗じることによって、誤差を補正することは可能です。しかし、試料光の分光分布が不明な場合には補正処理ができませんし、分光分布が変動する場合には、全てに対して補正係数を準備しておくことは現実問題としてなかなか対応が難しいという問題があります。
このような分光的測定誤差は、別に可視域での測定に特有な訳ではなく、当然の事ながら紫外域や赤外域での測定でも同じことが起こり、測定単位表示との関係もあって、より問題化し易いと言えます。以下にUVメータの場合について具体的に考えてみます。
UVメータの分光応答度特性
一口にUVメータと言っても、測定対象とする紫外波長域も様々であり、機種によって受光センサの分光応答度も異なっています≪※2≫。 一般用のUVメータ(紫外線強度計)として供給されているもの(特に小型のハンディタイプのもの)は、フィルタ方式のものが多く、センサの分光応答度は、例えば右図のように、測定対象波長範囲全体に亘ってフラットになっている訳ではありません≪※3≫。 このような分光応答度のセンサで測定した結果が、波長毎の重みづけが異なっているのに、物理エネルギー量としての放射量測定値(ワット [ W ] 単位系)で表示されています。 この測定値表示の意味を理解せずに、表示された測定値をそのまま受け取ってしまうと、大きな測定誤差に繋がってしまうことがあるので注意が必要です。この測定値の解釈には、測定器の校正条件が大きく関係しています。

放射量測定値の校正
測定器の校正は、校正に適した分光分布を持つ特定種類の管理された標準光源を規定された条件で点灯させ、校正光源と測定器を所定の位置関係に配置した条件の下で行われます。この条件下においては、放射量値が、校正値として例えばUV放射照度計の場合は [ W/m2 ] 単位の放射照度値で値付けされていますので、測定器をその条件下で動作させて校正値の表示となるように測定器を調整して校正する訳です。
従って、校正光源と同等の分光分布を持つ試料光の場合に限り、測定結果も物理的エネルギーとしての放射量の絶対値として受け取ることができます。しかし、校正光源と異なる分光分布の試料光の場合には、当然分光的測定誤差が生じてしまいます。
なお、試料光の分光分布が校正光源の分光分布と異なっていても、試料光の分光分布が既知である場合には、(理論的には上述しました様に手間はかかりますが)補正係数により分光的測定誤差を補正することは可能です。また、試料光の分光分布が固定されている条件の場合には、分光的測定誤差の発生も一定比率になりますので、相対値としての比較測定はできると言えます。
可視域での測光の場合、フィルタ方式の測定器の分光応答度は、理論的分光評価関数、例えば標準分光視感効率 V( λ ) に対して、完全には一致しきれずに差異が残っている波長帯が存在するのですが、全体的には概ね近似しています。これに対して、UVメータの場合、物理エネルギーとしての放射量測定の為には理論的にフラットな分光応答度であるべきところが、実際には上図の様なかけ離れた分光応答度特性の形状である場合が殆どです。従って、可視域での測光の場合に比べて、分光的測定誤差の出方は格段に大きくなってしまいます。つまり、試料光の分光分布が不明確な場合、フィルタ方式のUVメータでの測定値は絶対値としては大きな分光的測定誤差の発生リスクを孕んでいると言えます。
放射量の単位 と“実効”放射量の単位
可視域の測光の場合には、分光的評価関数(標準分光視感効率 V( λ ) 等)に対応した単位系も明確に規定され、それに対応する測光量の単位系( lm、cd、lx 等)もきっちりと整備されています(第一部第7回≪※2≫)。標準分光視感効率 V( λ )は人間の視覚の代表特性で、作用関数としては人間生活に極めて密着したものであるため、他の作用関数に対して圧倒的に重要で、多方面に亘って盛んに使用されており、測定器の使用者側にもかなり周知されています。放射量([ W ]単位系)と “実効”放射量である測光量([ lm ] 単位系)が混同されることは殆ど無く、概ね適正に使い分けられている場合が多いと考えられます。
それに対して、紫外や赤外でもその目的によってはそれに応じた分光的作用関数が規定されてはいますが、その用途は極めて限定的・専門的であって、可視域の標準分光視感効率 V( λ ) のように、非常に広い範囲の人間生活に亘って一般的に高頻度に使用されている訳ではないのが実情です。そのような背景もあって、紫外域や赤外域の測定においては、特別の場合≪※4≫を除いて、それぞれの作用・効果毎に個別の単位系が整備されている訳ではありません。
“実効”放射量(例えば紫外放射による日焼けへの影響、等)を評価したい場合でも、その影響・効果に対する分光的作用関数をあまり意識せずに汎用のフィルタ方式のUVメータを使用して測定している場合もあるようです。この場合の測定値は(かなりの分光的測定誤差を含んでいる可能性はあるものの) [ W ] 単位系で放射量値が表示されており、“実効”放射量値ではないのですが、表示単位上は区別も無いため、つい“実効”放射量を測定しているものと思い込んでいる場合もあると思われます。
あるいはまた、一般のUVメータの測定値は [ W ] 単位系で表示されますので、使用者側の意識として、特定の作用関数での測定(“実効”放射量の測定)という概念が抜け落ちてしまい、試料光の分光分布に関わらず、紫外放射自体の強度(すなわち放射量)の絶対値を測定していると誤解して使っている場合が結構多いのが実情ではないでしょうか。
従って、フィルタ方式の測定器によって“実効”放射量を評価したい場合には、便宜上、光源の種類を特定(相対分光分布を固定)した条件の下で、目的とする分光的作用関数(分光応答度)で試料光の物理エネルギーとしての放射量( [ W ] 単位系)を評価・測定するということが行われています。つまり、特定の同一分光分布の光源の下で、という前提での相対比較評価であって、試料光の分光分布が異なれば同じ土俵では適切な定量的比較が困難になってしまうことになります。
以上の様な事情から、フィルタ方式のUVメータを使用する場合は、測定目的の作用関数と測定器の分光応答度、および校正光源について、確認しておくことが非常に重要です。
つまり、その測定器を校正した光源(放射源)と同等の相対分光分布の試料光を測定した時のみ、分光的測定誤差が概ね無視しうる測定結果が得られることになります。これらの両者が異なっていれば、分光的測定誤差が大きく生じる可能性があり、正確な測定はできません。なお、試料光の分光分布が変動しない、という前提条件が有る場合には、分光的測定誤差の発生も一定比率になりますので、絶対値測定ではなく、相対比較測定に使用することは可能です。
以上の説明は、紫外域での測定(UVメータ)を例に説明致しましたが、赤外域での測定(IRメータ)でも、原理的には全く同様なことが言えます。
註釈
≪※1≫ “異色”測光誤差
可視域を対象とする測光・測色では、分光的測定誤差のことを、試料光の分光分布の違いが試料光の“色味”の違いに直結するため「異色測光誤差」と表現することもあります。紫外・赤外においても同様の分光的測定誤差を便宜的に異色測光誤差と称する場合もあるようですが、紫外・赤外では「色」という概念は適用できないので、“異色”測光誤差と言うのは適切な表現とは言えず、その上位概念である分光的測定誤差と言うべきでしょう。
≪※2≫ 紫外域の波長域細分化
紫外域は凡そ 10~380 nm の波長範囲を指しますが、一口に紫外放射と言っても、生ずる作用効果はその波長によって非常に多種多様です。このような事情もあって紫外域は一般に右図の様に細分化して議論されています。市販のフィルタ式UVメータの殆どは近紫外域が測定対象であり、実際にはUV—A用、UV—B用 、UV—C用という様に更に細分化されています。

≪※3≫ UVメータの分光応答度
UVメータに用いられる受光素子はシリコン系の受光素子が一般的ですが、シリコン系の受光素子自体の分光応答度は一般に可視から近赤外にかけての応答度が高く、可視から紫外にかけての短波長側は波長が短くなるほど応答度が低くなっており、近紫外域をどうにかやっとカバーしているような特性になっています。従って、UVメータの受光素子としては、主応答度のある可視~近赤外域をカットして、応答度の低い紫外域を使うということになります。放射測定のために紫外域での分光応答度をフラットにしようとすれば、まだ何とか残っている応答度を更にフィルタで削ることになってしまうため、測定器としての検出能力が更に低下してしまうことになってしまいます。このような事情から、放射量測定用と謳ったフィルタ方式のUVメータの分光応答度でも分光応答度はフラットではないものが殆どであるのが実情です。
≪※4≫ 紫外域での“実効”放射量の単位表記
紫外域での“実効”放射量の単位表記殺菌紫外や有害紫外放射などの特殊な紫外測定については、以下のように、それらの“実効”放射量を明確に示す特別の単位表記が規定されています。
例えば殺菌効果に対しては、右上図のような(等放射パワーに対する)波長毎の殺菌効果作用関数が規定されており、殺菌灯の殺菌力はこれによって測定することになります(第一部第3回参照)。
殺菌紫外の“実効”放射束の単位として“殺菌ワット G−watt”という単位表記が規定されており、例えば殺菌紫外放射照度は [ G−W/m2 ] という単位表記になります。 (JIS Z 8811—1968殺菌紫外線の測定方法)
また、有害紫外放射の測定については、右下図のような(等放射パワーに対する)波長毎の相対分光有害作用関数が規定されており、これに基づく実効的な有害放射束は ”有害ワット W(haz) ” という単位系の表示が規定されています。(”haz” は ”hazard” の意味)
例えば有害紫外放射照度は[ W/m2 (haz) ] という単位表記になります。(JIS Z 8812—1987 有害紫外放射の測定方法)


光と色の話 第二部

第13回 UVメータと分光的測定誤差
測光・測色機器の測定誤差には大別して、測定器の仕組み・構造などの所謂ハードウェアに起因するものと、測定者による使い方に起因するものに分けられます。測定器取り扱いの不注意や理解不足による誤差発生については、本連載の第6回、第7回で照度計や輝度計の場合の例を具体的にお話ししました。
測定器のハードウェアに起因する誤差にも様々な要因がありますが、今回はその内の代表的なものとして分光的測定誤差を採り上げてみたいと思います。分光的測定誤差については、既に本連載 (第10回)でも、可視域でのLED測光の場合について「異色測光誤差」≪※1≫という表現で具体的に説明致しましたが、今回は特に、紫外・赤外域での放射測定において問題化し易い分光的測定誤差について、測定値の単位表記との関連も含めて論じてみたいと思います。
放射量(物理エネルギー)測定 と“実効”放射量測定
光(放射)を測定する対象は大きく分けて、その光自身が有する純粋な物理的エネルギーを評価する測定と、(その光が及ぼす)或る特定の作用効果を評価する測定に分けることが出来ます。前者は、試料光が持つ分光分布をどの波長に対しても均等な重みづけ(フラットな分光的評価関数)で評価して、その光自体の物理エネルギー量である放射量(放射束、放射強度、放射照度、放射輝度等)を測定するものです。また後者は、試料光を受ける側にどれだけの作用・効果を及ぼすかということを、その作用・効果に対応した波長毎の重み付け(分光的作用関数)で、謂わば“実効”放射量を測定するもので、例えば可視域においては人間の視覚に及ぼす刺激量を測定する測光(光束、光度、照度、輝度等の測定)や測色(3刺激値X、Y、Zの測定)等が代表的な例です。
紫外や赤外の測定においても同様に、試料光自体の物理エネルギー量の測定(放射量測定)の場合と、その放射を受ける側の影響・効果を測定・評価する測定(“実効”放射量測定)に分けられます。紫外・赤外域において試料光が及ぼす作用効果にも様々なものがあり、例えば紫外域における(人間に対する)有害紫外放射、殺菌効果作用、樹脂の紫外線硬化作用、赤外域における温熱効果作用、白内障・・・・等、様々な作用効果が知られています。人間に対する有害紫外放射にも、人体の部位(眼や皮膚など)によって、その作用・効果の分光的作用関数は当然異なります。
測定器の分光応答度 と 分光的測定誤差
測定器の分光的評価関数である分光応答度は、放射量測定の場合には分光的にフラットであること、“実効”放射量測定の場合にはその効果に対する分光的作用関数に合致していること、が必要になります。これらの分光応答度を実現する方法としては、分光方式とフィルタ方式があります。
分光方式の測光機器の場合は、試料光の分光分布を波長成分毎に細かく分割して測定したデータに対して数値設定された分光的評価関数(放射量測定の場合には定数、“実効”放射量測定の場合には分光的作用関数)を用いて測定値を算出しますので、原理的に分光的測定誤差は非常に小さく抑えられます。また分光方式は、複数種類の分光的評価関数をデータとして持っておくことができますので、放射量測定にも“実効”放射量測定にも容易に対応できます。
フィルタ方式は、使用する受光素子に光学フィルタを掛けて目的の分光的評価関数に合わせた分光応答度を作り出すものです。受光素子の分光応答度と光学フィルタの分光透過率の組合せで出来上がる受光センサの実際の分光応答度は、目的とする分光的評価関数に対して、対象とする全波長域に亘って精度良く一致させることはなかなか困難で、(第10回の標準分光視感効率
V( λ )に対する解説図のように)差異のある波長域がどうしても残ってしまいます。
このような特性のフィルタ方式の受光センサで測定した場合、試料光の分光分布に依存して誤差の発生の仕方が変動する現象が生じます。分光応答度の差異が大きい波長域に、試料光の分光分布の高い部分が重なると、どうしても測定誤差が大きく出てしまいます。つまり、試料光の分光分布に依存して誤差の発生量が変動するということになってしまいます。これが分光的測定誤差です。
このように、分光的測定誤差の観点からは、測定原理的に分光方式の方が望ましいのですが、分光方式の測定器はどうしても高価になり勝ちで取り扱いにも注意が必要なため、安価で取り扱いやすいフィルタ方式が多方面で使われています。
分光的測定誤差が生じ易いフィルタ方式の場合でも、試料光の分光分布が既知の場合等は、測定器の校正光源の分光分布との関係から予め補正係数(CCF:color compensating factor)を求めておいて、ナマの測定値にその補正係数を乗じることによって、誤差を補正することは可能です。しかし、試料光の分光分布が不明な場合には補正処理ができませんし、分光分布が変動する場合には、全てに対して補正係数を準備しておくことは現実問題としてなかなか対応が難しいという問題があります。
このような分光的測定誤差は、別に可視域での測定に特有な訳ではなく、当然の事ながら紫外域や赤外域での測定でも同じことが起こり、測定単位表示との関係もあって、より問題化し易いと言えます。以下にUVメータの場合について具体的に考えてみます。
UVメータの分光応答度特性
一口にUVメータと言っても、測定対象とする紫外波長域も様々であり、機種によって受光センサの分光応答度も異なっています≪※2≫。 一般用のUVメータ(紫外線強度計)として供給されているもの(特に小型のハンディタイプのもの)は、フィルタ方式のものが多く、センサの分光応答度は、例えば右図のように、測定対象波長範囲全体に亘ってフラットになっている訳ではありません≪※3≫。 このような分光応答度のセンサで測定した結果が、波長毎の重みづけが異なっているのに、物理エネルギー量としての放射量測定値(ワット [ W ] 単位系)で表示されています。 この測定値表示の意味を理解せずに、表示された測定値をそのまま受け取ってしまうと、大きな測定誤差に繋がってしまうことがあるので注意が必要です。この測定値の解釈には、測定器の校正条件が大きく関係しています。

放射量測定値の校正
測定器の校正は、校正に適した分光分布を持つ特定種類の管理された標準光源を規定された条件で点灯させ、校正光源と測定器を所定の位置関係に配置した条件の下で行われます。この条件下においては、放射量値が、校正値として例えばUV放射照度計の場合は [ W/m2 ] 単位の放射照度値で値付けされていますので、測定器をその条件下で動作させて校正値の表示となるように測定器を調整して校正する訳です。
従って、校正光源と同等の分光分布を持つ試料光の場合に限り、測定結果も物理的エネルギーとしての放射量の絶対値として受け取ることができます。しかし、校正光源と異なる分光分布の試料光の場合には、当然分光的測定誤差が生じてしまいます。
なお、試料光の分光分布が校正光源の分光分布と異なっていても、試料光の分光分布が既知である場合には、(理論的には上述しました様に手間はかかりますが)補正係数により分光的測定誤差を補正することは可能です。また、試料光の分光分布が固定されている条件の場合には、分光的測定誤差の発生も一定比率になりますので、相対値としての比較測定はできると言えます。
可視域での測光の場合、フィルタ方式の測定器の分光応答度は、理論的分光評価関数、例えば標準分光視感効率 V( λ ) に対して、完全には一致しきれずに差異が残っている波長帯が存在するのですが、全体的には概ね近似しています。これに対して、UVメータの場合、物理エネルギーとしての放射量測定の為には理論的にフラットな分光応答度であるべきところが、実際には上図の様なかけ離れた分光応答度特性の形状である場合が殆どです。従って、可視域での測光の場合に比べて、分光的測定誤差の出方は格段に大きくなってしまいます。つまり、試料光の分光分布が不明確な場合、フィルタ方式のUVメータでの測定値は絶対値としては大きな分光的測定誤差の発生リスクを孕んでいると言えます。
放射量の単位 と“実効”放射量の単位
可視域の測光の場合には、分光的評価関数(標準分光視感効率 V( λ ) 等)に対応した単位系も明確に規定され、それに対応する測光量の単位系( lm、cd、lx 等)もきっちりと整備されています(第一部第7回≪※2≫)。標準分光視感効率 V( λ )は人間の視覚の代表特性で、作用関数としては人間生活に極めて密着したものであるため、他の作用関数に対して圧倒的に重要で、多方面に亘って盛んに使用されており、測定器の使用者側にもかなり周知されています。放射量([ W ]単位系)と “実効”放射量である測光量([ lm ] 単位系)が混同されることは殆ど無く、概ね適正に使い分けられている場合が多いと考えられます。
それに対して、紫外や赤外でもその目的によってはそれに応じた分光的作用関数が規定されてはいますが、その用途は極めて限定的・専門的であって、可視域の標準分光視感効率 V( λ ) のように、非常に広い範囲の人間生活に亘って一般的に高頻度に使用されている訳ではないのが実情です。そのような背景もあって、紫外域や赤外域の測定においては、特別の場合≪※4≫を除いて、それぞれの作用・効果毎に個別の単位系が整備されている訳ではありません。
“実効”放射量(例えば紫外放射による日焼けへの影響、等)を評価したい場合でも、その影響・効果に対する分光的作用関数をあまり意識せずに汎用のフィルタ方式のUVメータを使用して測定している場合もあるようです。この場合の測定値は(かなりの分光的測定誤差を含んでいる可能性はあるものの) [ W ] 単位系で放射量値が表示されており、“実効”放射量値ではないのですが、表示単位上は区別も無いため、つい“実効”放射量を測定しているものと思い込んでいる場合もあると思われます。
あるいはまた、一般のUVメータの測定値は [ W ] 単位系で表示されますので、使用者側の意識として、特定の作用関数での測定(“実効”放射量の測定)という概念が抜け落ちてしまい、試料光の分光分布に関わらず、紫外放射自体の強度(すなわち放射量)の絶対値を測定していると誤解して使っている場合が結構多いのが実情ではないでしょうか。
従って、フィルタ方式の測定器によって“実効”放射量を評価したい場合には、便宜上、光源の種類を特定(相対分光分布を固定)した条件の下で、目的とする分光的作用関数(分光応答度)で試料光の物理エネルギーとしての放射量( [ W ] 単位系)を評価・測定するということが行われています。つまり、特定の同一分光分布の光源の下で、という前提での相対比較評価であって、試料光の分光分布が異なれば同じ土俵では適切な定量的比較が困難になってしまうことになります。
以上の様な事情から、フィルタ方式のUVメータを使用する場合は、測定目的の作用関数と測定器の分光応答度、および校正光源について、確認しておくことが非常に重要です。
つまり、その測定器を校正した光源(放射源)と同等の相対分光分布の試料光を測定した時のみ、分光的測定誤差が概ね無視しうる測定結果が得られることになります。これらの両者が異なっていれば、分光的測定誤差が大きく生じる可能性があり、正確な測定はできません。なお、試料光の分光分布が変動しない、という前提条件が有る場合には、分光的測定誤差の発生も一定比率になりますので、絶対値測定ではなく、相対比較測定に使用することは可能です。
以上の説明は、紫外域での測定(UVメータ)を例に説明致しましたが、赤外域での測定(IRメータ)でも、原理的には全く同様なことが言えます。
註釈
≪※1≫ “異色”測光誤差
可視域を対象とする測光・測色では、分光的測定誤差のことを、試料光の分光分布の違いが試料光の“色味”の違いに直結するため「異色測光誤差」と表現することもあります。紫外・赤外においても同様の分光的測定誤差を便宜的に異色測光誤差と称する場合もあるようですが、紫外・赤外では「色」という概念は適用できないので、“異色”測光誤差と言うのは適切な表現とは言えず、その上位概念である分光的測定誤差と言うべきでしょう。
≪※2≫ 紫外域の波長域細分化
紫外域は凡そ 10~380 nm の波長範囲を指しますが、一口に紫外放射と言っても、生ずる作用効果はその波長によって非常に多種多様です。このような事情もあって紫外域は一般に右図の様に細分化して議論されています。市販のフィルタ式UVメータの殆どは近紫外域が測定対象であり、実際にはUV—A用、UV—B用 、UV—C用という様に更に細分化されています。

≪※3≫ UVメータの分光応答度
UVメータに用いられる受光素子はシリコン系の受光素子が一般的ですが、シリコン系の受光素子自体の分光応答度は一般に可視から近赤外にかけての応答度が高く、可視から紫外にかけての短波長側は波長が短くなるほど応答度が低くなっており、近紫外域をどうにかやっとカバーしているような特性になっています。従って、UVメータの受光素子としては、主応答度のある可視~近赤外域をカットして、応答度の低い紫外域を使うということになります。放射測定のために紫外域での分光応答度をフラットにしようとすれば、まだ何とか残っている応答度を更にフィルタで削ることになってしまうため、測定器としての検出能力が更に低下してしまうことになってしまいます。このような事情から、放射量測定用と謳ったフィルタ方式のUVメータの分光応答度でも分光応答度はフラットではないものが殆どであるのが実情です。
≪※4≫ 紫外域での“実効”放射量の単位表記
紫外域での“実効”放射量の単位表記殺菌紫外や有害紫外放射などの特殊な紫外測定については、以下のように、それらの“実効”放射量を明確に示す特別の単位表記が規定されています。
例えば殺菌効果に対しては、右上図のような(等放射パワーに対する)波長毎の殺菌効果作用関数が規定されており、殺菌灯の殺菌力はこれによって測定することになります(第一部第3回参照)。
殺菌紫外の“実効”放射束の単位として“殺菌ワット G−watt”という単位表記が規定されており、例えば殺菌紫外放射照度は [ G−W/m2 ] という単位表記になります。 (JIS Z 8811—1968殺菌紫外線の測定方法)
また、有害紫外放射の測定については、右下図のような(等放射パワーに対する)波長毎の相対分光有害作用関数が規定されており、これに基づく実効的な有害放射束は ”有害ワット W(haz) ” という単位系の表示が規定されています。(”haz” は ”hazard” の意味)
例えば有害紫外放射照度は[ W/m2 (haz) ] という単位表記になります。(JIS Z 8812—1987 有害紫外放射の測定方法)